寄稿ライター
3ヶ月前
医師NISA 「売り時」 っていつ?
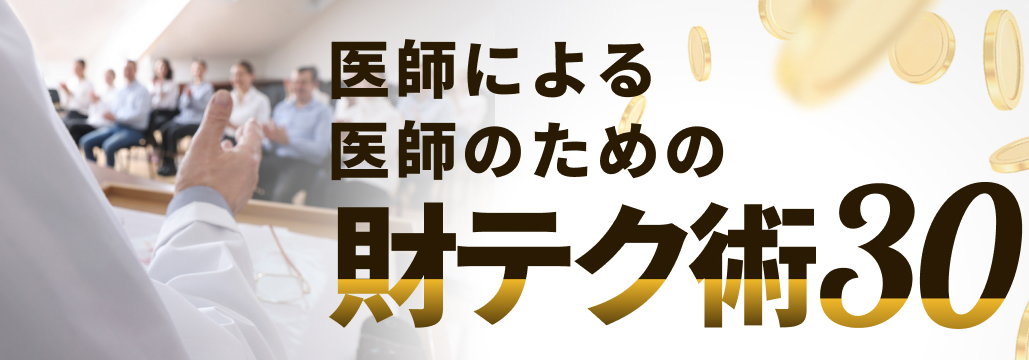
新NISAをしている先生も多いでしょう。 連載 「医師による医師のための財テク術」 第30回では、 NISAを実際に運用していく中で見落としがちな注意点──売却のタイミングや相続、 海外留学などの取り扱いについて解説します。
※本記事は筆者の個人の見解であり、 投資成果を保証するものではありません。 投資は自己責任でお願いいたします。
NISA株の売り時と相続
前回で述べたように、 短期売買は投資枠の非効率な使用につながるため、 新NISAでは原則として長期保有が望ましいとされています。 では、 どんなときに売るべきなのか。
筆者が考える売却のタイミングは、 「資金が必要になったとき」 です。 たとえば留学や老後資金など、 通常の収入ではまかないきれない大きな出費がある場合、 NISA枠で積み上げた資産を取り崩すことは合理的です。

写真はイメージです
新NISAでは売却翌年にその分の投資枠が復活します。 これにより、 「いざという時は売却できる」 という安心感が、 日々の投資判断を後押しする要素にもなるでしょう。
また、 投資対象の見直しも検討すべきタイミングのひとつです。 たとえばS&P500に投資している場合、 米国が明確に経済的覇権を失ったと判断できる状況であれば、 投資戦略自体の再構築が必要になります。 ただし、 一時的な暴落だけでは判断すべきではありません (第7回参照)。

写真はイメージです
気をつけたいのが、 「死ぬときに資産が最も多い」 という状況です。
NISAで増えた資産は相続税の対象になります。 新NISAによる長期運用は数千万円規模に成長する可能性があり、 相続時に多額の税負担が発生するリスクもあります。
NISA口座保有者が死亡した場合、 「非課税口座開設者死亡届出書」 の提出が必要です。 死亡日までの運用益・配当は非課税ですが、 その日をもって課税口座に移され、 相続税が発生します。
相続税対策としては、 以下のような方針が挙げられます。
・自分の寿命を意識して効果的に使い切る
・暦年贈与を利用
・相続時精算課税制度を活用
・不動産に変えて相続税評価額を下げる
・資産管理法人を設立する
ただし、 どれも人によって最適解が異なり、 税制改正も頻繁に行われるため、 専門家 (税理士) に必ず相談することをおすすめします。
海外留学時のNISA口座

写真はイメージです
海外留学を予定している医師にとって、 NISA口座の扱いは意外な落とし穴です。
NISAはあくまで 「日本居住者」 を対象とした制度であり、 長期海外滞在中は原則として新規取引ができなくなります。
2019年からは 「継続適用届出書」 を提出することで、 やむを得ない事情による海外転居であれば最大5年間、 口座維持が可能となりました。 ただしこの適用は転勤等に限定されており、 自主的な留学が該当するかは証券会社によって判断が分かれるため、 事前に確認が必要です。

写真はイメージです
具体的には、 出国前日までに 「継続適用届出書」、 帰国後に 「帰国届出書」 を提出する必要があります。 5年以内の帰国であればNISA口座の復活が可能ですが、 5年を超えると自動的に課税口座に移される点には注意が必要です。
現在はSBI証券、 楽天証券、 マネックス証券といった大手ネット証券がこの制度に対応していますが、 商品によっては一部取引が制限されるケースもあるため、 各社のホームページで詳細を確認してください。
証券会社の選び方・変更の注意点

写真はイメージです
NISA口座を開設する証券会社は自由に選択可能です。 一般的には先述のSBI証券、 楽天証券、 マネックス証券の3社が主流ですが、 最近ではmoomoo証券などの新興勢力も注目されています。 ただし、 moomooは成長投資枠のみに対応、 iDeCo非対応など、 制限があるため注意が必要です。
NISA口座は1人1口座までで、 証券会社の変更は翌年度からのみ可能です。 変更後の口座において、 前年度の使い残したNISA枠を使うことはできますが、 前の口座で購入した商品を新しいNISA口座に移すことはできません。
移動させたい場合は売却が必要となり、 その売却分が翌年の枠として戻ってくる形になります。 変更手続き自体は可能ですが、 管理が煩雑になること、 枠の消化効率が下がる可能性があるため、 よほどの理由がない限りは変更しない方が無難です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。 本日のTake Home Messageは
- NISA株の売り時は他の理由で資金が必要になったときで、 売却しても翌年に投資枠が復活する
- 相続税の対象になるので、 相続税対策も必要
- 海外留学する前に手続きをすることで5年間NISA口座の維持ができる
となります。 次回は、 iDeCoについて考えてみましょう。
プロフィール
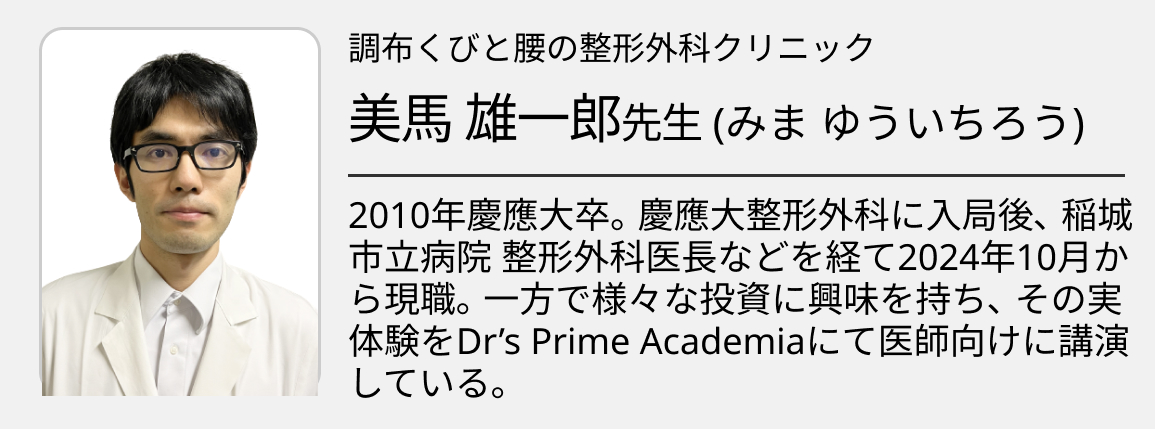
HOKUTO関連コンテンツ
- 投資は研修医から始めるべし!その心得とは
- 投資よりも外勤しまくる方が稼げる?
- 医師はインフレに弱い? インフレ社会を生き抜く術とは
- インフレに弱い医師、絶対してはいけないこと
- 医師にオススメの投資銘柄は?
- 【医師必見】投資の王道 S&P500の欠点は?
- 医師必見! 暴落は敵か味方か
- 多忙な医師、株価の暴落を予見できるのか
- 医師の資産、どれだけ投資に回せばいいの?
- 骨にしみる痛税感…医師ができる節税は?
- 「赤字にして節税」 ってホントにいいの?
- 「借金は悪」 なのか…融資について考える
- 医師が勧誘される代表格 「ワンルームマンション投資」 ってどうなの?
- 医師必見!1Rマンションのキャッシュフローの罠
- 医師必見! 「1Rマンションで節税」に騙されてはいけない
- 「先生だけ特別に…」 は信じていい?
- 1Rマンション投資、 サブリース契約はあり?
- どうして1Rマンション投資がなくならないのか
- 筆者オススメ!1LDKマンション投資って? (前編)
- 筆者オススメ!1LDKマンション投資って? (後編)
- 中古アパート投資で一気に節税?
- 節税対策のはずが、 余計な税金を払うハメに…
- 【医師注目】不動産の 「一棟投資」 について考える
- 医師の投資、 地方の高利回り物件で一攫千金?
- 医師の投資、 NISAの注意点
- NISAをしてはいけない医師とは
- 医師NISA 徹底比較!
- 医師NISA、 適切な投資のタイミングは?
- 医師NISA、 一括投資と分割投資どちらがいいの?

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。