寄稿ライター
3日前
撤退戦のすゝめ
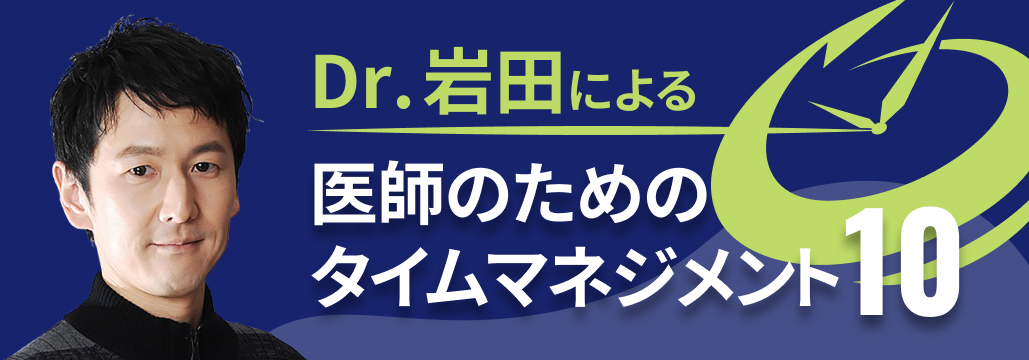
物価高になっても診療報酬は定額なまま。 人件費は上がるのに、 「働き方改革」 でサービス残業もさせられない (させるべきでもない)。 構造的に、 日本の病院は赤字体質です。 連載 「Dr. 岩田による医師のためのタイムマネジメント」の第10回では、 日本医療の行き着く先について考察します。
診療報酬の物価スライドは難しい
赤字体質であるならば診療報酬を物価上昇にスライドさせて上げるべき、 というのが 「正論」 なわけですが、 これも難しい。 なぜなら物価は上がっても、 物価高を差し引いた日本の実質賃金はむしろ下がっているのです。
厚生労働省が公表している毎月勤労統計調査によると、 2025年4月(速報値)の実質賃金 (名目賃金から物価変動の影響を除いたもの) は前年同月比1.8%減少。 4ヵ月連続のマイナスとなりました*¹⁾。
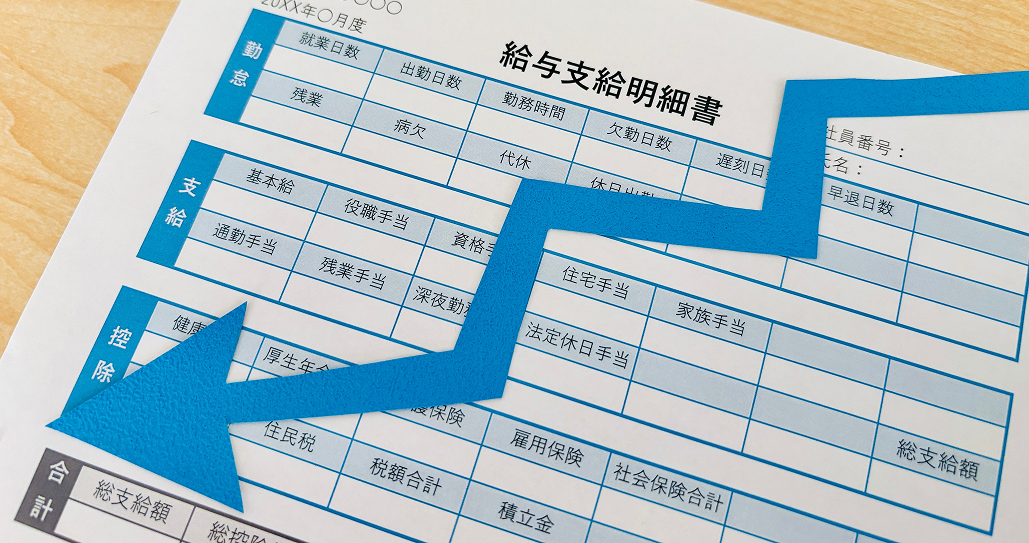
画像はイメージです
この状態で診療報酬を上げるとなると、 社会保険料の値上げは必然です。
ただ、 すでに日本では税金や社会保険料などの 「国民負担率」 が5割近くになっています。 高齢者の医療費を支える若い世代にさらなる負担を強いることは、 両者の間に軋轢を生み、 社会の 「分断」 を加速させてしまうかもしれません。
日本の医療は八方塞がり

画像はイメージです
結論、 若い世代にこれ以上負担は強いられないですが、 医療費は増大する一方です。
医療費増大の最も大きな理由は医学の進歩です。 医学の進歩自体を止めろというわけにもいきません。
とはいえ、 病院の経営状態がこれ以上悪化すれば、 経営破綻を起こすところも出てくるでしょう。 医療の供給が途絶えれば、 今度困るのは患者さんです。
日本の医療は、 どこを向いてもよい条件がないのです。
「医は仁術なり」 は今や昔

画像はイメージです
どうすればいいのか。 我々医療者はついつい、 医療業界の枠内だけでものを考えてしまいがちです。
病院の経営は本来、 コストや収支の問題なので、 「一般化」 が可能です。 つまり、 お金のやり取りがあるすべてのセクターと同じような原則を適用できるんじゃないか、 と考えるわけです。
「医療は人の命がかかっている。 他のビジネスと同じ考え方ができるわけがない。 一緒にするな」 という批判を受けることは多いです。
特に 「医療においてお金の話をしてはいけない。 医は仁術なり」 と言われたものです。

画像はイメージです
こういったことは、 診療報酬で医療機関が儲かることができ、 若い世代が多く、 人口も経済も右肩上がりで成長一していた時代に言えたことです。
国立病院や自治体病院が赤字でもどこかから補填してもらえましたし、 企業の病院が赤字に陥っても本業が穴埋めしてくれました。
金の話 「しか」 でない病院の会議
しかし、 今は国にも自治体にもカネはありません。 民間企業も儲かっていません。 バブル期の日本企業は、 世界の時価総額ランキングの上位に名を連ねていましたが、 今、 世界トップ50に入ることができるのはトヨタ自動車くらいです*²⁾。

画像はイメージです
そもそも、 今病院の運営会議などに参加すると、 経営幹部は金の話 「しか」 していません。 診療の質や患者の権利といったテーマはほとんど議題にならず、 とにかくカネの話ばかりです。 開業医も同じような状況だと聞き及んでいます。
ぼくは、 「医療の世界でカネの話をしたらあかん」 とは少しも思いません。 貴重な社会保険料を預かって診療しているのですから、 コスト効果を考えずに湯水のように医療費を使うことは全く不見識だと考えます。
貧すれば鈍する
とはいえ、 カネの話 「しか」 できないのはもっと困ります。 もはや日本の病院は1にカネ、 2にカネの話で、 膨らんでいく赤字をどうしようかということ 「しか」 考えられないくらい追い詰められているのです。

画像はイメージです
貧すれば鈍する――。 昔は病院の先輩たちが 「医療の理想とは」 「診療の真髄とは」 と高い理念を論ずる光景をよく見かけました。 しかし、 今、 そのような理念を滔々と語るドクターは本当に減りました。
そして、 若手医師たちは現場から立ち去り、 「美容」 などに活躍の場を転じているのです。
最善策は 「撤退するが勝ち」
ぼくは、 このような危機的な状況ではゼロベースで 「医療をサバイブさせる」 ことから逆算し、 なんとか医療が沈没しないように模索するのが最善策だと思っています。
つまりは撤退戦です。 「撤退はするが、 全滅はしない」。 玉砕しないためには逃げるが勝ち、 なのです。

画像はイメージです
兵庫県では公立病院と民間病院の合併など、 聖域なき集約化が進んでいます。 集約化はもっと進めなければならないでしょう。 「医局」 の壁も取っ払い、 複数の大学医局で一つの診療科を賄うくらいの覚悟も必要でしょう。
集約化は患者に我慢を強います。 通院の遠距離化や支払い増はもう回避できません。 処方薬のOTC化も一定レベルでは必要不可欠です。
医師など医療者の収入も減る可能性が高いです。 こうやって皆で泥をすすってでも生き残りを目指す他ないのです。 あとは、 覚悟の問題です。
避けるべきは、 先送りの 「ゆでガエル」
では、 どこまで撤退するか。 撤退ラインの設定で今後は大いに揉めまくることでしょう。 ただ、 いくら揉めても撤退することそれ自体には変わりはありません。
現状維持で問題先送り、 そしてゆでガエルになって死亡、 というシナリオだけは避けねばならないのです。
監修・執筆医
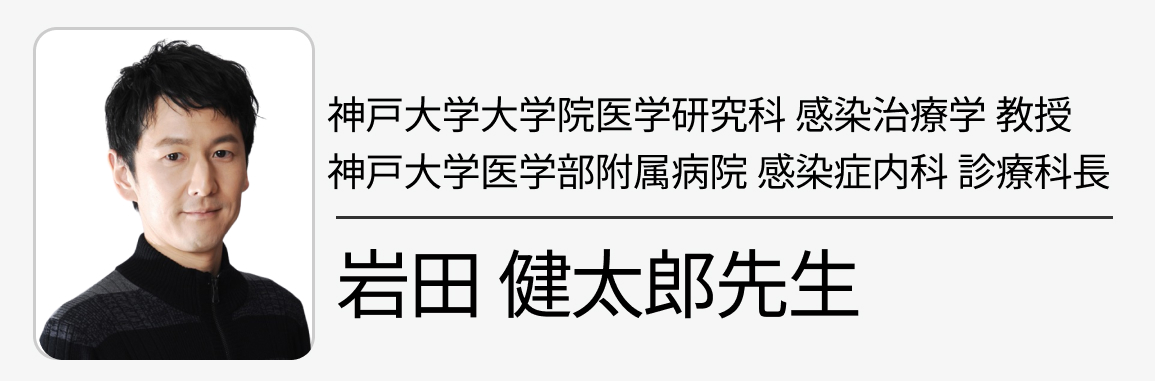
略歴
島根医科大 (現・島根大) 卒。 沖縄県立中部病院研修医、 セントルークス・ルーズベルト病院 内科研修医を経て、 ベスイスラエル・メディカルセンター感染症フェローに。 北京インターナショナルSOSクリニックを経て、 2004年に亀田総合病院で感染症科部長、 同総合診療・感染症科部長歴任。 2008年より現職。
「タイムマネジメントが病院を変える」 など著書多数。 米国内科専門医、 感染症専門医、 感染管理認定CIC、 渡航医学認定CTHなどのほか、 漢方内科専門医、 ワインエキスパート・エクセレンスやファイナンシャル・プランナーの資格をもつ。
出典
- ¹⁾ 厚生労働省 : 毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果速報【報道発表資料】
- ²⁾STARTUPS JOURNAL : 平成最後の時価総額ランキング。 日本と世界...その差を生んだ30年 (2019/07/17)
関連コンテンツ
- ムダな残業、会議が多すぎる件について
- 嬉々として残業する医師
- 「働き方改革」 は単なる労働時間カットではない
- 改革を拒む抵抗勢力たち
- 言えない組織は、弱い組織
- 働き方改革は、 医療の質を下げるのか?
- そろそろ地方会は廃止した方が良い
- 「定期接種」 「任意接種」 の区別はただの詭弁
- PubMedの未来

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。