HOKUTO編集部
4日前
鑑別診断の整理に活用!考えを深めるプロンプトの使い方
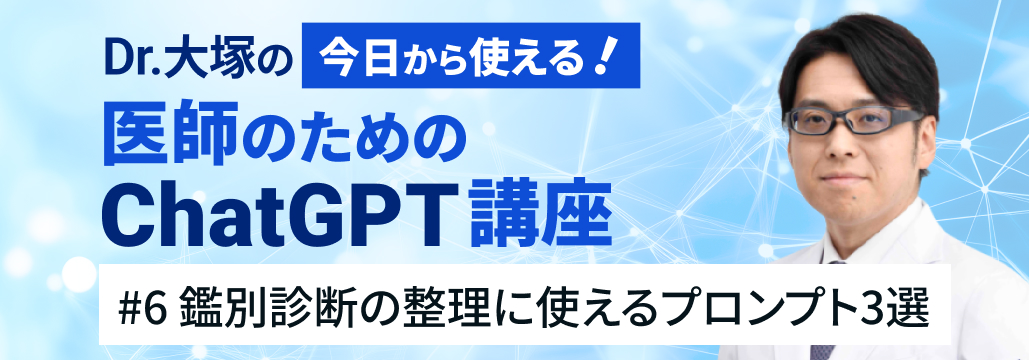
医療での生成AI活用のトップランナー、 大塚篤司先生によるChatGPT講座。 今回は、 鑑別診断の整理に使える3つのプロンプトを紹介します!
はじめに
前回は、 学会スライド作成を支援するプロンプトを紹介した。 今回は、 日常診療の中核をなす 「鑑別診断」 に焦点を当てる。
診断は医師の最も重要な仕事の1つであるが、 症状が非典型的な場合や、 複数の疾患が併存する場合、 見落としのリスクは常に存在する。 ChatGPTを 「診断の思考パートナー」 として活用することで、 鑑別診断の網羅性を高め、 診断精度の向上に貢献できる。
ただし、 AIは 「診断を下すもの」 ではなく、 あくまで 「医師の思考を整理し、 見落としを防ぐための補助ツール」 であることを、 改めて強調しておく。
今回は、 「症状から鑑別を広げる」 「優先順位をつける」 「次の一手を考える」 という診断プロセスの3つのステップに対応した、 定番プロンプトを紹介する。
バックナンバー
今日から使える!3つのプロンプト
1. 症状・所見から鑑別診断を系統的に展開
活用シーン
患者の主訴と主要な所見から、 考えられる鑑別診断を系統的・網羅的にリストアップし、 見落としやすい疾患も含めて検討する。
プロンプト例
あなたは総合診療医です。
以下の患者情報から、 考えられる鑑別診断を系統的にリストアップしてください。
頻度の高いものから稀なものまで、 見落としてはいけない疾患も含めて提示してください。
【患者情報】
年齢・性別 : [例 : 65歳男性]
主訴 : [例 : 2週間続く乾性咳嗽と労作時呼吸困難]
既往歴 : [例 : 高血圧、 2型糖尿病]
内服薬 : [例 : アムロジピン、 メトホルミン]
社会歴 : [例 : 喫煙歴30pack-years、 建築業]
主な身体所見 : [例 : 両側下肺野でfine crackles聴取、 ばち指なし]
基本的検査 : [例 : WBC 8,500、 CRP 2.3、 胸部X線で両側下肺野にすりガラス陰影]
【出力形式】
1. 可能性の高い鑑別診断 (Common)
- 疾患名 : 簡潔な理由
- (3-5疾患)
2. 見落としてはいけない鑑別診断 (Critical)
- 疾患名 : なぜ重要か
- (2-3疾患)
3. 稀だが否定すべき鑑別診断 (Rare but important)
- 疾患名 : 示唆する所見
- (2-3疾患)
4. 系統別の鑑別診断
呼吸器系
-
循環器系
-
その他の系統
-
活用のコツ
● 患者情報は匿名化し、 個人を特定できる情報は含めない。
● 社会歴・職業歴は鑑別に重要であるため、 可能な限り入力する。
● AIの出力は 「思考の出発点」 として使い、 必ず自身の臨床経験と照合する。
● 「見落としてはいけない疾患」 のセクションは、 特に注意深く検討する。
2. 鑑別診断の優先順位付け・検査計画立案
活用シーン
リストアップした鑑別診断に対して、 臨床的な優先順位をつけ、 それを確定または除外するための検査計画を立案する。
プロンプト例
あなたは診断推論に精通した内科医です。
以下の鑑別診断リストに対して、 検査の優先順位と具体的な検査計画を提案してください。
【現在の鑑別診断リスト】
1. 間質性肺炎 (薬剤性、 特発性)
2. 心不全
3. 肺癌 (原発性、 転移性)
4. 感染症 (非定型肺炎、 結核)
5. 職業性肺疾患
【患者の状態】
- 全身状態 : [例 : 安定、 SpO₂ 94% (室内気) ]
- 緊急度 : [例 : 準緊急]
- 検査可能な環境 : [例 : 総合病院外来]
【出力形式】
1. 診断確定の戦略
Phase 1 : 初期評価 (当日実施)
- 検査項目 :
- 各検査で確認したいポイント :
- 予想される所要時間 :
Phase 2 : 追加精査 (1週間以内)
- 検査項目 :
- 実施の判断基準 :
Phase 3 : 専門的検査 (必要時)
- 検査項目 :
- コンサルテーション先 :
2. 各鑑別診断の確定/除外のポイント
- 間質性肺炎 : [特徴的な検査所見]
- 心不全 : [特徴的な検査所見]
- (以下同様)
3. Red flagsと対応
- 見逃してはいけない所見 :
- 緊急対応が必要な場合 :
活用のコツ
● 検査の侵襲性やコスト、 患者負担を考慮した現実的な計画を心がける。
● 「Phase分け」 により、 段階的な診断アプローチを明確化する。
● Red flagsは必ず確認し、 見落としを防ぐ。
● 各施設の検査体制に応じて、 実施可能性を検討する。
3. 診断に迷った時の思考整理と次の一手
活用シーン
初期検査で診断が確定しない場合や、 典型的でない所見がある場合に、 診断推論を整理し、 次のアプローチを検討する。
プロンプト例
あなたは診断困難症例の相談を受ける指導医です。
以下の症例について、 診断推論を整理し、 次の診療方針を提案してください。
【これまでの経過】
初診時の症状 : [詳細に記載]
実施した検査と結果 :
- [検査1] : [結果と解釈]
- [検査2] : [結果と解釈]
- (すべて列挙)
初期診断 : [当初考えた診断]
治療反応 : [実施した治療と反応]
【現在の問題点】
- [例 : ステロイドに部分的に反応するが、 画像所見が典型的でない]
- [例 : 炎症反応は改善したが、 症状が持続]
【出力形式】
1. 診断推論の再整理
説明できる所見
- 所見 : どの診断と合致するか
説明困難な所見
- 所見 : なぜ典型的でないか
診断の再考
- 当初の診断を支持する根拠 :
- 当初の診断に反する根拠 :
- 新たに考慮すべき鑑別診断 :
2. 診断確定への3つのアプローチ
アプローチ1 : [方針名]
- 具体的方法 :
- メリット/デメリット :
- 期待される情報 :
アプローチ2 : [方針名]
- (同様に記載)
アプローチ3 : [方針名]
- (同様に記載)
3. 推奨する次の一手
- 優先順位1位の理由 :
- 実施のタイミング :
- 判断のポイント :
活用のコツ
● 「説明困難な所見」 に注目することで、 診断の見直しポイントが明確になる。
● 複数のアプローチを比較検討することで、 思考の幅が広がる。
● 経過観察も立派な 「診断的アプローチ」 として含める。
● 専門医へのコンサルテーションのタイミングも検討に含める。
効果的な活用に!実践的アドバイス
診断推論の質を高めるコツ
情報の構造化
散在する情報を整理してから、 プロンプトに入力する。
段階的な使用
一度にすべてを解決しようとせず、 段階的に内容を深めていく。
批判的思考
AIの提案を鵜呑みにせず、 常に 「なぜそう考えるか」 を考える。
よくある失敗と対策
情報不足での質問
基本的な情報 (年齢、 性別、 主訴) は必須。
過度な依存
AIの提案はあくまで参考情報である。 最終判断は医師が行う。
検証の省略
提案された鑑別診断は、 必ず最新のガイドラインで確認する。
診断におけるAI活用の倫理と限界
法的・倫理的配慮
診断は医師の専権事項であり、 AIはあくまで診断支援ツールである。
患者への説明においても、 「AIが診断した」 という表現は避け、 「診断の参考にした」 程度に留めることが重要である。
技術的限界の認識
現在のChatGPTは2024年6月末までの情報で学習しており、 最新の診断基準や治療法を反映していない可能性がある。
また、 画像診断や検査データの直接的な解釈はできないため、 これらは医師自身で判断する必要がある。
今回は、 鑑別診断の思考プロセスを支援する3つのプロンプトを紹介した。 これらは 「診断の網羅性を高める」 「検査計画を体系化する」 「行き詰まった時の突破口を見つける」 という、 診断の各段階で活用できる。
重要なのは、 「ChatGPTを”第二の脳”として活用しつつも、 最終的な診断責任は医師にあることを常に意識する」 ことである。 AIとの適切な協働により、 診断の質を高め、 患者により良い医療を提供できるようになることが目標である。
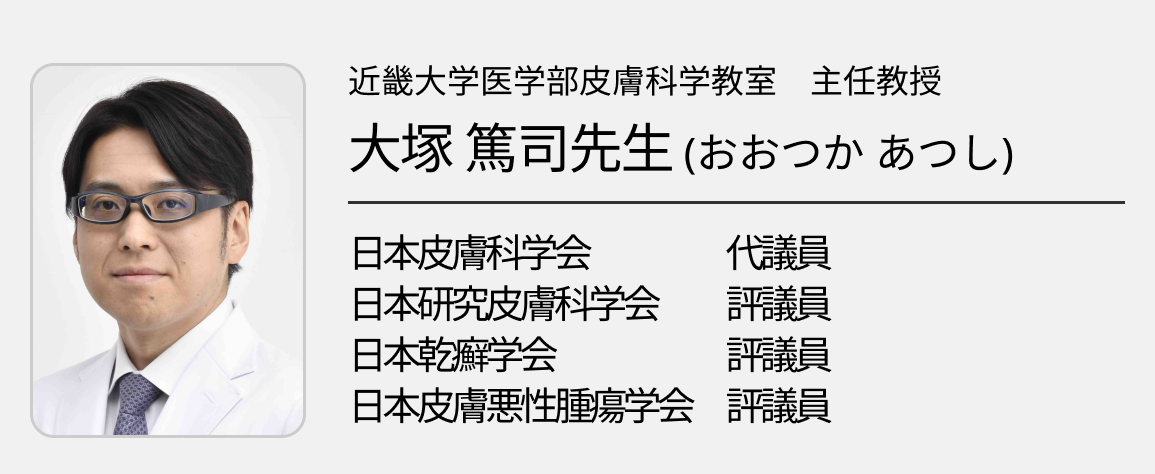
大塚先生執筆の書籍はこちら!
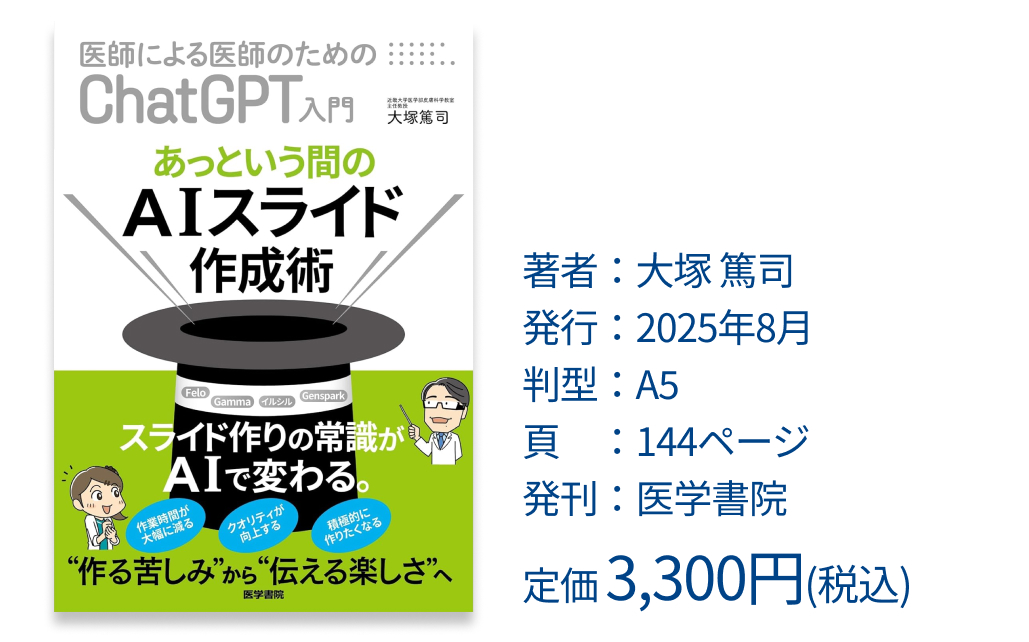
医師による医師のためのChatGPT入門
あっという間のAIスライド作成術
2025年8月発刊! 「スライドづくりの時間が足りない」 を一瞬で解決。 各種生成AIを場面別に使い分け、 構成やデザインをあっという間に整える実践書。 「伝える」 スライド作成のテクニックも公開!
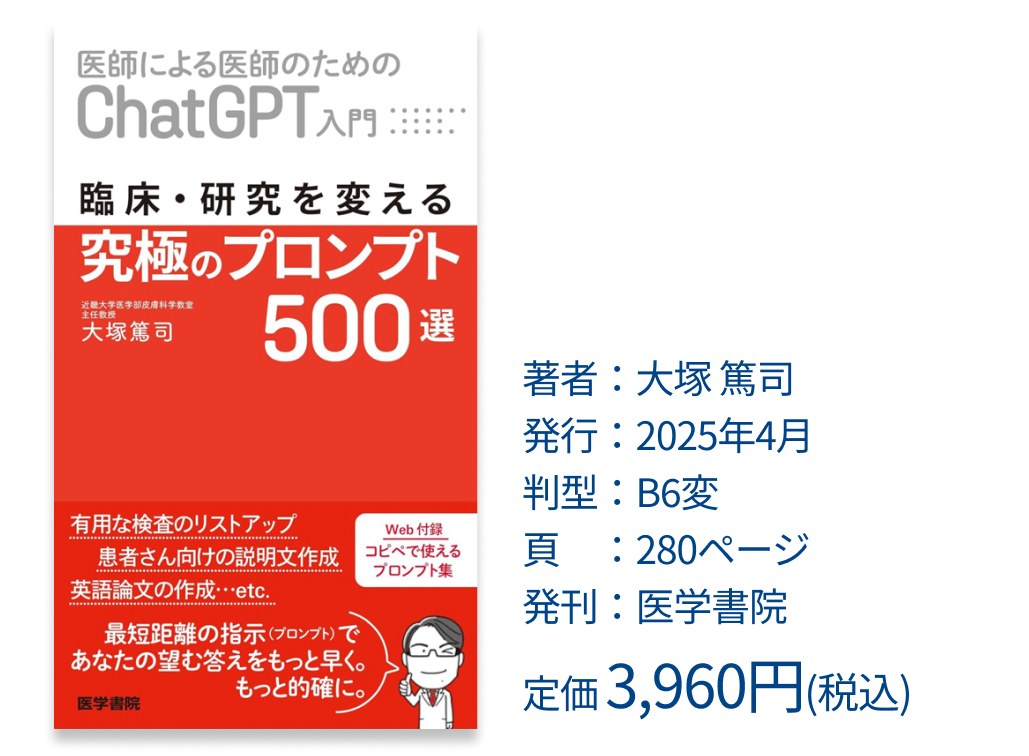
医師による医師のためのChatGPT入門
臨床・研究を変える究極のプロンプト500選
2025年4月発刊!医療現場でそのまま使えるプロンプトをテーマ別に収載。 日々の診療・教育・研究に役立つ実践的な1冊。
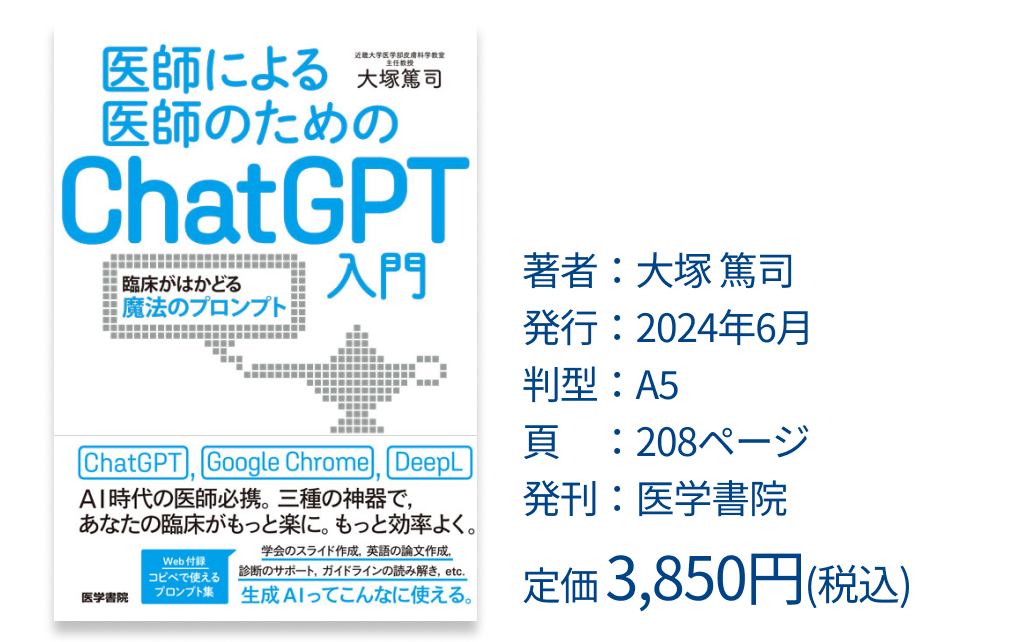
医師による医師のためのChatGPT入門
臨床がはかどる魔法のプロンプト
ChatGPTに苦手意識のある医師に向け、 基本的な使い方から日常業務での活用法までを、 会話形式で丁寧に解説。
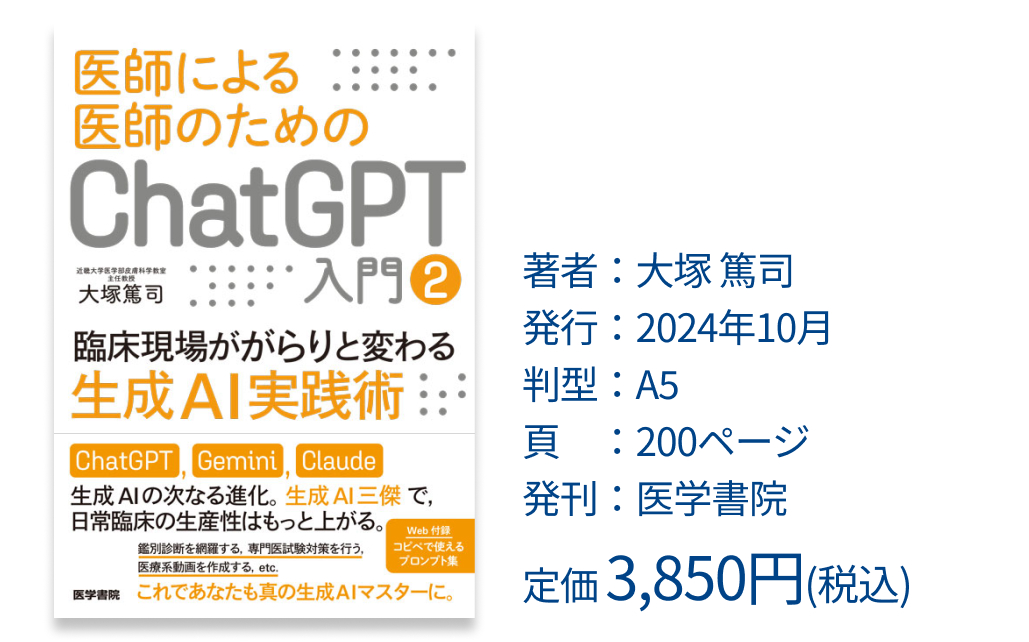
医師による医師のためのChatGPT入門 2
臨床現場ががらりと変わる生成AI実践術
GeminiやClaudeなどの登場で広がる最新の活用法を網羅。 前作に続き、 実例とともに理解が深まる構成。
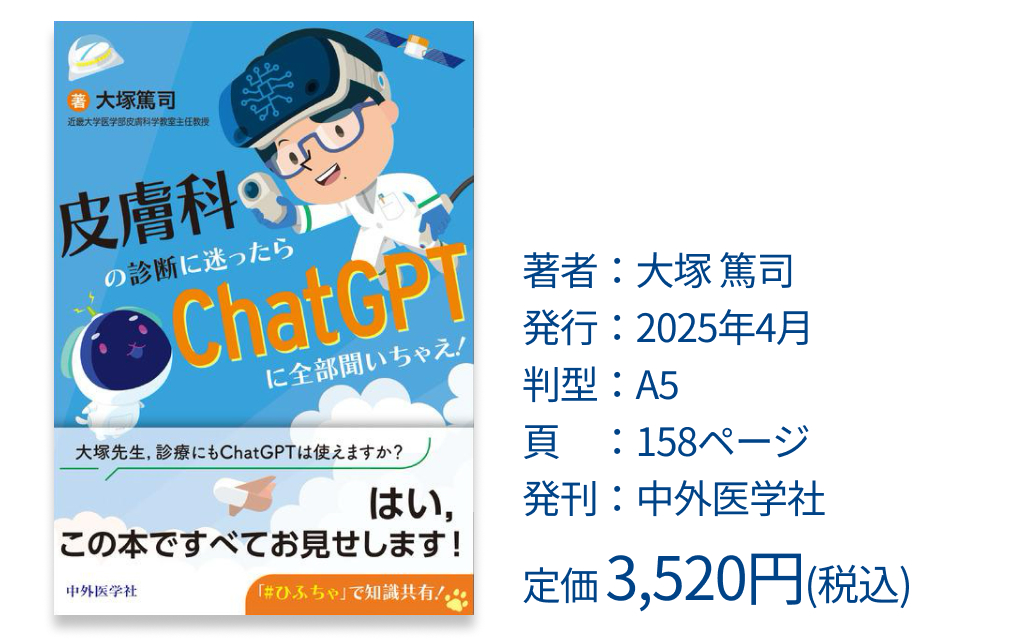
皮膚科の診断に迷ったらChatGPTに全部聞いちゃえ!
紅斑・丘疹・鱗屑など皮疹の"見え方"を言語化し、 ChatGPTで鑑別リストを引き出す手順を症例対話で丁寧に指南。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。