寄稿ライター
10ヶ月前
酔っ払いはうんざり…酩酊患者は放っておいていいの?
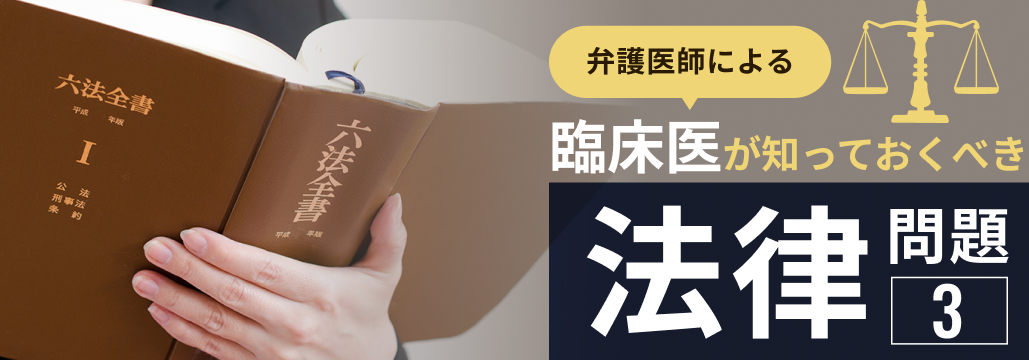
医療訴訟が珍しくなくなった今、 医師は法律と無関係ではいられない。 連載 「臨床医が知っておくべき法律問題」 3回目のテーマは 「酔っ払いはうんざり…酩酊患者は放っておいていいの?」
飲酒患者の8割は救急車で受診
通常の外来受診で、 酒が入って受診する患者はさすがにレアだろうが、 救急外来では酔っ払いは珍しくない。 急性アルコール中毒の疑いのある患者はもとより、 飲酒後脳出血を生じたと思われる意識障害、 飲酒後の転倒などによる外傷などさまざまだろう。
少々古い文献になるが、 2012年発行の 「日本アルコール・薬物医学会雑誌」 によると、 飲酒患者は全受診の 1.2%に過ぎないが、 そのうち77.6%が救急搬送で受診しており、 救急搬送全体の5%近くを占める。 中等度以上の患者が半数に及び、 受診時に暴力的な状態であったり、 診療や治療を拒否したりするケースも8%ほどあるという¹⁾。

写真はイメージです
飲酒患者は問診も身体所見もとりにくいし、 採血なども非協力的なことがあるため、 できるならば断りたいというのが医師の本音であろう。 やむを得ない病気ではなく、 自分の意思で飲酒しているのだからという目線もある。 だからと言って、 自業自得を理由に酔っぱらいを追い返せるのだろうか。
飲酒患者を救急搬送せず、 裁判沙汰に
2019年の神戸地裁判決²⁾ を見てみよう。 50代患者が自宅で倒れているとの通報を受け、 救急隊が 「上下肢の脱力」 または 「突然の歩行障害」 が窺われることを認識し、 脳卒中の可能性もある状況で現場に到着したケースである。
救急隊は近くに空の酒パックがあること▽顔を近づけたときに口元からアルコール臭がしたこと――などを根拠に、 酒の影響で意識がぼんやりしていると考え、 名前の確認や短い簡質問に対する回答の様子から 「異常なし」 と判断した。

写真はイメージです
ただ、 結局この患者は脳梗塞で後遺障害が残った。 救急隊の対応が不適切だったとして、 約3800万円の損害賠償を求めて訴えられた。
救急隊は顔の歪みを確認するために歯を見せてもらったり、 笑ってもらったりしていなかった。 構音障害を確認するために、 ある程度長く話をさせることもしておらず、 「過失がある」 と認定され、 慰謝料100万円を支払うよう地裁に命じられた。
急性硬膜下血腫の見落としも
医師の場合、 さらに酩酊の鑑別義務は重い。 1990年にあった神戸地裁明石支部の判決³⁾ を紹介しよう。 60歳男性が晩酌後、 自宅の階段から転落し、 石の床に頭部を打ち、 仰向けのまま動かなくなった事案である。
救急搬送時、 当直医は患者の呼気から酩酊状態にあると判断し、 問診は詳しくせず、 全身状態や頭部触診、 脈拍、 瞳孔を数分間診察。 後頭部に顕著な外傷を認めない上、 患者が診察中終始発語していることなどから、 意識状態は清明であると見て、 「脳挫傷の可能性はない」 と結論付けた。

病院外で待機中の技師を呼び出してレントゲン検査をする必要性や、 入院による経過観察の必要性もないとして、 「大丈夫。 寝させておいたら治る」 と家族に伝えた。 ただ、 結局は急性硬膜下血腫で死亡している。
裁判所は 「脳損傷による意識障害を酩酊状態と誤認することのないように、 本人や家族から飲酒量や摂取した酒類などの事情を十分に問診しておく必要があった」 として損害賠償の支払いを命じている。
単純酩酊は除外診断で
つまり、 酩酊により怪我をして医師や救急隊の判断を難しくしたことは、 損害賠償の減額事由にはならないようである。
単純酩酊は、 やはり除外診断と心得ておいた方が無難であろう。
プロフィール
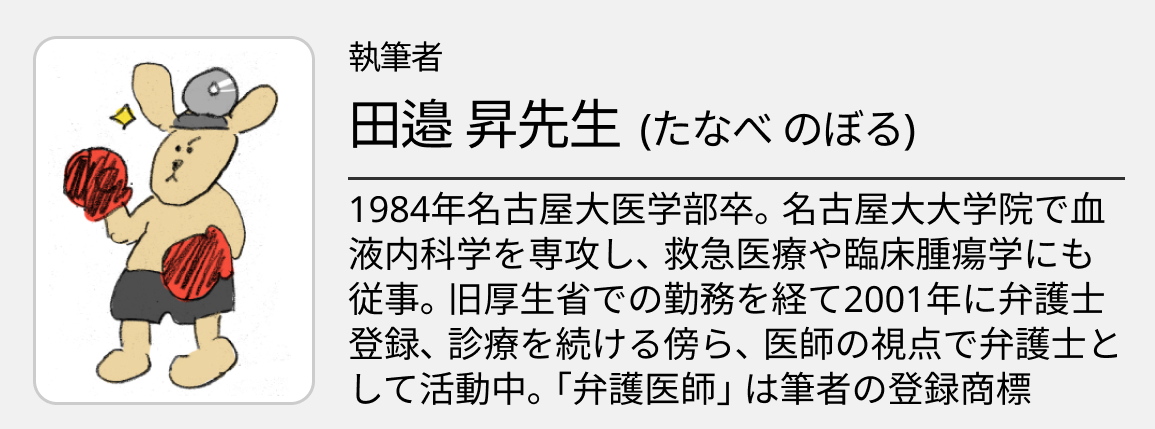
出典
¹⁾ 柴山美紀根ほか (2012) 「ER型救命救急センターを受診した『問題飲酒者』の実態と対策」 ,『日本アルコール・薬物医学会雑誌』, 47 (6), 331-340
²⁾ 神戸地裁令和元年12月13日判決
³⁾ 神戸地裁明石支部令和2年10月8日判決
HOKUTO関連コンテンツ
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。