亀田総合病院
2ヶ月前
【呼吸器疾患】2025年2月の注目論文3選 (中島啓先生)

呼吸器感染症領域で注目度の高い論文を毎月3つ紹介してきた本シリーズが、 2025年2月より『呼吸器疾患』全体を対象にした論文紹介へとリニューアルされます!
気管支拡張症に対するマクロライド維持療法の心血管リスクは?
Eur Respir J. 2024 Dec 12:2401574.
背景 : MMTの心血管リスクは不明
マクロライド維持療法 (MMT) は気管支拡張症患者の増悪を抑制します。 増悪が主要な心血管イベント (MACE) のリスク因子である一方で、 MMTがMACEに及ぼす影響は不明でした。 また、 マクロライド自体の心血管リスクも指摘されています。 本研究は、 香港の大規模データを用いてMMTとMACEの関連を調査しました。
研究デザイン : 大規模コホートでMACEリスクを評価
- 対象: 2001~18年に診断された気管支拡張症患者2万2,895例
- MMT投与群と非投与群に分類し、 1:2傾向スコアマッチングで交絡因子を調整
- 主要評価項目 : MACE (心血管死、 心筋梗塞、 脳卒中の複合)
- 安全性評価項目 : 心室性不整脈、 突然心臓死
- 統計解析 : Cox比例ハザード回帰
結果 : MMTでMACEリスクが32%低下
- MMT群1,123例と非MMT群2,014例を解析
- MMTはMACEのリスクを有意に低下
- 1,000人年あたり16.4 vs 24.1イベント
- HR 0.68 [95%CI: 0.52-0.90])
- 心室性不整脈や突然心臓死のリスク上昇は認めず
- 1000人年あたり7.2 vs 7.7イベント
- HR 0.93 [95%CI: 0.60-1.44])
💬 My Opinion
近年、 呼吸器感染症と心血管疾患の関連が明らかになり、 気管支拡張症患者も心血管リスクが高いことが知られています。 本研究では、 香港の大規模コホートを用いて、 MMTがMACEを32%低下させ、 不整脈リスクの上昇もなく安全性が確認されました。
間質性肺疾患急性増悪にステロイドは有効か?
Thorax. 2025 Feb 17;80(3):140-149.
背景 : ILD急性増悪の死亡率は高く、 治療法が課題
間質性肺疾患 (ILD) の急性増悪は死亡率が高く、 治療戦略の確立が急務とされています。 ステロイド療法は広く用いられていますが、 最適な投与方法や有効性は未確立です。 本研究では、 系統的レビュー (SR) を実施し、 ステロイドの治療効果を評価しました。
研究デザイン : 関連論文をSRで網羅
PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (SRMAの報告ガイドライン) に準拠。 研究間の違いを考慮し、 メタ解析は実施せず。
- 1万2,454件の論文を特定、 447件を全文レビュー
- 対象: ILD急性増悪の治療に対する高用量ステロイドと低用量または非ステロイド療法を比較した9研究、 1万8,509例
- 主要評価項目 : 院内死亡率、 長期死亡率、 急性増悪の再発率
結果 : 非IPFでは有効、 IPFでは一定せず
非IPF性ILD (特発性肺線維症以外のILD)
- 高用量ステロイド療法 (>1.0mg/kgプレドニゾロン)
- 生存率が改善 (調整ハザード比 [HR] 0.22 [95% CI: 0.10-0.48]、 p<0.001
- 90日死亡率が低下
- 早期漸減 (2週間以内に10%以上減量)
- 院内死亡率が低下 (調整HR 0.37 [95% CI: 0.14-0.99])
- 30日間の累積投与量が多い (5,185±2,414 mg/月 vs. 3,133±1,990 mg/月)
- 再発率が低下 (調整HR 0.61 [95% CI: 0.41-0.90]、 p=0.02)
IPF性ILD (特発性肺線維症のILD)
- 高用量ステロイド療法の効果は不明確
- 一部の研究で死亡リスク増加 (オッズ比 1.08 [95% CI: 1.04-1.11]、 p<0.001)
💬 My Opinion
本SRでは、 日本からの研究4件を含む1万8,509例のデータが評価されました。 非IPF性ILDでは高用量ステロイド療法が生存率の改善に寄与する可能性が示されましたが、 IPFでは有効性が一定せず、 むしろ死亡リスクの増加が指摘されています。 疾患ごとの最適なステロイド投与プロトコルを確立するため、 さらなるランダム化比較試験による検証が必要です。
血糖降下薬でCOPD増悪は減るか?
JAMA Intern Med. 2025 Feb 10:e247811.
背景 : 血糖降下薬のCOPDへの影響は?
SGLT-2阻害薬、 GLP-1受容体作動薬、 DPP-4阻害薬はCOPD患者に有益な可能性がありますが、 COPD増悪との関連性は未解明でした。 本研究では、 Target trial emulation*を用いて、 各薬剤のCOPD増悪リスクを比較しました。
*観察研究データを用いて 「もしRCTを実施したら得られるであろう結果」 を再現する解析手法。 RCTのデザイン原則 (介入群・対照群の明確化、 試験開始時点の統一、 交絡因子の調整など) を適用し、 因果推論の精度を向上させる。
デザイン : RCTを模倣したデータベース解析
- 40歳以上の2型糖尿病かつ活動性COPDの患者を追跡し (中央値145日)、 中等度または重度のCOPD増悪*の初回発生を調査
*外来/入院の、 COPDに対する経口ステロイド処方と定義
- 傾向スコアマッチングコホート研究
- SGLT-2阻害薬 vs. DPP-4阻害薬
(各2万7,991例)
- GLP-1受容体作動薬 vs. DPP-4阻害薬
(各3万2,107例)
- SGLT-2阻害薬 vs. GLP-1受容体作動薬
(各3万6,218例)
- データソース : 米国の3つの保険請求データベースを利用
Optum, IBM MarketScan, Medicare
結果 : SGLT-2阻害薬とGLP-1受容体作動薬がCOPD増悪リスクを低減
- SGLT-2阻害薬 vs DPP-4阻害薬
- COPD増悪リスクが19%低下 (HR 0.81 [95%CI: 0.76-0.86])
- 発生率は100人年あたり2.20件減少 (95%CI: 2.83件減少-1.58件減少)
- GLP-1受容体作動薬 vs DPP-4阻害薬
- COPD増悪リスクが14%低下 (HR 0.86 [95%CI: 0.81-0.91])
- 発生率は100人年あたり1.60件減少 (95%CI: 2.18件減少-1.02件減少)
- SGLT-2阻害薬 vs GLP-1受容体作動薬
- 有意差なし (HR 0.94 [95%CI: 0.89-1.00])
- 発生率は100人年あたり0.55件減少 (95%CI: -1.09件減少-0.01件減少)
💬 My Opinion
本研究ではTarget trial emulationを用いることで観察データからの因果推論の精度を高め、 SGLT-2阻害薬とGLP-1受容体作動薬がCOPD合併2型糖尿病患者の増悪リスクを低下させる可能性を示しました。 近年、 これらの薬剤が肺炎や敗血症のリスクも減らすと報告されており、 呼吸器感染症への影響が注目されています。 本研究結果は、 血糖降下薬の選択にCOPD合併の有無を考慮する重要性を改めて示唆しています。
HOKUTO関連コンテンツ
HOKUTO編集部 : 医療の最前線から
【BMJ】COPDの3剤配合吸入療法、 最も有効で安全なのは?
HOKUTO編集部 : 海外ジャーナルクラブ
HOKUTO編集部;GOLD2025年改定版
HOKUTO編集部 : 人気コンテンツ紹介
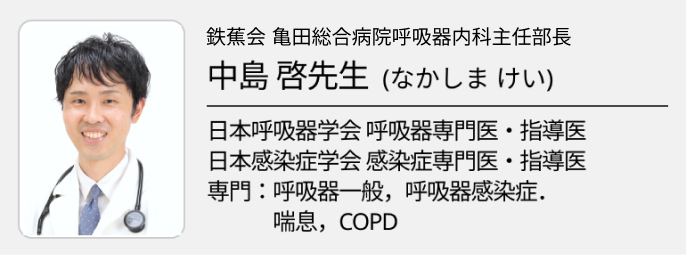
呼吸器内科全般を深く勉強したい先生は,全国のエキスパートの知と技を結集した新刊 「呼吸器内科診療の掟」 (中島啓 編著) をぜひ診療の参考にされて下さい!
呼吸器内科の基本をしっかり学びたい方は 「レジデントのための呼吸器診療最適解」 (医学書院) でぜひ勉強されて下さい!
一言 : 当科では教育および人材交流のために、 日本全国から後期研修医・スタッフ (呼吸器専門医取得後の医師) を募集しています。 ぜひ一度見学に来て下さい。
連絡先 : 主任部長 中島啓
メール : kei.7.nakashima@gmail.com
中島啓 X/Twitter : https://twitter.com/keinakashima1
亀田総合病院呼吸器内科 Instagram : https://www.instagram.com/kameda.pulmonary.m/
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。