HOKUTO編集部
15日前
【解説】大腸癌に対するロボット支援手術の現在
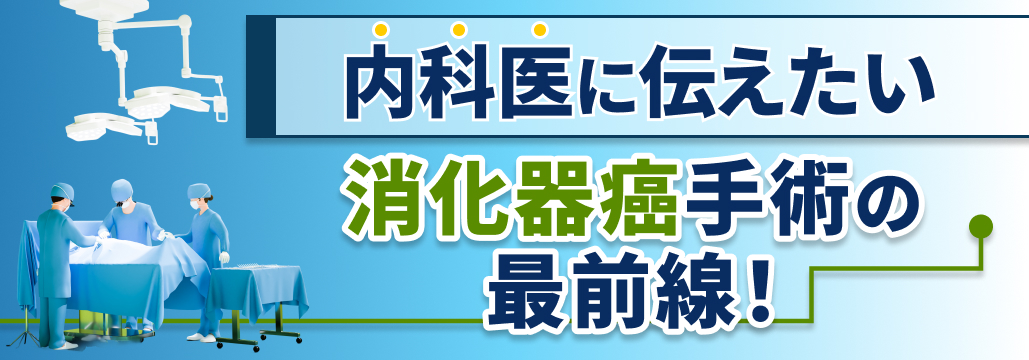
外科医のみならず、 がん薬物療法を担う内科医にとっても、 外科治療の最前線を知ることは、 集学的治療の観点から重要である。 本連載では、 消化器癌における手術治療の最新知見を紹介する。 初回となる本稿では、 大腸癌に対するロボット支援手術の適応とエビデンスを概観し、 腹腔鏡手術との比較を交えながら、 その意義を明らかにする。
解説医師
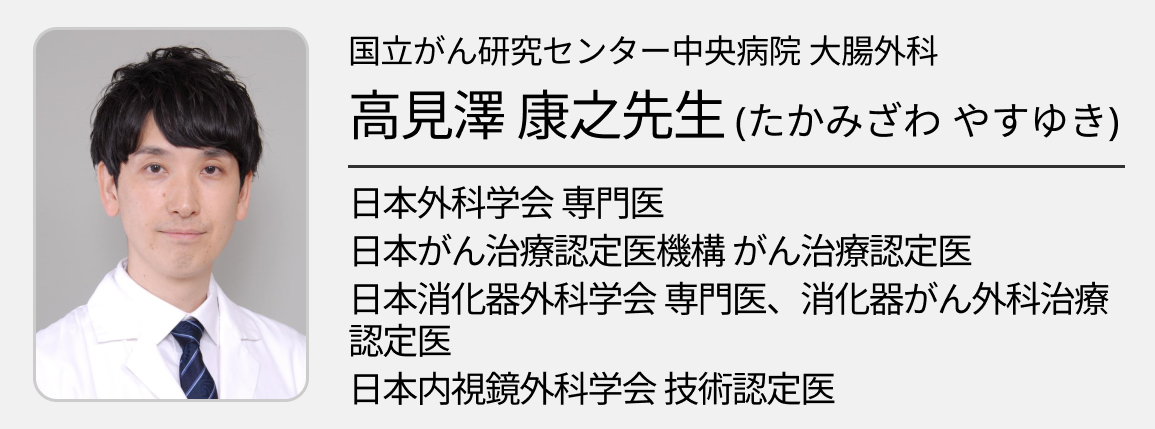
診療ガイドラインにおけるロボット手術の位置付け
大腸癌に対するロボット支援手術は、 2018年4月に直腸癌、 2022年4月に結腸癌を対象として保険適用となった。 『大腸癌治療ガイドライン2024』では以下のように記載されており、 ロボット支援手術は標準的な治療選択肢の一つと位置付けられている。
ロボット支援手術と腹腔鏡手術の長期成績
直腸癌に対するロボット支援手術の研究は近年増加し、 長期成績に関するエビデンスも蓄積されつつある。 多くのRCTおよび後方視的研究において、 ロボット支援手術と腹腔鏡手術の長期成績 (再発率、 生存率) に有意差はないとされており¹⁾²⁾、 「長期成績においては両者は同等である」 との理解が一般的である。
一方、 術前化学放射線療法 (CRT) を施行した症例では、 ロボット支援手術群で肺転移の発生が少なく³⁾、 また、 治療反応が乏しいypT3/4症例においても遠隔転移再発が少なかった⁴⁾とする報告もある。 さらに、 長期成績を主要評価項目としたRCTであるREAL試験⁵⁾では、 3年局所再発率および3年無病生存率においてロボット支援手術群が腹腔鏡群よりも良好な結果を示した。 これらの結果から、 直腸癌の一部サブグループにおいては、 ロボット支援手術がより良好な長期成績を示す可能性があり、 今後のさらなる検証が期待される。
結腸癌における長期成績に関する報告は依然として限られており、 現時点では腹腔鏡手術と同等と考えられている⁶⁾⁷⁾。 今後の知見の蓄積が望まれる分野である。
ロボット支援手術の短期成績と合併症リスクの軽減
ロボット支援手術の特長として、 術後合併症の軽減が挙げられる。 直腸癌においては、 腹腔鏡手術と比較して、 性機能障害、 排尿障害、 腸閉塞などの合併症の頻度が少ないこと²⁾⁸⁾、 開腹移行率が低いこと、 入院期間が短いことが報告されている⁹⁾。
結腸癌に関する知見は限られているが、 海外の大規模データベースを用いた後方視的研究では、 ロボット支援手術が腹腔鏡手術に比べてリンパ節郭清数が多く、 輸血量が少なく、 術後90日以内の化学療法導入率が高いとされる¹⁰⁾。 また、 縫合不全率や開腹移行率の低下も、 メタ解析により示されている¹¹⁾。
ロボット支援手術では、 多関節アームによる繊細かつ安定した操作が可能であり、 これが合併症の軽減に寄与していると考えられる。 ただし、 手術時間の延長や高コストといった課題も存在する。
My Opinion
ロボット支援手術は短期成績が良好であり、 ガイドラインでも推奨されているため、 導入可能な施設では積極的に選択すべき治療法である。 一方で、 長期成績において明確な優位性が示されているわけではなく、 従来の腹腔鏡手術や開腹手術を否定するものではない。 特に直腸癌における排尿障害や性機能障害は、 自律神経を温存する剥離層に沿って剥離操作が行われているかどうかに大きく依存する。 従来の術式で正確な手術操作が可能であれば、 これまで通りの方法で行うことも妥当と考えられる。
もっとも、 腹腔鏡手術からロボット支援手術に切り替えたからといって、 手術の質が即時に向上するわけではない。 基本的な解剖理解や剥離層の認識といった本質的な要素は術式にかかわらず共通しており、 「ロボットであれば突然うまくできるようになる」 といった劇的な変化は期待すべきではない。 ただし、 ロボット支援手術に習熟するにつれ、 その操作性や視野の安定性が腹腔鏡手術と比較して明らかに優れていることが実感できる。 特に骨盤腔が狭い直腸癌症例ではその利点が顕著であり、 実臨床においてはロボット支援手術が第一選択となっているケースも多い。 一度ロボット手術に慣れると腹腔鏡には戻りにくくなるという点は、 ロボット支援手術の 「魅力」 であると同時に、 「デメリット」 と捉えられる側面もある。
出典
- Ann Surg. 2015;261(1):129-37.
- Surg Endosc. 2025;39(1):184-193.
- Int J Colorectal Dis. 2022;37(9):2085-2098.
- Dis Colon Rectum. 2021;64(7):812-821.
- JAMA. 2025:e258123[オンライン版].
- Ann Surg Oncol. 2018;25(13):3906-3912.
- J Clin Med. 2022;11(9):2387.
- Dis Colon Rectum. 2022;65(10):1191-1204.
- Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 ;7(11):991-1004.
- J Robot Surg. 2024;18(1):341.
- Surg Endosc. 2022;36(1):32-46.
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。