寄稿ライター
2ヶ月前
シーリングって意味あるの?

こんにちは、 Dr.Genjohです。 シリーズ 「医師減給時代」 最終回となる第5回のテーマは 「シーリングって意味あるの?」 です。
シーリングって何?
前回 「地域枠って意味あるの?」 話した通り、 医師の偏在は地域間のみならず診療科間でも発生しています。 それを是正するためにシーリングシステムが設定されました。
各都道府県・各診療科において 「2018年医師数」 が 「2024年の必要医師数」 以上である場合、 「足元の医師充足率が高い=医師が十分に足りている」 と判定されます。
医師が足りていると判定された診療科・都道府県の組み合わせにおいて、 初期研修後の専攻医の進路先として 「人数上限数=シーリング」 が設定され、 内定枠の争奪戦になります。
大人気の東京

【表1】厚労省の資料より*¹⁾
【表1】で大人気の東京都を見てみましょう。 シーリングの対象科において、 泌尿器科を除くすべての科でシーリングが発生しています。 希望者の多い東京で、 人気のある診療科に一極集中しないように強い制限がかかっていることが読み取れます。
シーリングは3パターン

【表2】厚労省の資料より*¹⁾
シーリングが発生した場合、 その内定枠は①通常募集プログラム②連携プログラム③特別地域連携プログラム――の3種類に分類されます【表2】。
通常募集プログラム
希望する都道府県・診療科で研修する期間を最も長く取ることができるでしょう。 ただし、 研修期間の20%以上は医師少数区域での研修を要求されることが一般的です。 (連携プログラム枠確保の前提となります)
連携プログラム
シーリング対象外の都道府県へ出向し、 現地での研修が 「1年6か月以上」 も必要となります。
特別地域連携プログラム
出向先が特に医師が足りていない施設に限定されますが、 研修期間は 「1年以上」 になります。
シーリングが発生するような人気の都道府県・人気の診療科を選ぶ代わりに、 医師が少ない地域に一定期間応援しにいく、 という条件がつくわけですね。
特別地域連携プログラムのupdate

【表3】厚労省の資料より*¹⁾
特別地域連携プログラムに関しては、 来年度から【表3】のような派遣パターンが加わることになりました。
今年度は特別地域連携枠の派遣先として、 医師少数区域にある施設(すごく田舎)か、 時間外労働が1860時間オーバーの施設(ブラック病院)が設定されていました。 都市部病院からの派遣先としては落差が大きすぎて人気がでなかったのかもしれません。
来年度は、 医師少数都道府県ではあるが、 その中でも医師多数区域にある施設、 例えば県庁所在地にある〇〇県立病院などの施設が派遣先として設定出来るようになりました。
とばっちりを受ける先生も…

写真はイメージです
ただし、 それだけでは医師少数区域の医師数は増えません。 特別地域連携枠で都会から派遣されてきた先生のかわりに、 元来〇〇県立病院で働いていた地域の先生が医師少数区域にところてん式に押し出されることで、 医師少数区域の医師数が増員されることになります。 押し出された先生にとってはとばっちりを受ける形になり、 悲劇ですが…。
シーリングの限界
ただ、 シーリングシステムも医師偏在問題を根幹から解決するには至っていません。 端的にいえば、 医師少数地域への応援も、 医師1人当たり1年~1年半程度の一時しのぎに過ぎません。
交代人員を受け継ぐことで疑似的に医師少数地域の医師数を増やすことは出来るものの、 その医師が最終的にその地域に根付くわけではありません。 研修期間が終われば人気のある地域に帰ってしまいます。
医師少数区域で専攻医を修了して専門医になった医師ですら、 その地域に根付くとは限りません。 地方で実力を付けて都市に凱旋する専門医を、 地方に慰留させる公的な外力は現在のところ存在しないのです。

【表4】厚労省の資料より*¹⁾

【表5】厚労省の資料より*¹⁾
【表4】と【表5】をみてください。 各都道府県における診療科別の専攻医採用数です。 首都圏をはじめ、 都市に隣接する自治体の採用数は、 それ以外の自治体と比較すると相対的に多くなっています。
専攻医側としては当然の反応ですね。
「東京で内定取れなかった…そうだ、 東北や四国に行こう!」
とはなかなかなりません。
「東京で内定取れなかった…東京にも近い神奈川、 千葉、 埼玉に行くか…」
が自然でしょう。
都市周辺にドーナツ状に流出しただけ

シーリングで医師の都市一極集中に制限をかけることに成功はしたものの、 結果として一極集中都市の周辺にドーナツ状に流出しただけ。 本当の医師少数区域への均等な分布は達成されておらず、 医師の偏在が解決したとは言えません。
医師少数区域で専攻医研修を行うことに大きなインセンティブを付与出来れば状況は変わるかもしれませんが、 財源の問題もあり実際には難しいでしょう。
今後シーリングの基準の厳格化・対象の拡大の結果として、 都市の周辺自治体にも圧がかかるようになり、 さらに外側の医師少数区域へ専攻医が流出するように設定される可能性もあります。
医師減給時代に立ち向かえ
本シリーズでは、 今後予測される医師減給時代に向けて現状を整理してきました。
収入が保険診療に依存し固定されている状況においては取りうる対策に限界があるものの、 需要と供給が重要であることは間違いありません。
先生方が今後の在り方を見つめなおすきっかけとなるようであれば幸いです。
筆者プロフィール
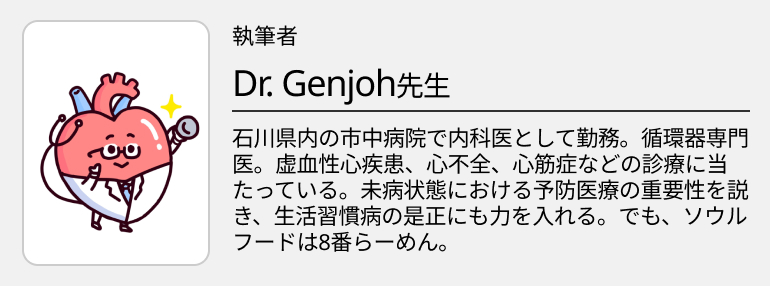
Xアカウント : @DrGenjoh
出典
*¹⁾厚生労働省 : 令和6年度第1回 医道審議会医師分科会 医師専門研修部会 「令和6年度の専攻医採用と令和7年度の専攻医募集について」 (2024/7/19)
HOKUTO関連コンテンツ
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。