寄稿ライター
29日前
「リピーター医師」 問題の根底にあるもの

医療訴訟が珍しくなくなった今、 医師は法律と無関係ではいられない。 連載 「臨床医が知っておくべき法律問題」 の第21回では、 報道特集でもたびたび取り上げられる 「リピーター医師」 問題について考察する。
医療事故を繰り返す医師とは?
「リピーター医師」 とは、 医療事故を繰り返す医師の通称である。 赤穂市民病院の脳神経外科医や群馬大学医学部附属病院の外科医による手術死亡例など、 特定の医師に不適切な結果が集中していると見なされる事例が報道のきっかけとなっている。 厚労省が問題視したケースもある。
ただ、 その背景や実態は、 単なる 「過失の繰り返し」 で一括りにはできない。
タイプ① : 確信犯型
重大な事故を経験し、 悪しき結果からクレームや民事訴訟 (多くは損害賠償請求) になったとしても、 自身の診療方針を改めず、 同じ事故を繰り返す──こうしたタイプの医師は、 過失というよりも“確信犯”的である場合がある。

写真はイメージです
つまり、 新しい知見やエビデンスを無視し、 自身の経験則に固執するわけだ。 2003年から日本産婦人科医会が妊産婦死亡についての報告制度を開始した背景にも、 このような医師像があった。 専門医らによるアドバイス的報告書を医療機関にだけリターンして学習してもらうのだが、 その後、 「産科医療補償制度」 の導入に結びつき、 産婦人科でのリピーター医師はあまり聞かなくなった。
ただ、 一部では今も 「自己流」 を貫く医師が存在する。 たとえば、 HPVワクチンや新型コロナワクチンに反対する医師が、 科学的根拠を無視して接種を推奨しないといった行為も、 「不作為によるリピーター」 といえるのかもしれない。
タイプ② : 成績不良型
手術件数が多く、 そのうちいくつかで予後不良事例が発生した結果、 「事故を繰り返している」 と見なされるパターンもある。 群馬大学病院では、 7年間に30例の術後死亡が報道され、 大きな問題となった。

写真はイメージです
しかし、 その全容を精査すると、 成功した事例もあり、 「してはいけない手術」 をしたわけではなさそうだ。 「地域で実施する医師が少ない中でのやむを得ない手術」 であったのならば許容されるべきであろう。
この件では、 原告側が一部メディアと手を組んで大々的に報道することで話題となり、 これに押された大学側も懲戒処分などをしている。 メディアが一部の事故例に注目し、 過去の例を掘り起こすことで問題視する構図は、 いわゆる 「文春砲」 と呼ばれるスキャンダル報道と類似している。
本来はチーム医療であるにもかかわらず、 個人をスケープゴートとした対応が取られた場合、 その医師が本当に 「リピーター」 かどうかは慎重に検討すべきである。
タイプ③ : コミュニケーション困難型

写真はイメージです
医療技術に大きな問題がなくとも、 患者や同僚とのコミュニケーションが円滑でない医師が、 事故の当事者として頻繁に名を連ねるケースもある。
赤穂市民病院の例では、 患者家族が漫画で批判を発信し注目を集めたが、 実際の事故調査では過失があったのはごく一部だったとされる。 こうしたケースでは、 当該医師の性格や振る舞いが誤解や対立を生み、 結果として 「問題医師」 として扱われてしまうこともある。
再発防止の手段はあるのか?

写真はイメージです
では、 「リピーター医師」 問題を解決するにはどうすればいいか。 医師個人の責任を問うだけでは不十分であるのはもちろん、 制度としての再発防止策も見直しが必要だ。
例えば、 医療事故調査制度の運用には課題がある。 この精度は本来、 事故の再発防止に向けた課題解決に軸足を置くべきだ。 それににもかかわらず、 現在もなお一部の医療機関では、 事故調報告書が訴訟の証拠として用いられている。 これは、 現場に萎縮効果をもたらしている。 結果が悪くても、 過誤とは思わず繰り返す場合もあり、 学習型の医療事故調査制度 (医療法6条の10) は、 過失は報告要件としていない。
懲戒?免許更新? その先にあるリスク

写真はイメージです
リピーター医師を減らすため、 医師免許の更新制を導入すべきとの声もある。 しかし、 それが形骸化すれば意味はなく、 逆に地域医療を支える医師まで失うリスクもある。 高齢ドライバーの運転免許制度と同様、 現実的な落としどころが必要だ。
さらに、 「自己流」 に傾倒する医師ほど、 患者からの支持を得やすいという側面もある。 そうした医師を制度だけで排除しようとすれば、 かえって医療不信を招くことにもなりかねない。
求められるのは“責任追及なき”学びの場

写真はイメージです
やはり、 現場での自由闊達なケースカンファレンスこそが、 もっとも有効な再発防止策となるだろう。 死亡例や重大事故に限らず、 日常的なミスや気づきを共有し学ぶ文化が必要だ。
そのためには、 「誰かを責めるため」 の調査ではなく、 「学ぶための検討記録」 であることを徹底すること。 裁判所による医療事故調査報告書の証拠採用を制限し、 事故調報告書の証拠保全申立てについても、 今後は全面的に禁止にするような運用の見直しが求められる。
プロフィール
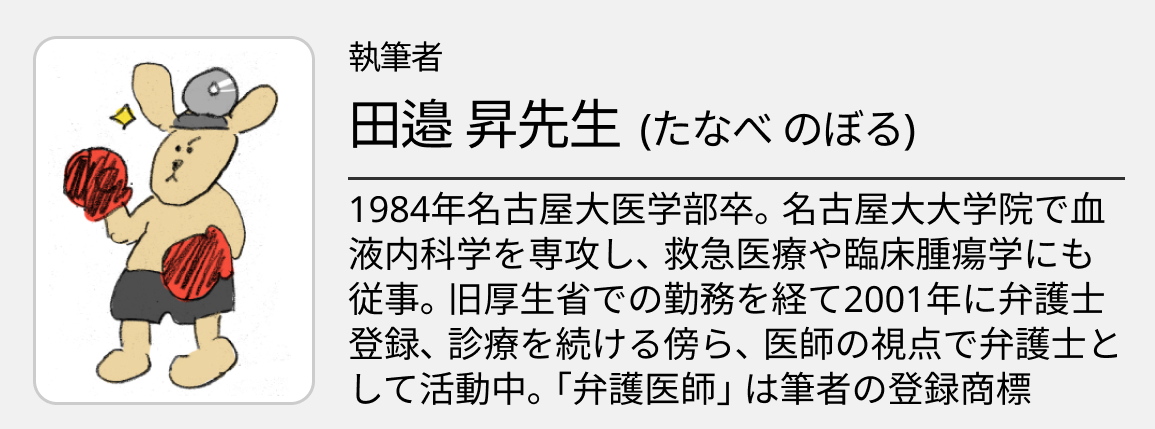
HOKUTO関連コンテンツ
- 薬物中毒の患者が受診した際、 通報すると守秘義務に違反する?
- 院内で発生した居座り患者、 どう対処する?
- 酔っ払いはうんざり…酩酊患者は放っておいていいの?
- 韓国・研修医のストライキは日本でも起こりうるのか
- 専門外領域の診療拒否は応召義務違反になるの?
- 患者の自主退院と誓約書、 医療者の責任とリスクは?
- 輸血拒否の患者、どうする?
- 認知症患者の同意をどう取るか
- 医療事故調査をめぐる問題
- 母体保護法と配偶者の同意
- 訴訟の多い診療科は?医療裁判の統計
- 説明義務違反と損害賠償
- 偶発腫を見落としたら責任を問われるのか
- 中居騒動の 「秘密保持条項」、 医療現場での効力は?
- 医師が知っておくべき 「解剖」 問題
- 【解説】自治医大訴訟を巡る法的論点
- 令和で激減?医療訴訟の逆転判決
- 重過失ってなんだ?
- ペイハラ対応の司法判断
- LINEでの説明は有効か

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。