インタビュー
7ヶ月前
【JCHO横浜中央病院】少人数制で、 地域生活に寄り添う医療を学ぶ

横浜の中心地に立地し、 交通の便が非常に良いのが特徴
JCHO横浜中央病院 (神奈川県) は、 横浜中華街にほど近い都市部にありながら、 地域に根ざした医療を実践する二次救急病院です。 初期臨床研修の定員は1学年4名。 きめ細かな指導と手厚いサポートを受けながら、 幅広い患者背景に向き合う“都市型地域医療”を経験できるといいます。
※インタビューは2025/5/19に実施しました。
今回はプログラム責任者の大岩 功治先生、 プログラム副責任者の藤川 博敏先生に、 研修の特徴や少人数制の研修のメリットについて話を聞きました。
研修プログラムの特徴
多様な地域住民に向き合う実践的な地域医療
――研修プログラムの特徴は。
大岩先生
「地域医療と地域救急に重点を置いた研修を提供しています。 当院は横浜市中区で唯一の二次救急病院であり、 研修医は研修に必須なコモンディジーズを現場で経験しながら学ぶことができます」
藤川先生
「山下公園や外人墓地など、 もともと海外との交流が多い街に立地し、 横浜中華街に隣接しているため多国籍の患者さんが来院されます。 また、 日雇労働者が多い『寄せ場』と呼ばれる地域も近くにあり、 さまざまな背景を持つ方々を診る機会があります」
大岩先生
「医療だけでなく患者さんの生活そのものに目を向けながら診療できるのが、 当院の研修の大きな特徴です」

ICLS研修中の研修医と看護師。 研修に熱が入る
少人数制のメリット
顔と名前が自然に共有される環境
――少人数制のメリットは。
大岩先生
「初期研修医の定員が4名と少人数であるため、 指導医の中で“研修医の実習状況や課題”という情報が自然と共有されています」
藤川先生
「1診療科に1人の研修医を原則にしているので、 症例を取り合うことがありません。 やる気次第で手技をどんどん任せてもらえるのは小規模病院ならでは、 です」
大岩先生
「少人数だからこそ、 誰一人として取り残さないという意識が病院全体に根付いていますし、 研修医同士も自然とそういう雰囲気をつくってくれています」

血管治療を指導医とともに行う研修医。 マンツーマンで指導する
研修の雰囲気
少人数だからこそ築ける関係性
――研修医同士の関係は。
藤川先生
「非常に仲が良い印象です。 毎年4月には、 2年目の研修医が1年目の研修医の診療科と重なるようローテーションを組むことで、 2年目がチューター役となり最初の研修期間をカバーするようにしています。 カルテ記載や諸検査のオーダーの仕方など、 入職時に戸惑うような事案も気軽に相談しやすいようにしています」
大岩先生
「1年目と2年目を合わせて8名です。 顔が見える規模感だからこそ、 研修医一人ひとりが孤立しにくく、 安心して研修に取り組めます」

研修医室での仲間と団らん・ひとときの休憩風景
医学生へのメッセージ
地域と向き合う医療の原点をここで
――医学生へのメッセージをお願いします。
藤川先生
「救急から地域包括ケアまで、 大規模病院では得がたい地域特性を重視した経験ができます。 横浜で地域医療や救急医療に向き合いたい人には非常にマッチすると思います」
大岩先生
「多様性を重視し、 多国籍の方や生活に困難を抱える方を含め幅広い患者さんに向き合います。 初期研修の時期に“地域生活に寄り添う医療”を経験することは大きな意味があります」
「主幹病院としての専攻医プログラムはありませんが、 連携大学病院の地域プログラムに入り、 スタッフとなる先生もいます。 外観は年季が入っていますが院内では最新の医療を行っていますので、 ぜひ一度見学に来てください」
先生方のプロフィール
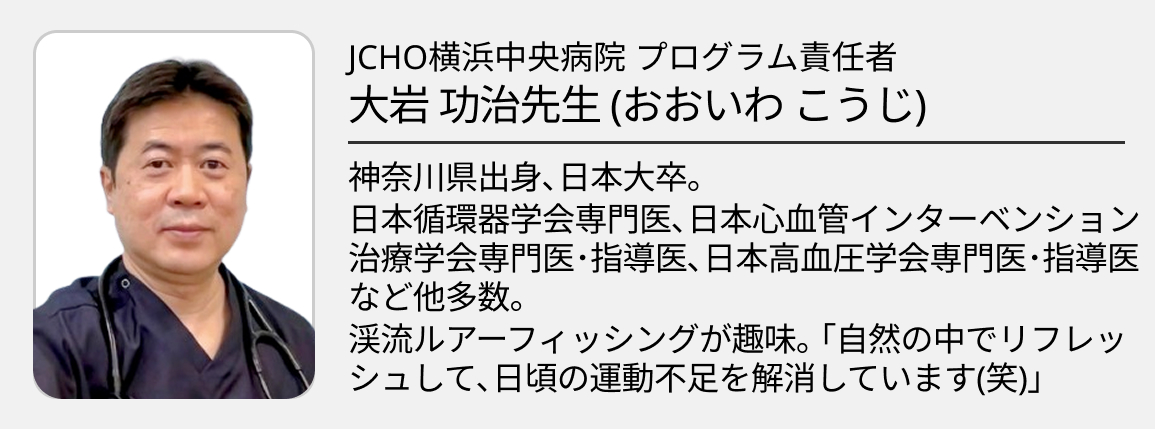
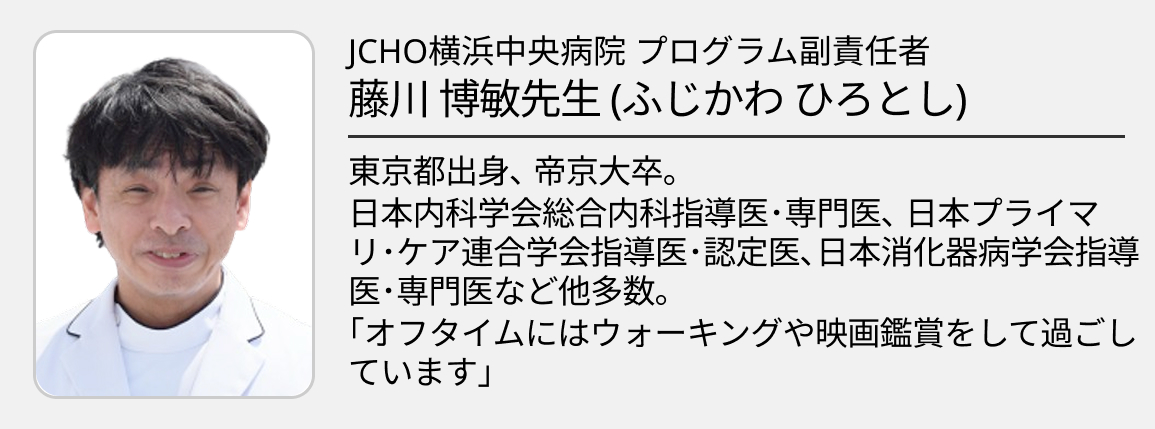
▶JCHO横浜中央病院 ホームページ
▶同病院 初期臨床研修医募集ページ ホームページ
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。