寄稿ライター
2年前
投資よりも外勤しまくる方が稼げる?
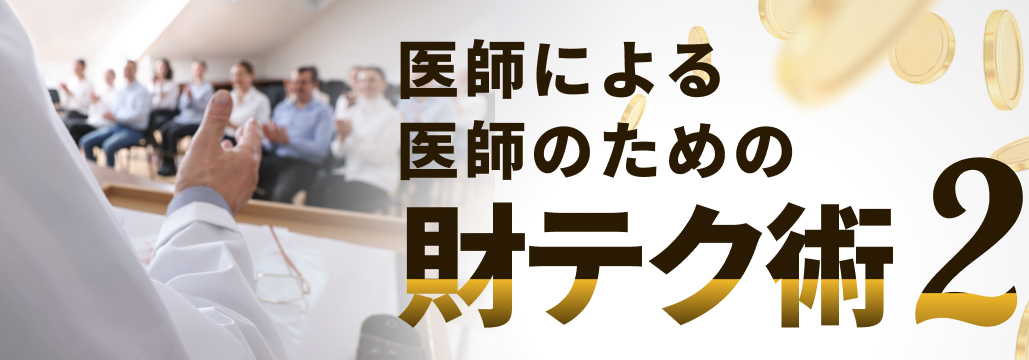
「投資するよりも堅実に働いたほうがいい」――。 こう考える医師は周囲にも多くいます。 連載「医師による医師のための財テク術」の2回目では、 実際のところどうなのか、 お話します。
※本記事は執筆者の個人的な意見に過ぎません。 特定の投資方法の効果を保証するものではありません。 投資は自己責任でお願いします。
投資を敬遠しがちな医師
連載1回目では、 なるべく早く投資を始めて、 複利で運用する大切さをご説明しました。 外勤1回分 (月5万円) の資金を年利5%の複利で運用するシミュレーションをすると、 1年目の利益は3万円になります。 こういった話をすると、
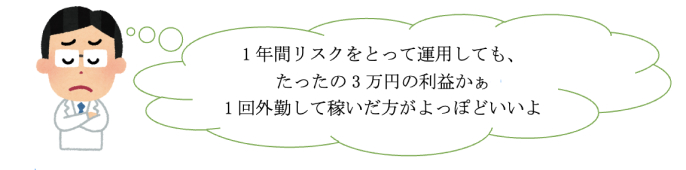
と思う医師は意外と多いです。 この背景には、 元々医師が高収入な上に、 常勤よりアルバイトの方が時給がいいという他に類を見ない業界特有の現象がありそうです。 では、 医師にとって投資は不要なのでしょうか?
医師が軽視しがちな 「 r > g 」 の法則
フランスの経済学者トマ・ピケティは、 過去200年間、 20か国以上の税金データを分析し、 「21世紀の資本」という本にまとめました。 原書は非常に分厚くて読むのは困難ですが、 中でも最も有名なのが「 r > g 」という法則です。
r は「資本収益率」、 つまり株式や不動産などを用いた資産運用による利回りのことです。 一方、 g は「経済成長率」、 賃金収入による収益を表しています。
過去200年のデータから、 r は平均5%程度で成長するのに対し、 g は平均1〜2%程度の成長にとどまるので、 資産家と労働者の格差は指数関数的にどんどん拡大してしまうというわけです。
でも、 こうなると先述の投資の稼ぎと医師のアルバイトの話で、 整合性がつかなくなってしまいますよね。 医師は「 r > g」の法則の例外なのでしょうか?

医師の人的資本としての価値を考える
医師の収入を先の式に当てはめてみましょう。 厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、 2022年度の医師の平均収入は約1400万円。 25歳から65歳まで40年間勤務したとすると、 生涯年収は5.6億円となります。
つまり、 「5.6億円の人的資本を年2.5%で運用している」ということができます (本当はもっと複雑ですが、 イメージとして捉えてください)。 一方、 これだけの資産をいきなり運用している医師はめったにいないですね。 「人的資本としての医師の価値が高すぎるがゆえに、 (特に初期のうちは) 投資の大切さを実感しにくい」といえるのです。

r と g を最大限使って資産を最大化しよう!
医師は人的資本としての価値が高いほかに、 さらに特徴があります。 一般的な勤務医の特徴として、
- 若い時は外勤で稼げる (年をとるとキツくなる)
- 管理職になると、 時間外がなくなって逆に収入が減る場合がある
があります。 言い換えると、 医師は「相対的に若い時の人的資本としての価値を高めやすい」ということです。 一般の会社員が年功序列で給与が決まり、 若いうちは稼げなくて苦しいのと対照的です。
そして、 投資は若いうちから始めると複利で絶大な効果を発揮します。 そのため、 rとgの両輪をフル活用して資産を最大化するのに、 医師は最適な職業なのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。 第1回と合わせて、 若いうちから投資を始めることの重要性について説明させて頂きました。 今回のTake Home Messageは
- 医師の人的資本としての価値は高く、 特に若いうちの価値を努力で高めやすい
- 上記を利用して長期投資することで、 資産を形成することが重要
となります。 次回からは、 世間の物価高に対抗する方法について考えていきます。
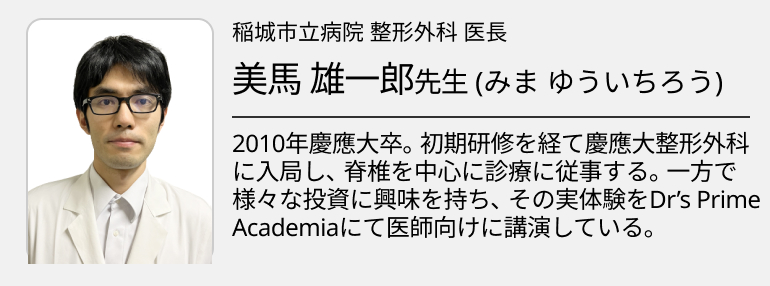
HOKUTO関連コンテンツ
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。