HOKUTO編集部
2ヶ月前
学会スライド作成もAIに相談!発表準備に役立つプロンプト3選

医療での生成AI活用のトップランナー、 大塚篤司先生によるChatGPT講座。 今回は、 学会発表準備に役立つ3つのプロンプトを紹介します!
はじめに
前回は、 学会抄録作成を支援するプロンプトを紹介した。 今回は、 抄録が採択された後の次なる関門 「スライド作成」 に焦点を当てる。
学会発表では、 自分の研究だけでなく、 扱う疾患について深い理解と新しい視点を示すことが求められる。 「疾患の全体像をどう整理するか」 「聴衆に何を持ち帰ってもらうか」 「自分の研究のユニークさを、 どう際立たせるか」 ・・・これらの課題に対して、 ChatGPTは強力な思考パートナーとなる。
今回は、 疾患理解を深め、 独自性のある発表を実現するための3つのプロンプトを紹介する。
バックナンバー
今日から使える!3つのプロンプト
1. 疾患の全体像を整理 : 背景スライドの作成
活用シーン
発表で扱う疾患について、 最新の知見を含めた包括的な背景スライドを作成する。 聴衆に疾患の重要性と研究の位置付けを理解してもらうための土台作りとなる。
プロンプト例
あなたは[専門分野]の指導医です。
[疾患名]に関する学会発表の背景スライド (2-3枚) の内容を提案してください。
【発表情報】
- 学会 : [学会名]
- 聴衆 : [専門医/研修医/他科医師など]
- 私の研究テーマ : [簡潔に1-2文で]
【出力形式】
スライド1 : 疾患の全体像
1. 疫学データ (最新の統計を含む)
- 有病率/発症率 :
- 好発年齢・性差 :
- 地域差・人種差 :
2. 臨床的重要性 (3点)
- 患者QOLへの影響 :
- 医療経済的負担 :
- 社会的インパクト :
3. スライド用ビジュアル案
- 推奨する図表 :
- 強調すべきデータ :
スライド2 : 現在の課題と未解決問題
1. 診断における課題
-
-
2. 治療における課題
-
-
3. 予後・管理における課題
-
-
4. 本研究が取り組む課題 (1文で明確に)
スライド3 (必要に応じて) : 最新の進歩
1. この2-3年の重要な発見
-
-
2. ガイドラインの変更点
-
3. 今後期待される展開
-
活用のコツ
● 疾患名は、 略語ではなく正式名称を用いて正確に記載する
● 聴衆のレベルに応じて専門用語の使用を調整
● 自分の研究との関連性を明確にすることで、 発表の流れをスムーズに
2. 疾患のエッセンスを凝縮 : まとめスライドの作成
活用シーン
発表の最後に、 扱った疾患について聴衆が持ち帰るべき重要ポイントをまとめる。 自分の研究成果を疾患理解の文脈に位置付ける。
プロンプト例
あなたは教育熱心な[専門分野]の専門医です。[疾患名]について、 学会発表のまとめスライドに含めるべき 、 「この疾患の理解に必須の5つのポイント」 を作成してください。
【背景情報】
- 私の研究内容 : [研究の要約]
- 主な発見 : [最も重要な知見]
- 対象聴衆 : [聴衆のレベル]
【出力形式】
まとめスライド : [疾患名]の要点
【覚えておくべき5つのキーポイント】
1. 病態生理の核心
「」 (30字以内のキャッチフレーズ)
- 補足説明 (1-2文)
2. 診断のピットフォール
「」 (30字以内のキャッチフレーズ)
- 見逃しやすい点 (1-2文)
3. 治療選択の原則
「」 (30字以内のキャッチフレーズ)
- 判断基準 (1-2文)
4. 予後を左右する因子
「」 (30字以内のキャッチフレーズ)
- 重要な予後因子 (1-2文)
5. 今後の展望 (本研究の貢献を含む)
「」 (30字以内のキャッチフレーズ)
- 期待される進歩 (1-2文)
【スライドデザイン提案】
- レイアウト : [5つのボックス/リスト形式/マインドマップ風など]
- 視覚的工夫 : [アイコン使用/色分けなど]
- 口頭での締めくくり文案 : 「」
活用のコツ
● キャッチフレーズは、 記憶に残りやすい表現を心がける
● 自分の研究成果を、 5つ目の 「今後の展望」 に自然に組み込む
● スライドは質疑応答中も表示されるため、 議論の起点となる内容とする
3. 研究の独自性を際立たせる : 新視点の発掘
活用シーン
自分の研究が持つユニークな視点や、 これまで注目されていなかった側面を発見し、 発表にオリジナリティを加える。
プロンプト例
あなたは革新的な視点を持つ[専門分野]の研究者です。
以下の研究について、 独自性や新規性を際立たせる 「これまでにない切り口」 を3つ提案してください。
【研究情報】
疾患 : [疾患名]
研究内容 : [研究の概要]
主な結果 : [主要な知見]
従来の研究との違い : [既存研究との差別化ポイント]
【出力形式】
提案1 : [切り口のタイトル]
1. 新しい視点の説明
- なぜこの視点が新しいのか :
- どんな発見につながるか :
2. スライドでの見せ方
- 視覚的表現のアイデア :
- 比較対象 (従来の見方vs新しい見方) :
3. 想定される質問と回答案
Q:
A:
提案2 : [切り口のタイトル]
[同様の構成で記載]
提案3 : [切り口のタイトル]
[同様の構成で記載]
【最も推奨する切り口】
上記3つの中で最もインパクトがあるのは[番号]です。
理由 :
-
-
発表での強調ポイント :
- 冒頭で触れるべき点 :
- 結論で再度強調すべき点 :
活用のコツ
● 「世界初」 「本邦初」 にこだわらず、 「新しい解釈」 「異なる角度」 を重視する
● 批判的な質問を想定し、 防御的にならず建設的な議論につなげる準備を行う
● 奇をてらいすぎず、 科学的妥当性を保ちながら独自性を追求する
実践例で確認! 学会スライド作成の3ステップ
「アトピー性皮膚炎の新規治療に関する発表の作成」 を想定して、上記で紹介したプロンプトを用いた学会スライド作成の流れを以下に示す。
1. 疾患の全体像を整理
プロンプト1を使用。 アトピー性皮膚炎の疫学、 病態、 現在の治療体系を整理する。
特に、 近年の生物学的製剤の登場による治療パラダイムシフトを強調する。
2. 要点のまとめ
プロンプト2を使用。 「アトピー性皮膚炎治療の5つの転換点」 として、 自分の研究成果を最新の進歩の一つとして位置付ける。
3. 新しい視点の発掘
プロンプト3を使用。 「皮膚バリア機能の日内変動に着目した新しい外用療法戦略」 という切り口で、 「投薬タイミングの最適化」 という新視点を提示する。
よくある失敗とその対策
1. 疾患の全体像が「教科書的な説明」 になってしまう
対策
プロンプトに、 「なぜ今、 この疾患の研究が重要なのか」 という現代的文脈を必ず加える。
2. 独自性を強調しすぎて、 科学的根拠が薄弱になってしまう
対策
新しい視点は既存のエビデンスに基づいて展開する。 また、 「推測」 と 「事実」 を明確に区別して提示する。
3. まとめが総括的で、 印象に残らない
対策
「3つ覚えて帰ってください」 など、 具体的な数で限定する。 キーワードやフレーズを繰り返し使用して記憶に定着させる。
1. “疾患の全体像”で聴衆と共通認識を作る
2. “要点のまとめ”で持ち帰ってもらう知識を明確化する
3. “新しい視点”で研究の独自性を際立たせる
このプロセスをAIと協働で進めることで、 疾患の理解を深め、 独自性のある発表を実現できる。
ChatGPTは、 あなたの専門知識を整理し、 新たな角度から光を当てる優れたパートナーとなる。 しかし、 最終的に価値ある発表を作るのは、 患者さんと向き合い、 日々研究に取り組むあなた自身の経験と洞察である。
AIとの対話を通じて、 自分でも気づいていなかった研究の魅力を発見し、 それを聴衆と共有する。 そんな創造的なスライド作成プロセスを、 ぜひ体験してほしい。
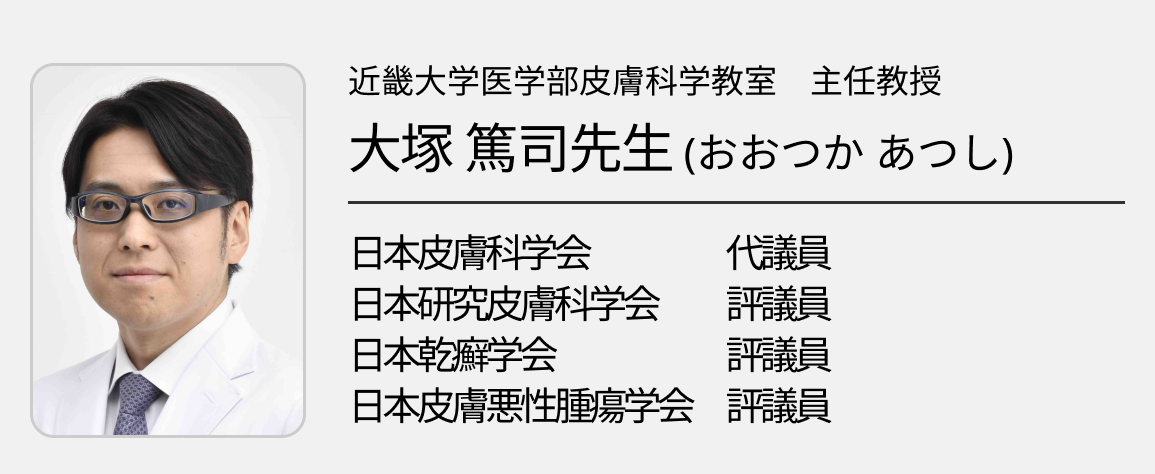
大塚先生執筆の書籍はこちら!
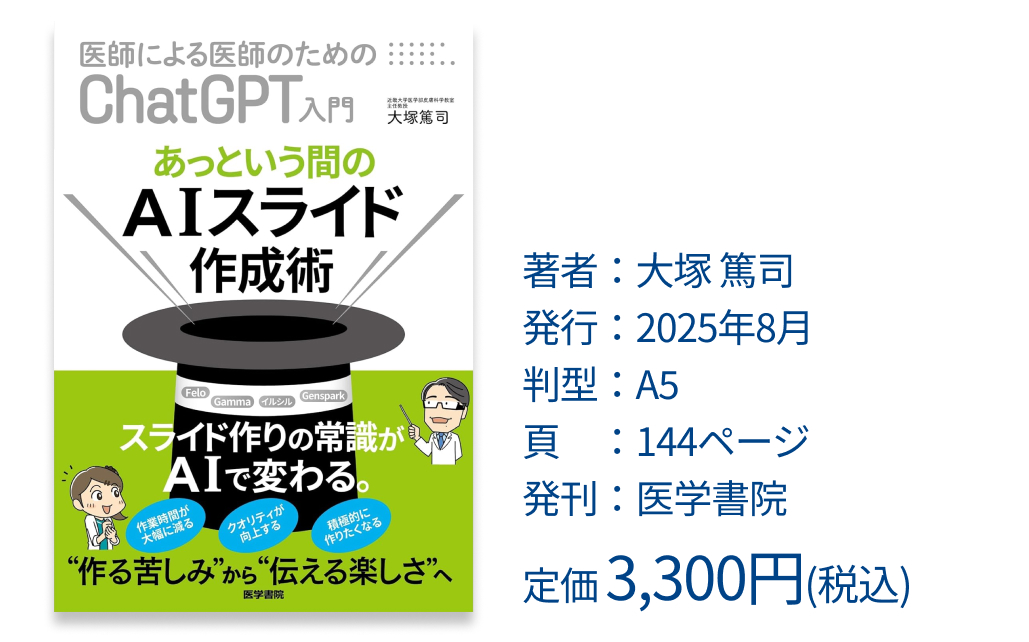
医師による医師のためのChatGPT入門
あっという間のAIスライド作成術
2025年8月発刊! 「スライドづくりの時間が足りない」 を一瞬で解決。 各種生成AIを場面別に使い分け、 構成やデザインをあっという間に整える実践書。 「伝える」 スライド作成のテクニックも公開!
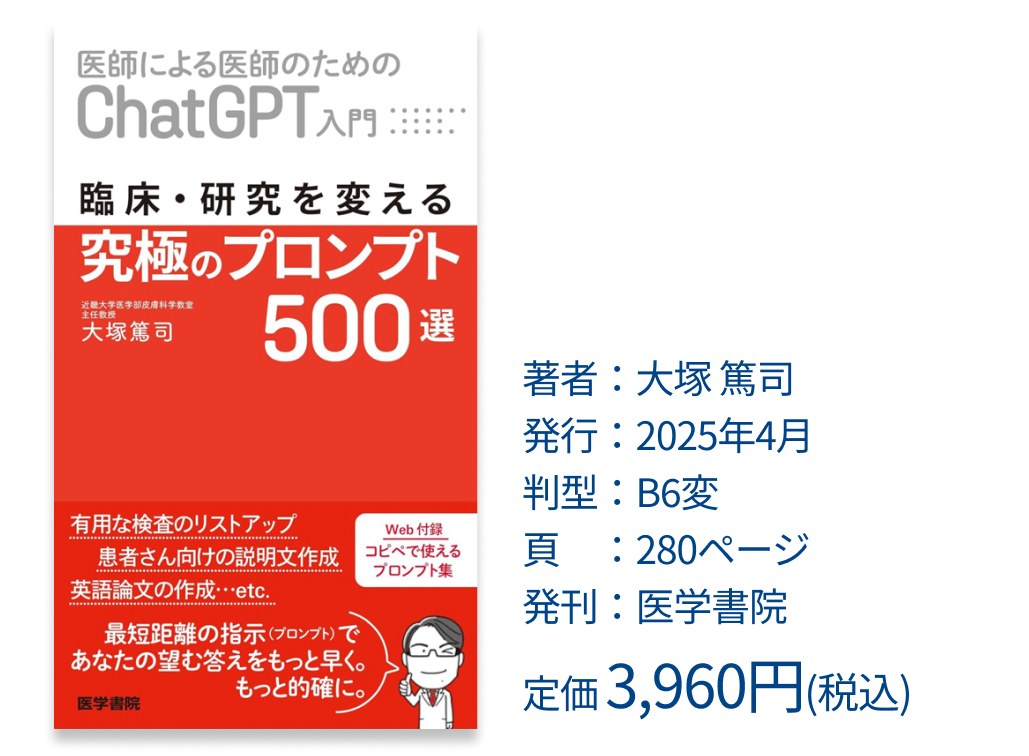
医師による医師のためのChatGPT入門
臨床・研究を変える究極のプロンプト500選
2025年4月発刊!医療現場でそのまま使えるプロンプトをテーマ別に収載。 日々の診療・教育・研究に役立つ実践的な1冊。
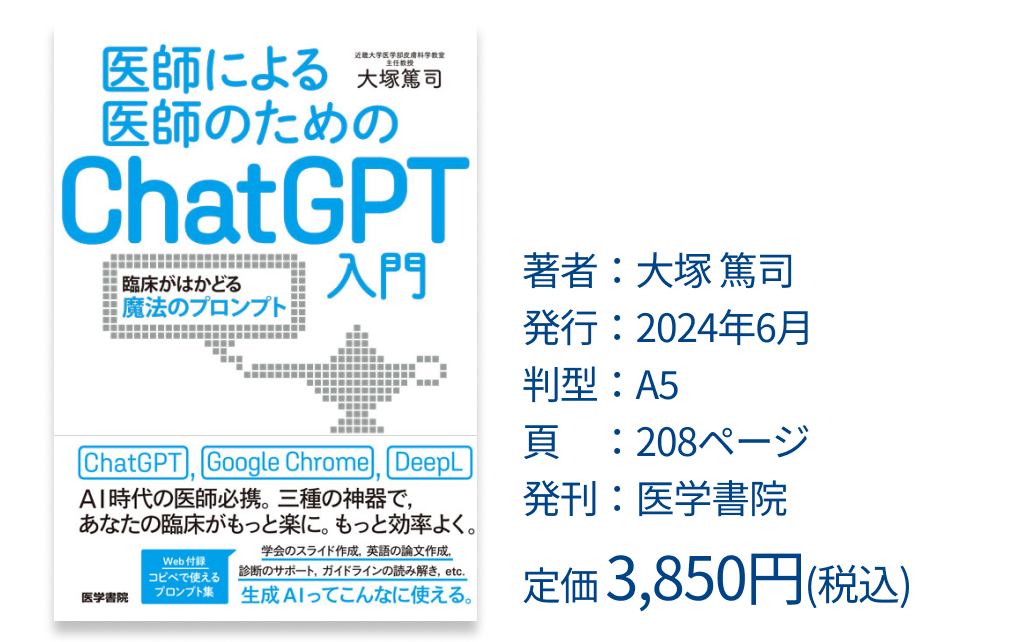
医師による医師のためのChatGPT入門
臨床がはかどる魔法のプロンプト
ChatGPTに苦手意識のある医師に向け、 基本的な使い方から日常業務での活用法までを、 会話形式で丁寧に解説。
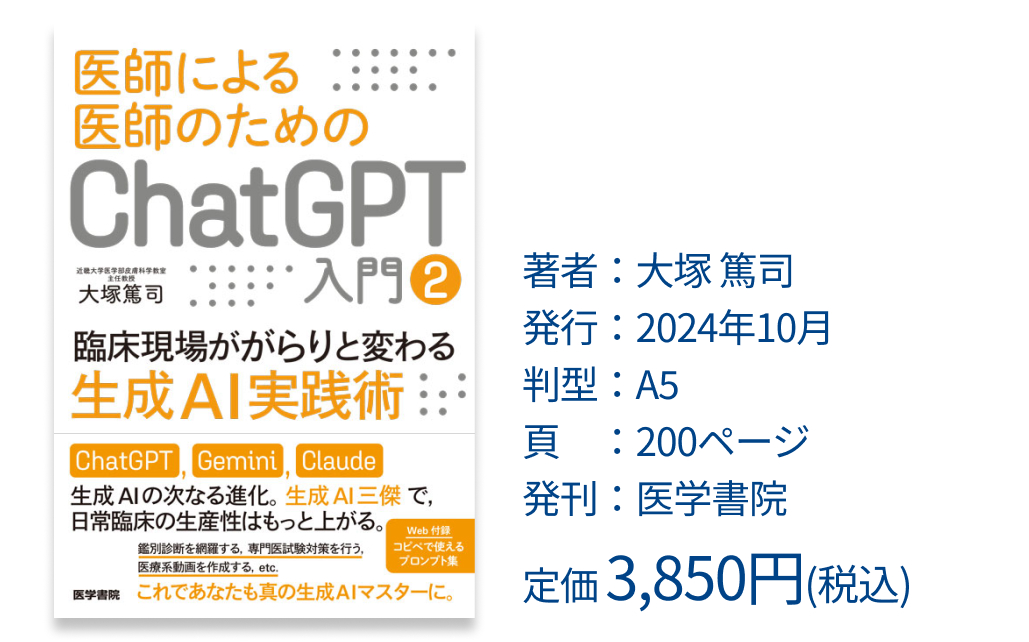
医師による医師のためのChatGPT入門 2
臨床現場ががらりと変わる生成AI実践術
GeminiやClaudeなどの登場で広がる最新の活用法を網羅。 前作に続き、 実例とともに理解が深まる構成。
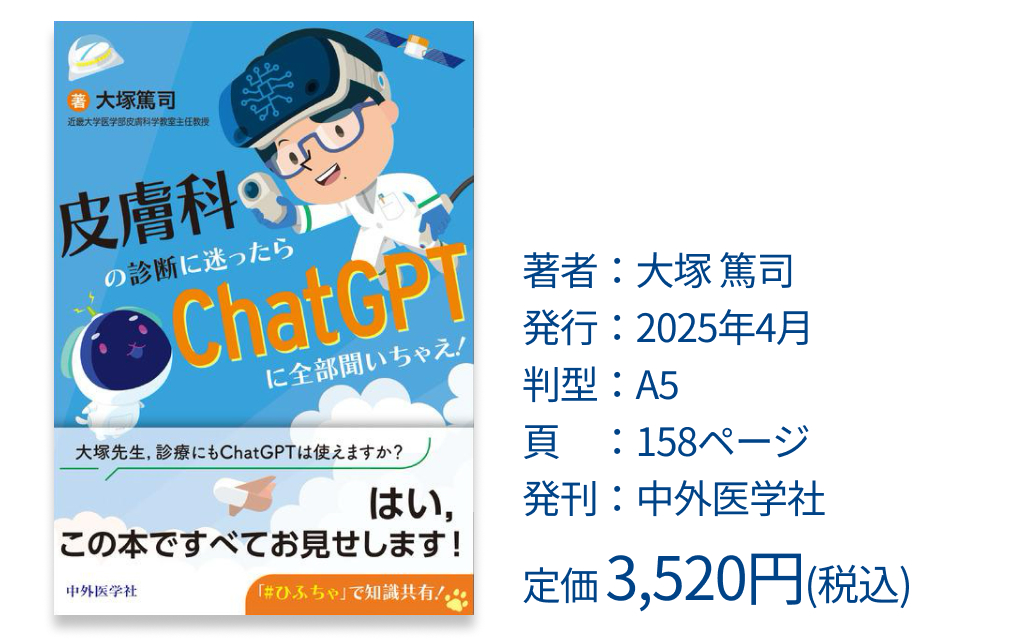
皮膚科の診断に迷ったらChatGPTに全部聞いちゃえ!
紅斑・丘疹・鱗屑など皮疹の"見え方"を言語化し、 ChatGPTで鑑別リストを引き出す手順を症例対話で丁寧に指南。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。