栄養療法マニュアル
2年前
【栄養療法】Refeeding syndrome
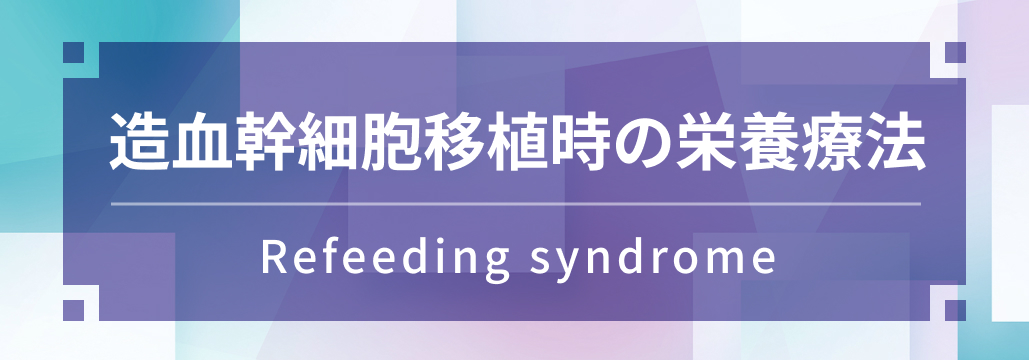
本コンテンツは造血幹細胞移植時の栄養療法について、 専門医の視点からわかりやすい解説を行う企画です。 是非とも臨床の参考としていただければ幸いです。
解説医師
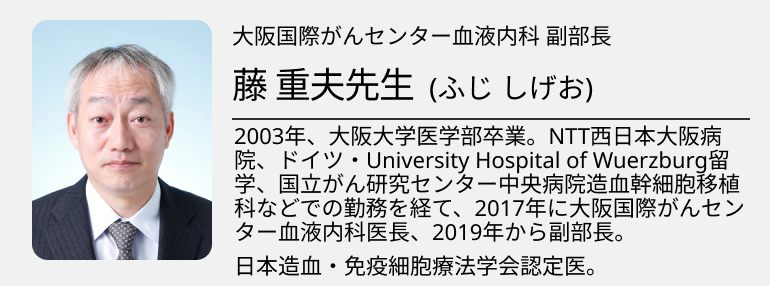
ポイント
- Refeeding syndromeのリスクがある場合には無理せずに少量の末梢静脈栄養 (PPN) より開始し漸増する。
- 電解質のフォローも必須である。
Refeeding syndromeの概要
Refeeding syndromeは、 長期にわたる低栄養状態から急激に栄養を摂取した際に起こる代謝性合併症である。 栄養補給により、 インスリンの急増と共にリン、 カリウム、 マグネシウムなどの電解質が細胞内に移動し、 血中濃度が低下する。 これにより、 心不全、 呼吸不全、 腎不全、 肝機能障害などの重篤な症状を引き起こす可能性がある。 特に、 リン不足はエネルギー代謝や酸素運搬に必須であり、 その欠乏は多様な臨床症状を生じさせる。 したがって、 適切な栄養補給のペースとモニタリングが重要である。
Refeeding syndromeのリスク因子
移植後早期にはあまり経験されないが、 慢性期に外来で高度の低栄養状態が続いていたことが後に判明することは経験される。 そのような症例の栄養管理を進める際にrefeeding syndromeのリスク因子¹⁾を把握しておくことは重要である。
▼主リスク因子
- BMI<16kg/m²
- 3~6ヵ月間で>15%の体重減少
- 10日以上ほとんど経口摂取がない
- 栄養投与前にカリウム、 リン、 マグネシウムが低い
▼副リスク因子
- BMI<18.5kg/m²
- 3~6ヵ月間で>10%の体重減少
- 5日以上ほとんど経口摂取がない
- アルコール多飲、 薬物投与 (インスリン、 化学療法、 制酸薬、 利尿薬)
主因子が1つもしくは副因子が2つあればrefeeding syndromeの高リスクと判断する。
高リスク例への栄養補充
Refeeding syndromeの高リスクと判断された場合には、 一般的には<10kcal/kg/dayまでの補充にとどめ、 4~7日間検査するなどフォローが必要である¹⁾。 特に重症例 (BMI<14kg/m²や15日以上ほとんど経口摂取がない例) では、 さらに投与カロリーを減らし5kcal/kg/day程度で10日間程経過をみることも検討される。
電解質のモニタリング
この時にビタミンB₁を含むビタミン製剤や微量元素製剤は投与して良い。 元々移植後にはフォローされていることが一般的であるが、 電解質のモニタリング (ナトリウム、 カリウム、 カルシウム、 無機リン、 マグネシウム) を行いつつ、 適宜補充にて対応する²⁾。
参考文献
- Refeeding syndrome: screening, incidence, and treatment during parenteral nutrition. J Gastroenterol Hepatol (2013) 28 Suppl 4:113-7. PMID: 24251716.
- Refeeding Syndrome: A Critical Reality in Patients with Chronic Disease. Nutrients. 2022 Jul 12;14(14):2859. PMID: 35889815
関連コンテンツ
入院患者の栄養状態
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。