インタビュー
2年前
3次救急なのに穏やか 〜 新潟県立中央病院 〜

屋根瓦式指導体制を強化し、 対話での振り返りで学びをサポートしている
3次救急病院でありつつ、 穏やかな雰囲気ーー。 一見、 相反するようなテーマを両立させているのが、 新潟県立中央病院です。 その成果なのか、 研修医の志望者数は年々増加しています。 今回は、 総合内科医長で同病院メンター制度の責任者でもある木島朋子先生にプログラムの特徴などを聞きました。
※肩書きや内容はインタビュー当時 (2023年9月) のものです。 現在とは異なる場合があります。
病院の概要
上越医療圏 (人口25万人) の基幹病院です。 3次救急病院として年間約5400台(2022年)の救急車を受け入れるほか、 地域がん診療連携拠点病院として高度ながん医療を提供しています。
半径約100km以内に大学病院がなく、 職員全員が 「最後の砦」 の意識を持って働いています。 各診療科が縦割りとならず、 横断的に一丸となって診療に当たっています。

研修医に手厚いバックアップ
段階的に成長できる当直体制
「医学生にヒアリングをすると、 3次救急病院は重症患者が押し寄せ、 緊張の連続なのではという不安の声も多いです。 そこで、 バックアップ体制をしっかり敷き、 段階的に成長できるような当直体制をとっています」
具体的には、 1年目の前半は、 2年目の先輩研修医と深夜0時までの副直に入ります。 必修の救急科研修を終えた1年目の後半から同期または先輩と2人で入り、 2年目には指導役に回ります。
「当直では研修医のほかに、 常に上級医が3人います。 また、 放射線科の医師が自宅に読影モニターを設置しており、 24時間体制で読影してくれます。 研修医が孤立したり困惑したりすることがないようにしています」

2022年度の救急車搬入患者数は新潟県内3位の5422人
孤立させないメンター制度
同病院では2021年から、 5〜15年目の若手・中堅医師が研修医の抱える悩みなど問題解決をサポートするメンター制度を導入しました。 木島先生は発起人で、 責任者でもあります。
「研修医が当直などで辛い思いをした時に、 上級医が誰も気づいていないということが過去にあったことも事実です。 研修医の困りごとをしっかり拾いあげるシステムを構築する必要性を感じ、 導入しました」
若手医師専用の 「第3医局」
「研修医・若手医師専用の医局 (第3医局) もあります。独立した仮眠室があり、 Wi-Fiや電子カルテも完備しているほか、 医学系雑誌なども充実しています」

第3医局。 個人スペースは広く、 共有スペースと分けて配置

なぜ、 ここまでサポート体制を手厚くするのか
「心理的安全性を高めるのは研修の必須条件と考えています。 不安を抱えたままではチャレンジ精神は生まれず、 スキルアップなどあらゆる面で支障が出るためです。 こうした取り組みが口コミなどで広がった結果、1年次研修医数は10年前に比べて倍増しました」
研修医の視点
自由選択期間が長い
実際、 研修医はどんな理由で同病院を研修先に選んだのでしょう。 研修医の率直な気持ちなどをX (旧Twitter) で発信しています。 以下は一例です。
「3次救急、 ほぼ全ての診療科がある+自由選択期間が11カ月と長い」
「先輩研修医の穏やかな雰囲気が自分に合うと感じた」
「雰囲気の良さ。 若手のみの第3医局はリラックスした環境で相談もしやすい」

研修医同士の写真
内科・外科バランスのよい進路
研修終了後の進路は、 内科・外科のバランスが取れているのが特徴といえます。
「内科、 麻酔科、 病理診断科が人気の傾向にありますが、 非必修科も含めてほぼ満遍なく選択されています。 研修後の専門科を決めていない人にとってもオススメのプログラムといえます」
強みを伸ばすフィードバック
最後に、 木島先生に医学生へのメッセージを聞きました。
「今の医学生は、 進路選択だけとっても病院勤務だけでなく開業、 起業、 行政、 留学と多様な選択肢があり、 悩むことが多いと思います。 一方、 不得意な分野も頑張って勉強し、 まんべんなく全部できるようにしてきた医学生が多く、 自分の本当に得意なこと、 好きな分野に気づいていないのではないでしょうか」
「これからの時代、 自分の強みを知って個性を活かし、 できないことはお互いに補い合いながら、 自由に好きな分野に取り組んでほしいです。 当院では客観的に見た個性・強みを伸ばすようなフィードバックをしています。安心して研修にきてください」
先生のプロフィール
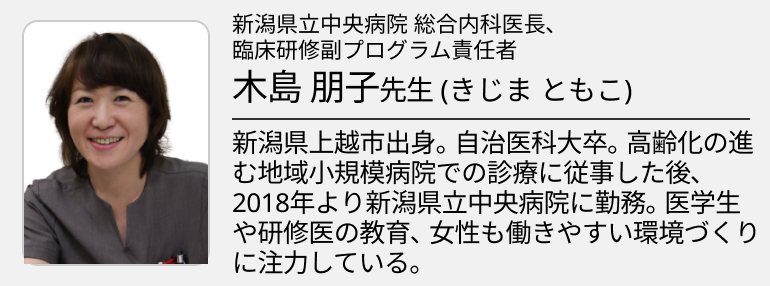
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。