寄稿ライター
7日前
LINEでの説明は有効か

医療訴訟が珍しくなくなった今、 医師は法律と無関係ではいられない。 連載 「臨床医が知っておくべき法律問題」 第20回のテーマは、 「LINEでの患者説明は有効か」。
LINEでの説明 : 医師の責任はどこまで問われるのか
新型コロナ以降、 オンライン診療が注目されるようになった。 なかでもLINEを使った診療連絡や、 Web経由での処方箋送付などは、 今や多くの医療機関で日常的に行われている。
慢性疾患の継続処方に限れば、 「3時間待って3分診療」 と揶揄される現状において、 オンラインの方が合理的とさえ言える。

写真はイメージです
それでは、 診療結果についてLINEで説明するような場合、 法的にはどのように位置づけられるのであろうか。 「LINEで説明を済ませたつもりが、 後に訴訟で問題になるのでは?」 と不安に思う医師も多いのではないか。 実際、 医療訴訟では、 「医師がきちんと説明してくれなかった」 との訴えが非常に多い。
今回は 「説明義務」 にまつわる法的な枠組みを再確認しつつ、 オンライン診療時代の情報提供のあり方について考えてみたい。
説明義務の法的位置づけ
医師の説明義務は、 医療法・医師法に根拠を持つ 「公法上の義務」 であると同時に、 診療契約に基づく 「私法上の義務」 ともされている (最高裁昭和56年6月19日判決)。
説明は患者の自己決定権を保障するために必要なものであり、 その内容は厚労省の指針 (平成15年9月) により一定の基準が示されている。

写真はイメージです
具体的には、
- 症状や診断名
- 治療方針
- 処方薬の効能・副作用
- 代替治療法の有無と費用差
- 手術のリスクや合併症
などを丁寧に伝えることが求められる。 これらを押さえた記録があれば、 裁判でも説明義務違反を認められにくい。
誰が、 いつ、 どのように説明すべきか
説明の 「主体」 は必ずしも主治医本人でなくともよいとされている (最高裁平成20年4月24日判決)。 チーム医療の中で、 主治医が適切な知識を持ち、 上位者が指導・監督していれば、 たとえ執刀医自身が説明していなくても責任を問われないとするものだ。
また、 説明の 「時期」 についても、 医師の裁量に一定の幅が認められている。 例えば、 胃がんの診断を入院後1か月後に伝えた事例で、 大阪地裁 (平成16年4月26日判決) はこれを適切と認定している。

写真はイメージです
裁量と言っても、 自己決定権の行使のための熟慮に必要な期間と、 侵襲行為までの猶予とのバランシングは必要であろう。
説明方法に 「LINE」 は通用するのか?
最も関心の高いのが 「方法」 だろう。 直接の対面説明が原則とされる一方で、 先ほど紹介した最高裁平成20年4月24日判決では、 執刀医が一切説明していなかったにもかかわらず、 「必要な情報がチーム内で共有され、 しかるべき人が説明していれば説明義務を果たしたと評価できる」 と判断された。 これは、 必ずしも 「誰がどの手段で説明したか」 にこだわらず、 「必要な情報が患者に伝わったか」 が重視される姿勢を示している。

写真はイメージです
この考え方に立てば、 LINEや動画、 テキスト形式の説明であっても、 患者が手術等の判断に必要な情報を得ていれば、 説明義務を果たしたと評価されうる。
同意書よりも、 リアルな記録を
医療訴訟の現場では、 説明内容の立証に使われるのは主に 「同意書」 だが、 これはあくまで形式的な証拠にすぎない。 リスクなど説明すべき内容が、 患者に告知された事実認定には有用であるが、 「理解できたか」 「同意したのか」 という点を争うことも多い。
同意の点については、 例えば、 カルテに 「患者『腹をくくりました、 お願いします』との談あり」 とあれば、 少なくとも同意に関してはより高い証拠力を持つ。
重要なのは、
- 説明内容や対象が明確に記載されていること
- 具体的な言葉で迫真性があること
- 説明の直後に記録されていること
の3点セットである。 これは性犯罪訴訟などでの事実認定にも通じる要素だ。
説明を 「義務」 として捉え直すと…

写真はイメージです
もっとも、 不動産や介護業界では、 契約前に有資格者が身分証を示した上で対面で 「重要事項説明」 を行うことが法的に義務づけられている (宅建業法、 高齢者住居安定法など)。 医療は本来これらと異なるが、 今後は説明書の交付が常態化していく可能性もある。 そうなれば、 むしろLINEで説明書を送り、 テキスト記録を残す方が、 対面のみの説明よりも医師を守る手段になるかもしれない。
「嘘八百」 に備える医師の防衛
1時間かけて丁寧に説明しても、 後になって 「何も聞いていない」 と主張されることがあるのが医療訴訟の現実である。 医療の場合、 医師が一度も患者と話をしないことは現状では考えられないので、 これにプラスしてLINEやテキストベースの説明は、 やりとりがログとして残る点で、 医師にとって有利だ。
説明の質さえ担保されていれば、 「全て対面でなければならない」 という硬直的な発想は、 もはや時代遅れなのかもしれない。
プロフィール
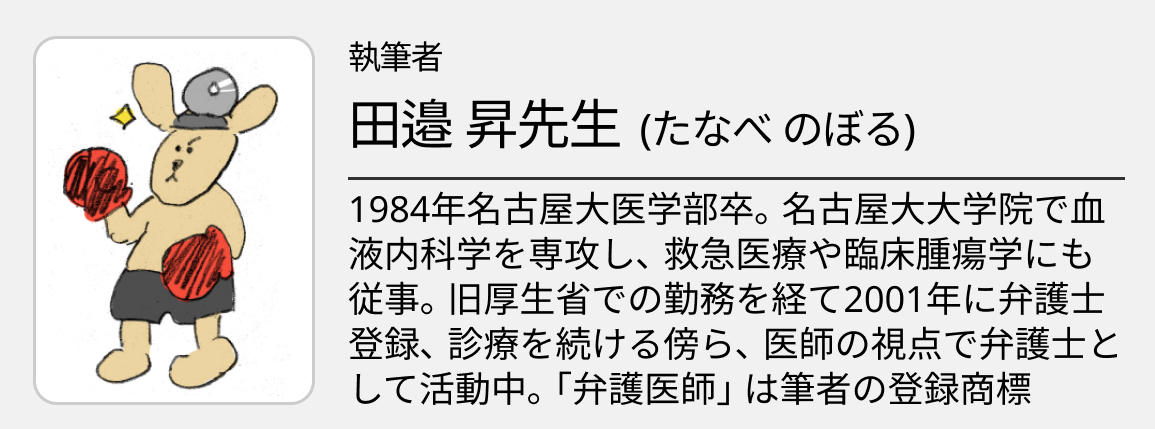
HOKUTO関連コンテンツ
- 薬物中毒の患者が受診した際、 通報すると守秘義務に違反する?
- 院内で発生した居座り患者、 どう対処する?
- 酔っ払いはうんざり…酩酊患者は放っておいていいの?
- 韓国・研修医のストライキは日本でも起こりうるのか
- 専門外領域の診療拒否は応召義務違反になるの?
- 患者の自主退院と誓約書、 医療者の責任とリスクは?
- 輸血拒否の患者、どうする?
- 認知症患者の同意をどう取るか
- 医療事故調査をめぐる問題
- 母体保護法と配偶者の同意
- 訴訟の多い診療科は?医療裁判の統計
- 説明義務違反と損害賠償
- 偶発腫を見落としたら責任を問われるのか
- 中居騒動の 「秘密保持条項」、 医療現場での効力は?
- 医師が知っておくべき 「解剖」 問題
- 【解説】自治医大訴訟を巡る法的論点
- 令和で激減?医療訴訟の逆転判決
- 重過失ってなんだ?
- ペイハラ対応の司法判断

編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。