寄稿ライター
9ヶ月前
医師が知っておくべき 「解剖」 問題

医療訴訟が珍しくなくなった今、 医師は法律と無関係ではいられない。 連載 「臨床医が知っておくべき法律問題」 15回目のテーマは、 SNS投稿が炎上して話題となった 「解剖」 について。
解剖を巡っては2024年末、 美容外科医がグアムにおける解剖研修で撮影した写真をSNSに投稿し、 炎上したことは記憶に新しい。 美容外科医の行動に対しては、 日本形成外科学会が 「断じて容認することはできない」 とする声明を発表している。
解剖の種類
死体解剖には、 ご存じの通り、 いくつか種類がある。
1. 系統解剖
献体された死体に対して、 医学部の解剖学の講義目的で行う
2. 病理解剖
臨牀のために死後、 死亡原因を確認するために行う
3. 行政解剖
事件性はないと判断された遺体の死因究明を目的に行う
4. 司法解剖
犯罪事件の可能性をもとに行う
1~3は死体解剖保存法によって規定され、 4は刑事訴訟法に基づいている。

写真はイメージです
系統解剖は解剖学の教授などが行う限り許可は不要。 病理解剖なども、 病理医の資格があれば死体解剖保存法の規定により、 特に厳格な手続きは不要である。 一方、 司法解剖は個々の解剖について裁判所の令状に基づいて行われる手続きである。
死体の保護は?
いずれの解剖も、 生きている人間の手術と比較して、 特に手厚く死体が保護されているわけではない。 個人情報保護法でも、 生きていれば病歴などの個人情報は保護されるが、 死んでしまえば原則として一切の保護はない。
美容外科医の炎上問題についてみると、 確かに、 日本法では、 死体への敬虔の感情が刑事罰をもって保護されている。
法律の世界では死んでしまえば、 死体は 「物」 として扱われる。 殺人や傷害は重い刑事罰があるが、 死体を傷つけた場合に該当する 「器物損壊罪」 の懲役刑は3年。 ただ、 墳墓を発掘して死体を持ち去る墓荒らしは3月以上5年以下の懲役で、 かなり重くなっている。 敬虔感情を刑法上評価していると思われるが、 墳墓という土地建物への侵害への評価もあろう。
遺体の所有権は?

写真はイメージです
死体は 「物」 なので所有者がいる。 遺族が所有者と考えられる。 解剖の際に死体を大学などに贈呈する意思表示があれば、 所有権は移転する。
1~3の解剖では、 法律により 「遺族の承諾を受けなければならない」 と定められている。 日本病理学会は遺体の所有権について 「遺族のもの」 とする見解を示した一方で、 平成27年11月の通知では、 「保管できないような遺族には渡すべからず」 としている。
この場合に判断が揺れるのが、 プレパラートなどの病理標本の引き渡しである。
一般的に考えれば、 遺族が 「遺体を火葬するために引き渡してほしい」 と求めれば、 当然引き渡すのであろう。 ただ、 加工してプレパラートになっている場合、 価値が上がっていると考えれば病院側に所有権が移動すると考える余地もある。

民法246条では、 物に加工を加えた場合、 同条1項で、 原則は原料 (死体がプレパラートの原料というのは敬虔さを欠くかもしれないが) 提供者の所有物であるが、 加工により価値が著しく上がった場合は 「加工者がその加工物の所有権を取得する」 とされる。
加工者が材料の一部を提供したとき (スライドグラスや染色液、 パラフィンなどであろう) は 「その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、 加工者がその加工物の所有権を取得する」 とされているからである。
裁判例 (東京地裁判決、 平成14年8月30日) では、 プレパラートの引き渡しについて、 死体解剖保存法17条に該当する病理解剖ができる特定機能病院や地域医療支援病院などの大きな病院であれば、 プレパラートなどは返す必要はないが、 同法18条では保健所長の許可で解剖したような場合は返しなさいと定めている。
今後、 再生技術やクローン、 遺伝子操作などで死体の価値が大きく変動するかもしれない。 敬虔感情などで説明できない、 遺体や解剖をめぐる問題が出てきそうである。
プロフィール
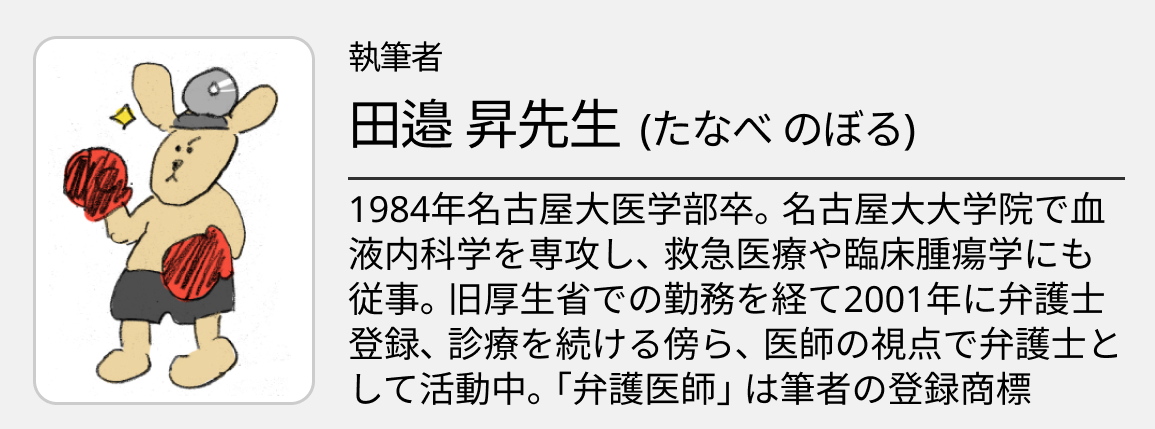
HOKUTO関連コンテンツ
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。