HOKUTO編集部
5ヶ月前
【最新推奨】MDS診療におけるゲノム活用と移植適応判断
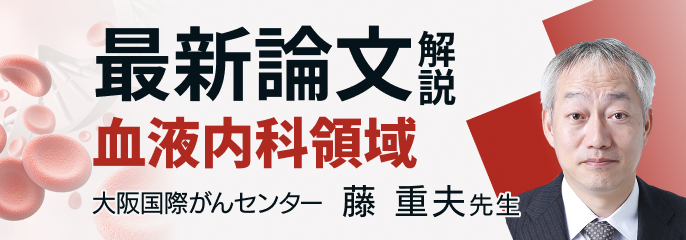
Clinical-genomic profiling of MDS to inform allo-HSCT:Recommendations from an international panel on behalf of the EBMT
Blood. 2025 Feb 19:blood.2024025131.
骨髄異形成症候群 (MDS) は極めて多様な疾患群であり、 その予後は患者背景や疾患生物学的特性によって大きく異なる。 唯一の根治療法である同種造血幹細胞移植 (allo-HSCT) は、 高リスク例において有力な治療選択肢となるが、 その適応判定および実施時期の判断は、 長らく難題とされてきた。 本稿では、 欧州骨髄移植学会 (EBMT) による最新の国際推奨¹⁾を整理し、 臨床現場での実践的な活用法を概説する。
IPSS-Mを用いたリスク分類
MDSにおけるリスク評価は、 従来のIPSS-Rから、 より詳細な遺伝子変異情報を組み込んだIPSS-M (Molecular IPSS) が新たな標準となった。
IPSS-Mは、 血球減少の程度、 骨髄芽球比率、 細胞遺伝学的所見に加えて31種類の遺伝子変異情報を統合し、 予後を6段階に層別化するものである。
このIPSS-Mは、 国際MDS予後評価作業部会 (International Working Group for Prognosis in MDS : IWG-PM) によって開発され、 オンライン計算ツールも提供されている。
▶ IPSS-Mスコアは以下の公式サイトから簡便に計算可能であり、 カンファレンスや患者説明時に有用である。
公式サイト (英語) は👉こちら
HOKUTOツールは👉こちら
移植適応の評価
疾患関連リスク因子
IPSS-Mの 「高リスク」 または 「非常に高リスク」 群は、 診断時点から移植適応を検討すべき対象となる。
一方、 「非常に低リスク」 群は、 原則として移植の適応外とされる。
「低リスク」 または 「中低リスク」 群においては、 以下の条件に該当する場合、 早期の移植検討が望ましい。
- 骨髄系腫瘍に対する遺伝性素因あり
- 輸血依存が持続し、 内科的治療に不応
また、 治療関連MDS (t-MDS) や、 難治性炎症を伴うVEXAS症候群合併例についても、 疾患進行を待たず移植を考慮すべきである。
患者関連リスク因子
移植適応の判断は、 患者の身体的背景や全身状態に基づく評価も極めて重要である。 EBMT推奨では、 患者関連因子を総合的に評価し、 移植適応の可否を判断することが示されている。
【移植適応あり (fit) 】
- 年齢80歳未満
- KPS*スコア80%以上
- HCT-CI**スコア0~2 (低~中リスク)
- MDS特異的Frailty Index***<0.3
*Karnofsky Performance Status
**Hematopoietic Cell Transplant-Comorbidity Index
***身体能力、 併存疾患、 検査値、 日常生活動作、 QOL、 PSなど、 42項目の指標を統合した評価尺度²⁾。
🔢 KPS (Karnofsky Performance Scale)
🔢 HCT-CI
【移植適応なし (unfit) 】
- 年齢80歳以上
- KPSスコア80%未満
- HCT-CIスコア3以上 (高リスク)
- MDS特異的Frailty Index≧0.3
サブタイプ別の治療戦略
EBMT推奨では、 MDSを分子サブグループに分類し、 移植適応性について言及している。 臨床現場で特に押さえておくべきサブグループは以下の通り。
移植適応を積極的に検討すべき群
TP53バイアレリック変異MDS
極めて予後不良であり、 治療抵抗性が強い。 移植後再発率は高く、 臨床試験参加を優先的に検討する。
AML様MDS
生物学的に急性骨髄性白血病に類似しているが、 骨髄芽球比率が20%未満である点が異なる。
DDX41変異MDS
白血化進展リスクが高い進行性疾患であるが、 他の芽球過剰型MDSと比較すると予後は比較的良好である。 なお、 DDX41変異を有する患者では重度の急性GVHD発症リスクが高いことが報告されており、 移植時にはドナー選択とともに、 PTCy (移植後シクロホスファミド) によるGVHD予防戦略が重要となる。
U2AF1、 SRSF2、 BCOR/L1、 -7/SETBP1、 IDH–STAG2、EZH2–ASXL1変異MDS、 der(1;7)異常を伴うMDS
いずれも進行が速く、 予後不良で白血化リスクが高い疾患群である。 ドライバー変異を標的とした治療薬 (例 : スプライソソーム阻害剤、 ivosidenib、 enasidenibなど) の開発が進められているが、 現時点での標準治療は移植である。
共変異を鑑みて移植適応を検討すべき群
del(5q) MDS
確立されたMDSのサブタイプであり、 予後は共存する遺伝子変異パターンにより左右される。 特にSF3B1、 RUNX1、 TP53の共変異を有する症例では、 移植を検討すべきである。
まとめ
MDSの治療戦略は、 IPSS-Mによる精緻なリスク層別化と分子プロファイルに基づく個別化の時代に入った。 現在、 日本でも造血器腫瘍パネル検査が保険適用となり、 実臨床での活用が進んでいる。 移植適応や介入時期に迷う症例では、 本推奨を参考に、 患者の価値観を踏まえた適切な判断を行いたい。
出典
関連コンテンツ
🔢 関連ツール
KPS (Karnofsky Performance Scale)
📖 造血器腫瘍遺伝子パネル検査
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。