栄養療法マニュアル
1年前
【栄養療法】経静脈栄養の減量・中止
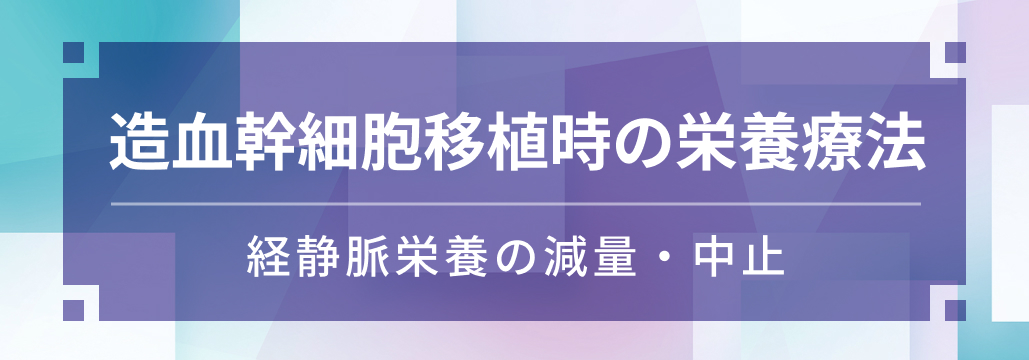
本コンテンツは造血幹細胞移植時の栄養療法について、 専門医の視点からわかりやすい解説を行う企画です。 是非とも臨床の参考としていただければ幸いです。
解説医師
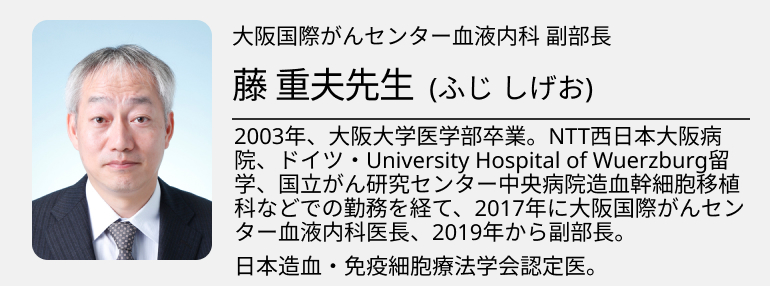
ポイント
経口からのカロリーおよび水分量の摂取量を確認してから経静脈栄養を減量・中止する。
経口摂取増加に伴う輸液調整
生着後経口摂取が増加してきた場合には、 1.0×BEEを最低限の基準として輸液からの投与カロリーを漸減していくことになる。 ただし、 高カロリー輸液投与時には食欲が出にくいとの訴えも時にあるため、 経口摂取カロリーが目標まで改善しない場合には日中の輸液を減らすことや夜間のみに輸液を行うようにするなどの対処も良いかもしれない。 ただ、 実際には移植後には輸液をやめても食欲が良くなることはあまり経験されない。
TPN中止の判断基準
Thomasでは必要エネルギーの30%程度を摂取できていれば全静脈栄養 (TPN) を中止して退院させるのも妥当であるとの記載があるが、 アメリカでは外来でも連日静脈栄養 (PN) を継続できる医療環境であることを理解する必要がある¹⁾²⁾。
PNと水分輸液の比較
Charuhasらが同種移植後目標 (1.3×BEE) の<70%の経口摂取しかできていない例を退院させた時にPNを用いる群 (n=128) と水分のみ輸液で投与する群 (n=130) に無作為化したところ、 水分のみを投与した方が経口摂取の回復が早かったとしているが、 水分のみ投与した群では1ヵ月で平均5%程度の体重減少があり低栄養のリスクが高く栄養管理としては問題と考えられる³⁾。
栄養補助食品等の活用
経口摂取の維持には第一回の「総投与カロリー」の項でも記載したとおり、 栄養補助食品等も使うことも重要であり、 退院前には経口摂取が少ない場合の対処法の指導も必要である。
輸液漸減時の注意点
造血幹細胞移植後に輸液を漸減していく場合にカロリー以外に注意が必要なのは水分量が十分確保されているか確認することである。
免疫抑制剤投与中に飲水が乏しく補液も少ないと腎機能障害の原因となる。 そのため、 カロリーと水分量どちらも目標量を保ちつつ漸減していく必要がある。 輸液を減らしていく段階では体重の減少がないかを確認していくことが重要である。
参考文献
- Nutrition Support of the Hematopoietic Cell Transplant Recipient. Thomas' Hematopoietic Cell Transplantation. Wiley-Blackwell (2009). p. 1551-69.
- Parenteral nutrition in marrow transplant recipients after discharge from the hospital. Exp Hematol (1983) 11(10):974-81. Epub 1983/11/01. PubMed PMID: 6420178.
- A double-blind randomized trial comparing outpatient parenteral nutrition with intravenous hydration: effect on resumption of oral intake after marrow transplantation. JPEN J Parenter Enteral Nutr (1997) 21(3):157-61. PubMed PMID: 9168368.
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。