メイヨークリニック感染症科 松尾貴公
7ヶ月前
【1分間で学べる】アンガーマネジメント②:怒りの発生メカニズム
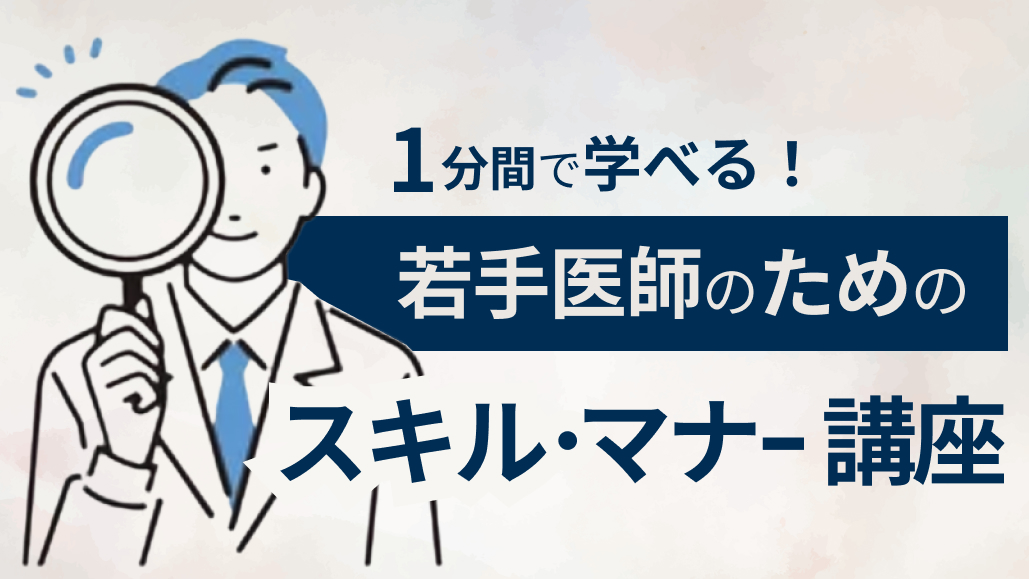
メイヨークリニック感染症科 松尾貴公先生による連載です。 前回は 「アンガーマネジメントが必要な3つの理由」 を紹介しました。 今回は 「怒りの発生メカニズム」 を解説します。
「怒りの感情」 の背後にあるものを知る
Take home message
- 怒りは価値観や期待と現実のズレから生じる感情である。 そのメカニズムを理解することが、 効果的な対処の第一歩となる。
医療現場では、 忙しい業務や多職種の連携、 患者さんとのコミュニケーションの中で怒りを感じる場面が少なくありません。 この怒りをうまくコントロールできるかどうかで、 医師としての成長や働きやすさが大きく変わります。
前回は 「アンガーマネジメントが必要な3つの理由」 を紹介しました。 今回は、 「怒りの発生メカニズム」 について解説します。
「怒りの発生メカニズム」 とは
「怒り」 は外部からの刺激に対して瞬間的に生じる防衛的な感情であり、 自分の身を守るために人間だけではなく動物に備わっている基本的な反応です。
怒りの大きな原因のひとつは、 私たちが持つ 「価値観」 や 「期待」 が現実と異なるときに生じる 「ギャップ」 です。 まずはこの怒りの発生メカニズムを理解することが、 怒りをコントロールする第一歩です。
「怒りが発生する状況」を知る
若手医師で特に多くみられると考えられる、 怒りが発生する状況例を3つ挙げます。
1.患者や家族とのコミュニケーション
患者さんに治療方針を説明した際、 「この治療を受けたくない」 と拒否された場合、 「患者さんは医師のアドバイスに従うべき」 という期待がズレたことで怒りが湧くことがあります。
2.多職種間の連携ミス
例えば、 皆さんが夜間の当直中に看護師さんが患者さんの処方内容の確認で電話をかけてきたとします。 あなたは 「処方内容の確認は日中に行うべき、 何でこんな時間に電話をかけてくるんだ」 と怒りの感情を抱くかもしれません。
3.上司や同僚からの厳しい指摘
研修医として一生懸命に業務に取り組んだにもかかわらず、 上司から指摘を受けたとき、 「努力は評価されるべき」 という考えが怒りにつながることがあります。
このような場面では、 「怒りの感情そのもの」 が問題なのではなく、 「怒りの背後にある価値観や期待」 に気付くことが重要です。
怒りの軽減には 「べき」 を見直す
若手医師として多忙な日々を送る中で、 怒りを減らすためには、 自分の中にある 「べき」 という固定観念を意識し、 それを柔軟に見直すことが効果的です。
また、 あなたにとって当たり前のことでも、 他の人にとっては特殊なことかもしれません。 価値観の柔軟性を持つことも重要です。
特に医療現場では、 怒りの感情が患者さんに対しての医療の質を低下させてしまう原因になることがあるため、 相手の背景や状況を理解しようとする姿勢が重要です。
次回は、 怒りを具体的に和らげるための実践的なテクニックをご紹介します。 医療現場で役立つアプローチを学びながら、 冷静かつ柔軟に対応できる医師を目指しましょう。
連載バックナンバー
第11回 : クレーム対応のコツ① 知っておきたい2つのギャップ
第12回 : クレーム対応のコツ② 円滑に進めるための4つのポイント
第13回 : クレーム対応のコツ③ 実践で活用できる4つのフレーズ
第20回 : アンガーマネジメント① : 必要な3つの理由
松尾先生執筆の最新書籍はこちら!
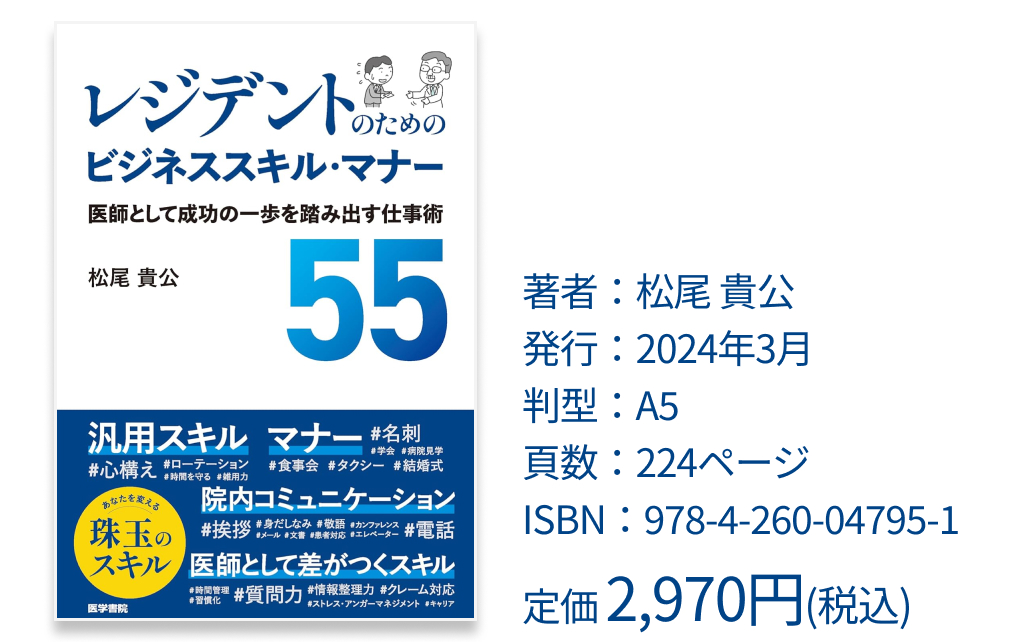
レジデントのためのビジネススキル・マナー
医師として成功の一歩を踏み出す仕事術55
本書では自分が失敗から学んできた社会人としての院内・院外で必要なマナーや、 医師としての心得、 自己成長を成し遂げていくために必要な仕事術を解説していきます。 特に若手医師の皆さんにこれらを少しでも早い段階で共有することにより、 医師としてのキャリアを成功させるためのお手伝いが少しでもできれば幸いです。
「1分間感染症コンサルト」のアカウントはこちら!
X (旧twitter) : @1min_ID_consult
X (英語版) : @1min_IDconsult
Youtube : @1min_ID_consult
Instagram : @1min_ID_consult
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。