栄養療法マニュアル
2年前
【栄養療法】経静脈栄養開始のタイミング
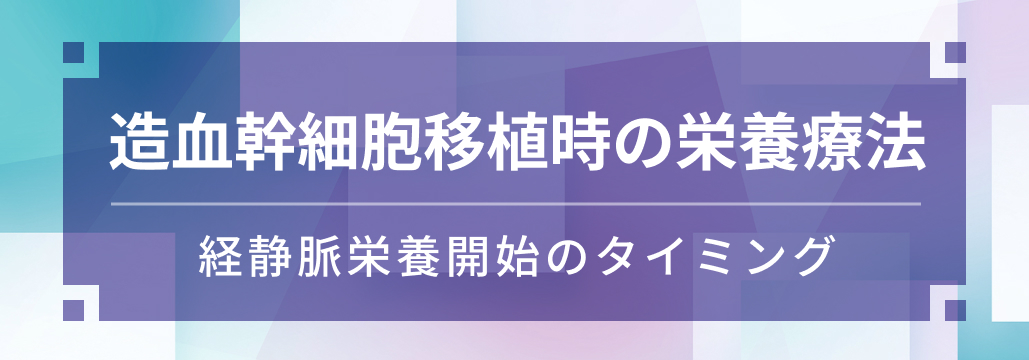
本コンテンツは造血幹細胞移植時の栄養療法について、 専門医の視点からわかりやすい解説を行う企画です。 是非とも臨床の参考としていただければ幸いです。
解説医師

ポイント
- 経静脈栄養は前処置開始時から目標総投与カロリーを維持するように投与する。
- 経口摂取が目標を下回った場合には栄養不良の症状が出現する前から経静脈的な栄養補充を行う。
- 経口摂取と併せ、 1.0×BEEは最低限維持するように末梢静脈栄養 (partial parenteral nutrition:PPN) も積極的に用いる。
栄養療法における経口摂取の重要性
栄養療法において重要なのは経口摂取を可能な限り保つことである。 ICUにおいても経腸栄養が経静脈栄養よりも推奨されている¹⁾。 EFFORT試験においても補助食品的なもので経口摂取を増やすことの意義が示されている²⁾。 EFFORT試験においては個別化栄養サポートを行った群で全死亡イベントが減少したが、栄養サポートの内容としては経口補助食品の工夫が結果として9割の方に行われていた。こういった経口栄養補助食品の工夫を管理栄養士とも相談しつつ最適化することが重要である。
欧州静脈経腸栄養学会 (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism:ESPEN) のガイドラインでも、 「Systematic “between-meals snacks” shall be offered and consumed to reach nutritional requirements as a standard hospital food service, and prevent night fasting」と、 間食等を勧めることが明記されている³⁾⁴⁾。
経口摂取により腸管の状態が保たれることも期待される。 これらのことから、 ゼリーや飲料なども含めて食事内容を適宜変更しながら、 出来る限り経口からの栄養摂取を保つことが重要である⁵⁾。
造血幹細胞移植後の栄養戦略
造血幹細胞移植後は粘膜障害に伴い栄養の吸収が低下することが予想され、 目標総投与カロリーに達さない場合も多い。 したがって、 投与カロリーが不足する際は経腸栄養・経静脈栄養を検討する。 現時点では移植後に経腸栄養を行う施設は限られているが、 現在進行中の試験の結果なども出てくると方針が変わってくる可能性はある。
PPNによる栄養管理
造血幹細胞移植の場合には、 入室時に経口摂取が少ない状態のICUとは異なり、 移植治療中に経口摂取が徐々に低下していくパターンを取ることが多いため、 経口摂取の減り具合を見ながらではあるがPPNから開始し、 徐々に漸増していくのが良い。 PPNに伴う副作用は限定的と考えられる。 長期間となると相当なカロリーを補充することが可能であり、 これにより累積でのエネルギーバランスがマイナスになる期間を減らすことができる⁶⁾。
ESPENのガイドライン (non-surgical oncology) ではPPNについて、 「目標の60%未満の栄養摂取が10日以上続くと予想される場合」といった記載があるが、 移植の領域では60%というのは若干低すぎるように感じている。 期間に関しても同種移植後は10日以上続くのが通常であり、 基本的には経口摂取が不足してきたらすぐにビーフリードなどPPNや中心静脈カテーテルがあればエルネオパを減量した量からでも開始するのが望ましい。
また、 PPNを用いている間に血糖管理に必要なインスリンの必要量を探っておくと、 中心静脈栄養 (total parenteral nutrition:TPN) となった時点でも安定した血糖値を維持しやすい。
TPNへの移行と注意点
長期にわたり経口摂取が不足した状態が続いた後にTPNを開始する際は、リフィーディング症候群のリスクになる程でなくても、 まずはPPNから開始し、 電解質、 血糖、 中性脂肪などに問題ないことを確認しつつ増量していくことが勧められる。
参考文献
- ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr 2019 ; 38 (Issue 1) :48-79. PMID: 30348463
- Individualised nutritional support in medical inpatients at nutritional risk: a randomised clinical trial.Lancet 2019 ; 393 (Issue 10188) : 2312-2321. PMID: 31030981
- ESPEN guideline on hospital nutrition
- ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer
- Individualised nutritional support in medical inpatients at nutritional risk: a randomised clinical trial. Lancet 2019 ; 393 (Issue 10188) : 2312-2321. PMID: 31030981
- Optimizing energy and protein balance in the ICU. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2013; 16(2) :194-201 PMID : 23334173
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。