HOKUTO編集部
5ヶ月前
【神経内分泌新生物】ソマトスタチンアナログの要点
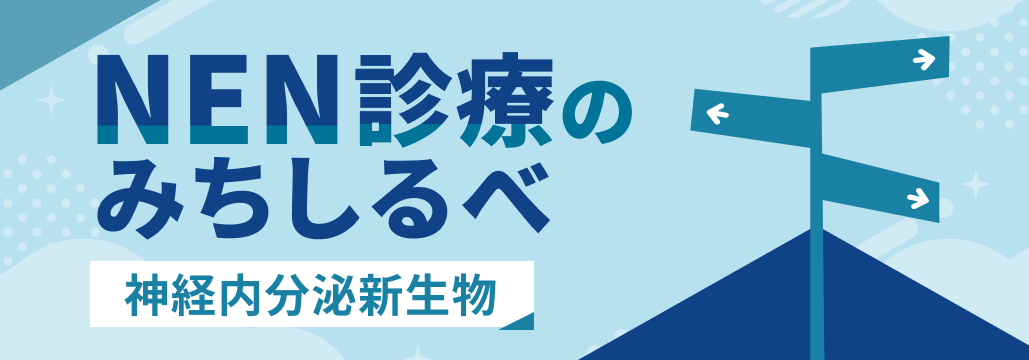
神経内分泌腫瘍 (NET) は、 ソマトスタチン受容体 (somatostatin receptor : SSTR) を高頻度に発現しており、 特にSSTR2およびSSTR5の発現が多いことが知られている。 そのため、 SSTR2およびSSTR5を標的としたソマトスタチンアナログの治療開発が進められてきた。 日本で使用可能なソマトスタチンアナログは、 オクトレオチドLARおよびランレオチドである。 両剤はSSTRに結合し、 mTOR経路の抑制を介して抗腫瘍効果を発揮する。 本稿では、 両剤の有効性および安全性について解説する (第2回解説医師 : 国立がん研究センター中央病院 頭頸部・食道内科 山本駿先生、 解説薬剤師 : 国立がん研究センター中央病院 薬剤部 田内淳子先生)。
解説医師・薬剤師
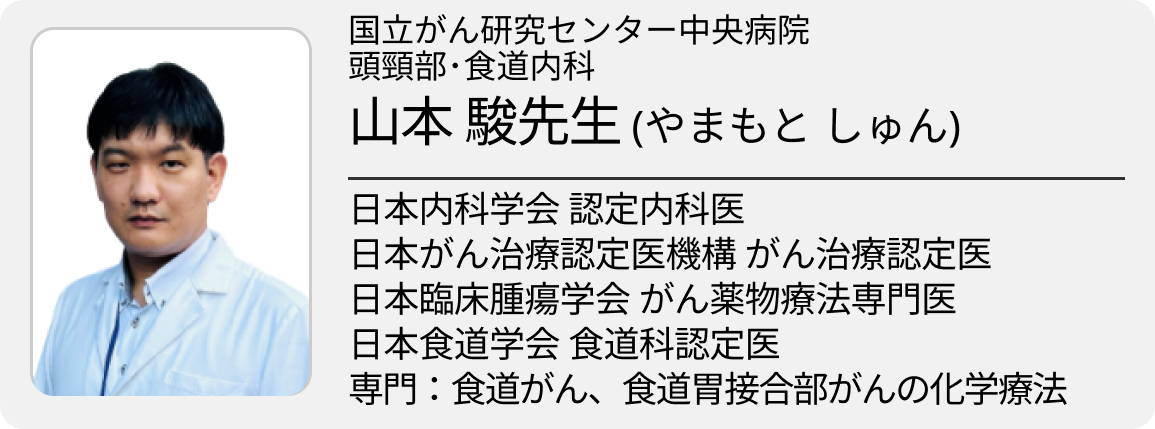
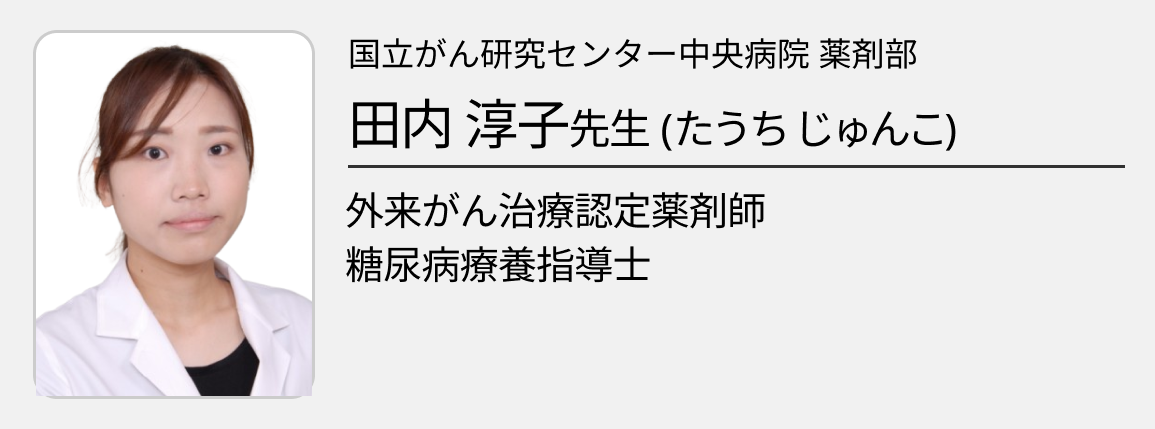
オクトレオチドLAR
オクトレオチドは、 従来は機能性NETに伴うホルモン過剰症状の緩和を目的として使用されていたが、 抗腫瘍効果も示唆されていた。 第III相無作為化比較試験PROMID¹⁾において、 その有効性および安全性が検証されている。
有効性
PROMID試験は、 中腸原発または原発不明の切除不能高分化NET患者85例を対象に、 オクトレオチドLAR群42例とプラセボ群43例に割り付け、 主要評価項目として無増悪生存期間 (PFS) を比較した。
PFS中央値は、 プラセボ群の6.0ヵ月に対し、 オクトレオチドLAR群では14.3ヵ月と優越性が示された (ハザード比 [HR] 0.34、 95%CI 0.20–0.59)。
またPFSは、 腫瘍の機能性・非機能性、 肝転移量、 クロモグラニンA値、 PS、 年齢、 原発切除歴、 診断からの期間別にサブグループ解析された。 肝転移量50%以上および原発切除歴のない集団では、 HRがそれぞれ0.71、 0.84と、 全体解析に比べ効果がやや小さい傾向を示したものの、 それ以外のサブグループでは一貫して良好な結果が確認された。
全生存期間 (OS) 中央値は、 オクトレオチドLAR群で未到達、 プラセボ群で73.7か月 (HR 0.81、 95%CI 0.30–2.18) であった。
安全性
主な有害事象は、 消化器毒性 (14.3%)、 血液毒性 (11.9%)、 疲労 (19.0%)、 発熱 (19.0%) であった。
治療関連死亡は認められず、 重篤な有害事象は11例 (26.2%) に報告された。 治療中止に至った症例は5例 (11.9%) であった。
消化器毒性 (下痢や鼓腸など) は投与開始から1ヵ月以内に多く発現するため、 治療初期は有害事象のモニタリングを十分に行う必要がある。 また、 胆石症の発生も報告されており、 注意を要する。
製剤と投与のポイント
オクトレオチドLARは用時調製とされており、 懸濁後は速やかに使用する必要がある。
ランレオチド
ランレオチドは、 体内での安定性を高めた徐放性ソマトスタチンアナログ製剤である。 第III相無作為化比較試験CLARINET²⁾において、 その有効性および安全性が検証されている。
有効性
CLARINET試験は、 非機能性かつ切除不能なSSTR陽性G1~G2消化器原発NET患者204例を対象に、 ランレオチド群101例とプラセボ群103例に割り付け、 主要評価項目としてPFSを比較した。
PFS中央値は、 プラセボ群の18.0ヵ月に対し、 ランレオチド群では未到達で優越性が示された (HR 0.47、 95%CI 0.30–0.73)。
またPFSは、 原発部位、 腫瘍グレード、 肝転移量別にサブグループ解析された。 症例数は限られているが、 後腸原発の集団14例ではHRが1.47と、 全体解析と異なり不良な傾向が認められたものの、 それ以外のサブグループでは一貫して良好な結果が示された。
OSは、 両群間で有意差を認めなかった (p=0.88)。
安全性
主な有害事象は、 下痢 (25.7%)、 腹痛 (13.4%)、 胆石症 (9.9%)、 鼓腸 (7.9%)、 注射部位疼痛 (6.9%)、 悪心 (6.9%)、 嘔吐 (6.9%) であった。
重篤な有害事象は3例 (3.0%)、 有害事象による治療中止は3例 (3.0%) であった。
製剤と投与のポイント
ランレオチドはプレフィルドシリンジ製剤であり、 調製を必要とせず、 投与手技が簡便である。
オクトレオチドLARとランレオチドの使い分け
オクトレオチドLARは、 中腸原発NETを対象としたエビデンスが中心である。 一方、 ランレオチドは、 Ki-67 indexが10%未満のNETに限定したエビデンスに基づいている。
両剤は同一の作用機序を有しており、 同等の治療効果が期待できるため、 明確な使い分けはない。 実臨床においては、 薬剤の投与手技や利便性も考慮される。
おわりに
本稿では、 ソマトスタチンアナログ (オクトレオチドLARおよびランレオチド) の有効性と安全性について、 臨床試験結果を基に解説した。 次回は、 NETに対する分子標的薬について概説する。
出典
関連コンテンツ
JCOG1901 (STARTER-NET) 解説
国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科 肱岡範氏
国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科 丸木雄太氏
💊関連薬剤情報
📝レジメン
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。