HOKUTO編集部
10ヶ月前
ASCO GI 2025の注目演題を解説-食道癌・大腸癌・NET-

2025年1月23~25日に米国・サンフランシスコで開催された米国臨床腫瘍学会消化器癌シンポジウム (ASCO GI 2025) にて発表された食道癌・大腸癌・神経内分泌腫瘍(NET)の各注目演題について、 国立がん研究センター中央病院頭頸部・食道内科の山本駿先生に解説いただきました。
(記事内写真 : 山本駿氏提供)
はじめに
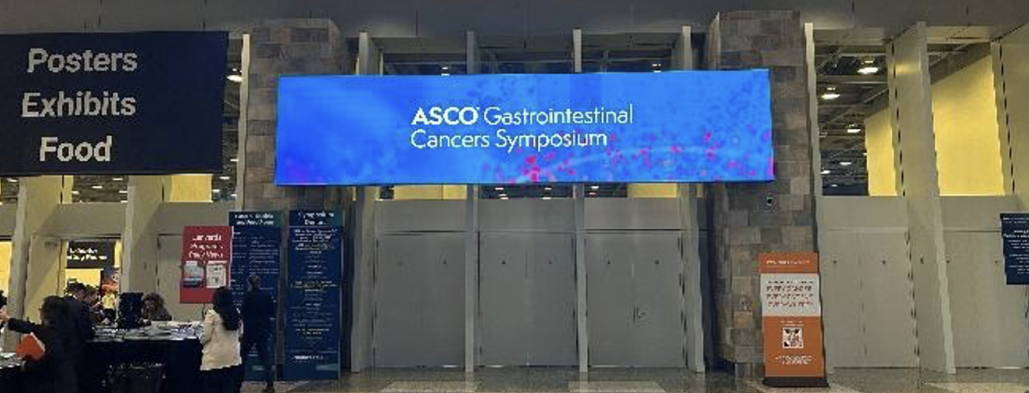
ASCO GI 2025の会場入り口
2025年の年明け早々だが、 米国のサンフランシスコでASCO GI 2025が行われた。 毎年3日間に渡り開催されるASCO GIは、 初日が上部消化管癌、 2日目が肝胆膵癌、 そして最終日が下部消化管癌に領域が別れていることが特徴だ。
今回も昨年同様、 癌種別に解説を行うとともに、 同じ臨床試験の附随解析などは1つにまとめて共有する。
切除可能食道癌
日本において食道癌のうち最多の集団である、 切除可能な局所進行食道扁平上皮癌に対する標準治療は、 JCOG1109試験の結果から、 術前DCF療法と根治切除である。 一方、 欧米ではCROSS試験とCheckMate 577試験の結果から、 術前化学放射線療法+根治切除、 さらに術後病理検査で病理学的完全奏効(pCR)が得られなかった場合は術後ニボルマブ療法が標準治療とされている。
ASCO GI 2025では、 切除可能食道癌の術前治療の最適化を目指し、 抗PD-1抗体sintilimab併用療法を検証する第III相試験SCIENCEの短期成績や、 術前FLOT療法の有効性を検討した第II相試験、 電話フォローアッププログラムによる有害事象 (AE) の重症化予防に関する検討などが報告された。
第Ⅲ相試験SCIENCE
概要
第Ⅲ相試験SCIENCEは、 切除可能な食道扁平上皮癌を対象に、 術前化学放射線療法単独、 術前化学療法+sintilimab併用療法、 術前化学放射線療法+sintilimab併用療法を比較する、 中国で実施された試験である。 主要評価項目はpCR割合と無イベント生存期間 (EFS) が設定され、 今回はpCRの結果が報告された。
試験の結果
患者背景に関してはPSやcStageなど、 両群で概ねバランスが取れていた。 pCR割合は術前化学放射線療法群で47.3%、 術前化学療法+ sintilimab併用療法群で13%、 術前化学放射線療法+sintilimab併用療法群で60%だった。 なお、 術前化学療法+sintilimab群と比較し、 術前化学放射線療法群 (p=0.0005) と術前化学放射線療法+sintilimab群 (p<0.0001) はいずれも有意差を認めた。
Grade 3以上の治療関連有害事象 (TRAE) として、 好中球減少が術前化学放射線療法群16.4%、 術前化学療法+sintilimab併用療法2.2%、 術前化学放射線療法+sintilimab併用群8.9%と報告された。
小活
SCIENCE試験では免疫チェックポイント阻害薬の上乗せで術前化学放射線療法におけるpCRの改善が示唆されたが、 JCOG1109試験ではpCRが良好であっても(特にモダリティが異なる場合)長期成績に与える影響が明らかではなかったことから、 SCIENCE試験の結論はもう1つの主要評価項目であるEFSの結果次第といえるだろう。
※SCIENCE試験の詳細レポートを後日配信予定。
術前FLOT療法の有効性と安全性
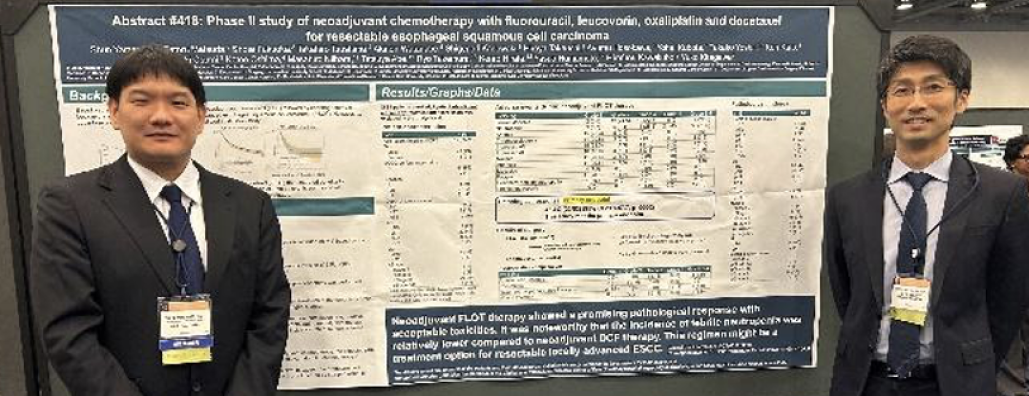
左 : 山本駿氏、 右 : 慶應義塾大学消化器外科 松田諭氏
試験の概要
本試験は術前FLOT療法*の有効性を検討した第Ⅱ相多施設単群試験である。 主要評価項目は日本食道学会の『臨床・病理食道癌取扱い規約第12版』に基づくGrade 2/3と定義された病理学的奏効割合だった。
試験の結果
病理学的奏効割合は43.4%(95%CI 29.8-57.7%)で、 事前に規定した基準(95%CI下限値 : 20%)を上回った。 また原発巣のみのpCR (治療効果の判定基準 : Grade 3)の割合は13.2%で、 Grade 3以上の発熱性好中球減少の発現頻度は1.9%であった。
*フルオロウラシル+ロイコボリン+オキサリプラチン+ドセタキセル
小活
術前FLOT療法はさまざまな可能性を秘めているレジメンである。 今回検討された対象とは異なるが、 シスプラチンが不適な腎機能低下例や心機能低下例においても投与可能であり、 さらに術前DCF療法と近い病理学的治療効果を示していることから、 これらの対象における治療選択肢にもなりうる。 さらに、 免疫チェックポイント阻害薬+FLOT併用も開発されており、 pCR割合は約40%と非常に有望な結果が報告されている。 まずはDCF療法が不適な症例における治療選択肢ではあるものの、 今後どこまで開発が進むのか期待される。
病棟看護師による術前DCF療法中の電話フォローアップの有用性
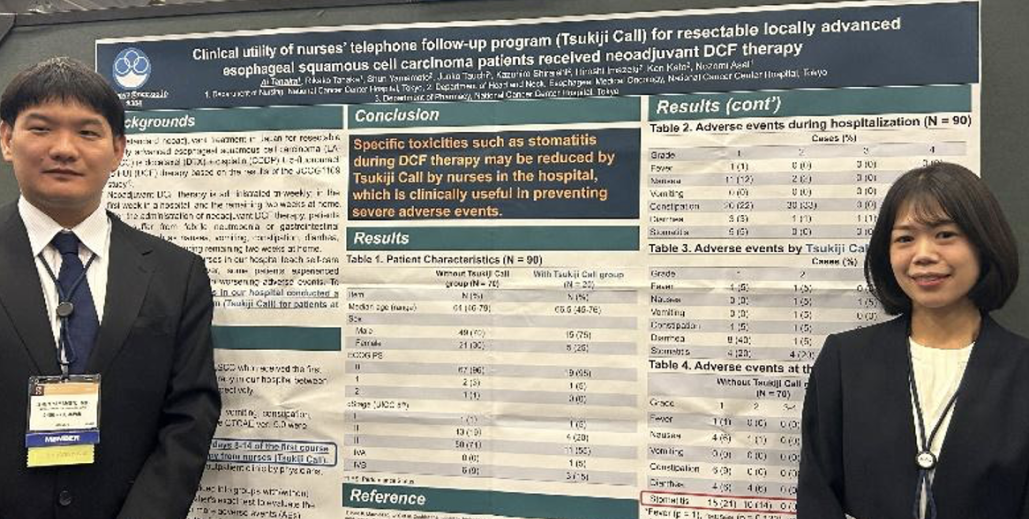
左 : 山本駿氏、 右 : 国がん中央病院 田中愛看護師
試験の概要
こちらの研究は、 術前DCF療法*の8~4日目に、 病棟看護師による電話フォローアップを受ける症例と受けない症例において、 初回外来時のGrade 2以上のAE発現頻度を比較した後ろ向き研究である。
試験の結果
電話フォローアップあり/なし例におけるGrade 2以上のAE発現頻度はそれぞれ発熱: 0% / 0% (p=1)、 嘔気: 10% / 1% (p=0.123)、 嘔吐: 0% / 0% (p=1)、 便秘: 0% / 0% (p=1)、 下痢: 0%/6% (p=0.572)、 口内炎: 0% / 14% (p=0.109) であった。
*ドセタキセル+シスプラチン+5-FU
小活
術前DCF療法のAEとして有名な好中球減少や悪心・嘔吐と同時に、 口内炎も一定の頻度で発生する。 重篤化すると経口摂取不能に至り、 緊急入院を要することがあるため、 早期発見・早期治療が求められる。 今回の結果では、 病棟看護師の電話フォローアッププログラムにより口内炎の重症化予防が得られている印象であり、 今後は症例数を増やしてさらなる検討が必要である。
第Ⅲ相試験JCOG1109の関連研究
第Ⅲ相試験JCOG1109は本邦の食道扁平上皮癌の術前治療を変えた臨床試験であり、 ASCO GI 2025では、 同試験の附随研究が3件報告されていた。 各試験の概要は以下の通りである。
①術前療法~手術までの待機時間が与える影響
1つ目は術前化学療法終了後から手術までの待機時間が有効性や安全性に与える研究で、 待機期間を4分位に基づいてサブグループに分類し、 同一レジメン内で生存期間解析を用いて比較したものの、 いずれの検討においても有意差は認めなかった。 しかし術前化学放射線療法に関しては、 早期に行うことで手術関連合併症(Q1/Q4: 24%/51%)や吻合部漏出(Q1/Q4: 6%/18%)の頻度を下げられる可能性が示唆された。
②術後合併症と予後の関連
2つ目は術後合併症と予後の関連を評価した研究で、 Grade 2以上の術後合併症の有無と無増悪生存期間 (PFS)、 全生存期間 (OS) との関連について、 生存時間解析を用いて3群間 (CF群、 DCF群、 CF-RT群) で比較したが、 いずれの術前療法群においても有意差は認めなかった。
また開胸手術と胸腔鏡手術を比較した場合、 どのモダリティにおいても、 術後合併症の有無別でOSのハザード比 (HR) が胸腔鏡手術で低い傾向があり(CF群のHR 開胸/胸腔鏡: 1.557/0.802、 DCF群のHR 開胸/胸腔鏡: 1.151/0.703、 CF-RT群のHR 開胸/胸腔鏡: 1.548/1.186)、 胸腔鏡手術の導入により術後合併症の予後に与える影響を低減できる可能性が考えられた。
③非癌関連死亡
3つ目は非癌関連死に関する研究である。 これは術前化学放射線療法群で長期的に死亡イベントが発生していたことが背景にあり、 詳細を明らかにする目的で検証された。
試験の結果、 化学放射線療法群では他群に比べ、 非癌関連死のうち呼吸器関連死が占める頻度が32%高い傾向にあった。 また多変量解析では、 非癌関連死と有意に関連する因子として、 高齢(HR 3.243[95%CI 1.897-5.852])、 PS 1(HR 0.279[同 0.090-0.871])、 高CRP値(HR 2.238[同 1.033-4.955])が抽出された。
進行期食道癌
切除不能な進行食道扁平上皮癌に対する初回標準治療は、 KEYNOTE-590試験とCheckMate 648試験の結果から、 シスプラチン+5-FU (CF) +ペムブロリズマブ併用療法、 CF+ニボルマブ併用療法、 および抗PD-1抗体ニボルマブ+抗CTLA-4抗体イピリムマブ (Nivo+Ipi) 併用療法と確立されている。
しかし治療効果はOS中央値が約12ヵ月といまだに限定的であり、 さらなる予後改善を目指して、 標準治療にFGFR阻害剤の上乗せを検討したTARPS試験が行われている。
第Ⅰ相試験TARPS
試験の概要
第Ⅰ相試験TARPSは、 未治療の切除不能な進行食道扁平上皮癌を対象に、 CF療法に抗PD-1抗体zimberelimabおよびFGFR阻害薬TAS120を上乗せした場合の安全性と有効性が検討された。 主要評価項目は用量制限毒性(DLT)だった。
試験の結果
DLTは、 最初に評価された3例中1例も認めなかった。 登録症例における高頻度に発現したAEは、 高リン血症 (81.4%)、 下痢 (67.4%)、 嘔気 (62.8%)、 食欲不振 (62.8%)であった。 また、 客観的奏効割合 (ORR) は70.7%、 確定した奏効割合は58.5%、 PFS中央値は4.9ヵ月であった。
小活
TARPS試験はTAS120+zimberelimab併用療法を基軸にした治験であり、 今回の食道癌の1次治療としては安全性が維持され、 短期的には高い抗腫瘍効果を認めた。 PFSが既存の1次治療とあまり変わらない点は気になるが、 OSの評価も必要だと考える。
切除不能大腸癌
切除不能な進行大腸癌に対する初回薬物療法は現在、 遺伝子変異に基づいて行われるのが一般的である。 その中でもMSI-high/dMMR集団では免疫チェックポイント阻害薬の開発が、 BRAF V600E変異を有する集団においてはBRAF阻害薬の開発が進められている。
第Ⅲ相試験CheckMate 8HW
試験の概要
第Ⅲ相試験CheckMate 8HWは、 MSI-high/dMMRを有する切除不能な進行大腸癌を対象に、 Nivo +Ipi併用療法、 ニボルマブ単剤療法をそれぞれ試験治療群として、 化学療法と比較した国際共同無作為化比較試験である。 主要評価項目は①Nivo+Ipi併用療法 vs 化学療法のPFS、 および②Nivo+Ipi併用療法 vs Nivo単剤療法のPFSだった。 昨年は①Nivo+Ipi併用療法 vs化学療法の2群に関するPFSと安全性が報告され、 今年は②Nivo+Ipi併用療法 vs Nivo単剤療法の2群に関するPFSと安全性が報告された。
試験の結果
患者背景は年齢や性別、 PS、 PD-L1発現、 遺伝子異常等に関して両群でバランスが取れていた。
中央判定でMSI-high/dMMRと判定された集団のPFS中央値は、 Nivo+Ipi群で未到達、 Nivo群で39.3ヵ月と、 Nivo+Ipi群の優越性が証明された(HR 0.62[95%CI 0.48-0.81])。 全体集団での解析も同様の結果であった(HR 0.64[同 0.52-0.79])。 また奏効割合に関しても、 Nivo+Ipi群のNivo群に対する優越性が証明された(71% vs 58%、 p=0.0011)。
安全性に関して、 Grade 3-4のTRAE発現率はそれぞれ22% vs 14%だった。 なおNivo+Ipi群では、 甲状腺機能低下症や亢進症、 副腎不全といった内分泌系の有害事象の頻度が高い傾向にあった。
小活
既に昨年のASCO GI 2024において、 化学療法と比較した1次治療としてのNivo+Ipiの有効性は報告されており、 残るは実臨床への応用が期待されるのみである。 今回の報告で重要な点は、 抗PD-1抗体単剤よりも治療効果を示したことであろう。 実際に複数の治療選択肢がある中で、 Nivo+Ipi併用療法の優位性をより強固にしたと考えられる。
※CheckMate 8HW試験の詳細レポートを後日配信予定。
第Ⅲ相試験BREAKWATER
試験の概要
第Ⅲ相試験BREAKWATERは、 BRAF V600E変異を有する未治療の切除不能進行大腸癌を対象に、 BRAF阻害薬エンコラフェニブ+抗EGFR抗体セツキシマブ併用(EC)療法とEC+mFOLFOX6*併用療法を試験治療として、 標準治療と比較した国際共同試験である。
主要評価項目は、 EC+mFOLFOX6併用療法 vs 標準治療のPFSと奏効割合だった。 副次評価項目にはOSが設定された。 今回はEC+mFOLFOX6併用療法 vs 標準治療における奏効割合およびOSが報告された。
試験の結果
患者背景は年齢や性別、 PS、 原発部位等に関して両群で概ねバランスが取れていた。 奏効割合は、 EC+mFOLFOX6群60.9%、 標準治療群40.0%と、 試験治療群の優越性が証明された(p=0.0008)。
なお中間解析でのOS中央値はEC+mFOLFOX6群で未到達、 標準治療群で14.6ヵ月と報告され、 優越性は認めなかったものの良好な傾向であった(HR 0.47[95%CI 0.318-0.691] )。 またGrade 3/4のTRAE発現割合はEC+mFOLFOX6群69.7%、 標準治療群53.9%だった。
*オキサリプラチン+フルオロウラシル+レボホリナート
小括
主要評価項目の1つである奏効割合が達成し、 OSも良好な傾向を示したこともあり、 米食品医薬品局 (FDA) は2024年12月に本治療を早期承認した。 日本での承認がどうなるかが注目される。
※BREAKWATER試験の詳細レポートを後日配信予定。
切除不能神経内分泌腫瘍
神経内分泌腫瘍(NET)は希少癌に分類される疾患で、 切除不能病期であっても一般に予後が緩徐である一方、 Ki-67 ラベリングインデックス (LI) が高値の症例やびまん性の肝転移を有する症例においては予後不良とされている。 同対象において過去の臨床試験でもエビデンスは乏しく、 RADIANT-3/4試験で含まれていたエベロリムスが用いられることが多い。
そのような中で、 エベロリムス+持続性ソマトスタチンアナログ製剤ランレオチド併用療法も少数例の報告は散見されていたが、 確固たるエビデンスは存在しなかった。
第Ⅲ相試験JCOG1901(STARTER-NET)
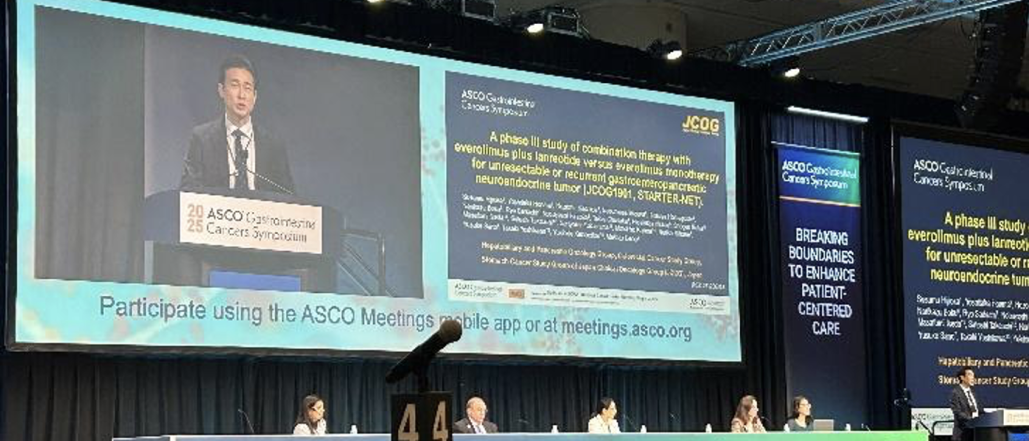
メインホールでJCOG1901試験の結果を発表する国立がん研究センター中央病院医長 肱岡範氏
試験の概要
第Ⅲ相試験JCOG1901(STARTER-NET)は、 未治療の切除不能な消化器原発NET G1/G2で、 予後不良因子(Ki-67 LI高値やびまん性の肝転移)を有する症例を対象に、 エベロリムス単剤療法とエベロリムス+ランレオチド併用療法を直接比較した無作為化比較試験である。 主要評価項目はPFSだった。
試験の結果
患者背景は年齢や性別、 原発部位、 Ki-67 LIは両群間で概ねバランスが取れていた。 今回は中間解析段階でのPFS中央値が示され、 同値はエベロリムス群11.5ヵ月に対し併用療法群29.7ヵ月と、 併用療法群の優越性が証明された(HR 0.38 [99.91%CI 0.15-0.96] )。
なおGrade 3以上のTRAE発現割合は、 エベロリムス群14.9%、 併用療法群35.6%であり、 なかでも併用療法群では高血糖(9.1%)、 口内炎(8.0%)の頻度が高い傾向にあった。 また、 本試験は中間解析の段階でデータモニタリング委員会より中止が勧告され、 最終的に有効中止となった。
小活
今まで消化器原発NETの治療薬は企業主導の治験による検討が多く、 その疾患特性もあり、 初回治療に限定したエビデンスはNETTER-2試験を除き、 非常に乏しい状況であった。 そのような中、 研究者主導で純粋な初回治療例を対象に本試験が行われ、 エベロリムス+ランレオチド併用療法を新たな標準治療として確立した意義は非常に大きい。 今後はNETの中でも予後不良因子を有する症例においては、 本レジメンが標準治療となりうると考えられる。
また学術的な部分では、 NETTER-2試験と一部症例が重なることが考えられ、 その場合どちらを優先して行うべきか、 今後の知見の集積が期待される。
※JCOG1901試験の詳細レポートを後日配信予定。
最後に
今回のASCO GIも興味深いデータが数多く報告された。 若手の先生で少しでも消化器癌に興味があれば、 是非一度は足を運んでいただきたい。
解説医師
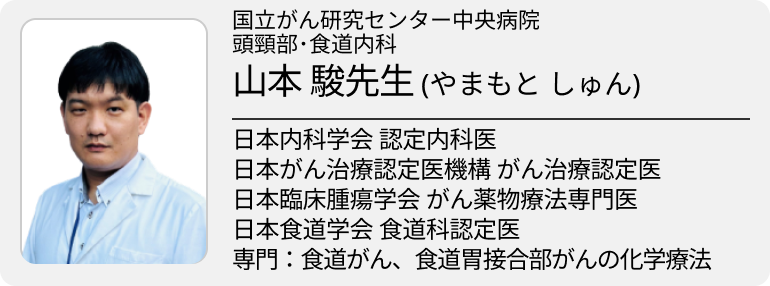
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。