HOKUTO編集部
8ヶ月前
【けいれん】レジデントからできる治療以外の発作時対応 (音成秀一郎先生)
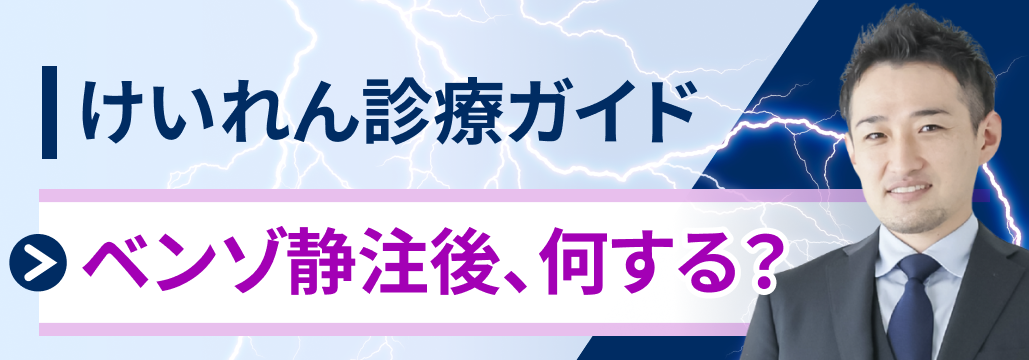
広島大学病院 脳神経内科の音成 秀一郎先生による連載 「けいれん診療ガイド」 です。 第4回は"レジデントからできる治療以外の発作時対応" について解説いただきます。
「先生、 けいれんしています!」
てんかんはコモンな全世代の慢性脳疾患
病棟看護師より 「先生、 ○○さんがけいれんしています!」 と連絡があったら 「え?てんかんの既往はなかったはずなのに、 どうして?」 と思いながらも冷静に対応しなければなりません。 ちなみに、 てんかんは100人に1人のコモンな脳の慢性疾患なので、 自分の担当患者に実はてんかんがあったということがあっても不思議ではないのです。
冷静に患者の状況を見極めましょう
いずれにしても初期対応が遅れてはいけませんので、 発作が続いているようであれば人員を確保しつつ、 点滴、 採血、 ジアゼパムなどの初期対応セットの準備を指示しつつ患者の状況を見極めましょう。 危険なバイタルサインであれば院内救急コールが必要です。 見た目の激しい 「けいれん」 に目を取られて、 実はVFだった、 だと大変です。
ジアゼパム投与をしたら?
最後まで 「気道確保を怠らない」
その後の初期対応、 ジアゼパムの静注で速やかに発作が止まったとします。 ここで、 ベッドサイドにいるレジデントには注意点があります。 それは発作が止まったことで安心せずに、 最後まで気道確保を怠らないことです。
ジアゼパム投与で速やかに鎮痙したとしても、 薬剤により鎮静・筋弛緩作用が生じるため、 舌根沈下しやすいです。 またけいれん発作では、 過剰分泌した流涎物 (いわゆる、 口から泡をふく) が口腔内にあるため、 これによる気道閉塞のリスクがあります。
速やかに 「側臥位」 へとポジショニング
そのため何をしなければいけないかというと、 鎮痙後にはバイタルサインの再確認に加えて、 速やかに側臥位へとポジショニングしましょう。 また痙攣発作の原因が実は脳出血だったらどうでしょうか? 頭蓋内圧の亢進でそのうち嘔吐してしまうこともあるでしょう。 仰臥位のままで嘔吐してしまうと大変危険です。
バイタル再検や、 吸引等の処置を行う
そのためレジデントの皆さんは看護師とともに、 患者を側臥位にさせて、 同時にバイタルサインの再検や、 吸引等の処置を行うと良いでしょう。 これにより発作後の誤嚥性肺炎の予防にもつながりますので、 コスパの良い重要な対応といえます。
口から泡をふくのはなぜ?
発作が中枢の自律神経系を巻き込むから
ところで、 なぜてんかん発作では 「口から泡をふく」 のでしょうか?これは決して苦しいからではありません。 答えとしては、 発作が中枢の自律神経系を巻き込むからです。
自律神経の中枢は大脳辺縁系や島回、 前部帯状回などに含まれます。 これらの領域がてんかん発作に巻き込まれると、 自律神経系が活性化されますので、 脈拍上昇 (頻脈) や血圧上昇が引き起こされます。 そして自律神経系の刺激により分泌亢進も伴いますので、 結果として口腔内泡沫の増加や、 著名な発汗がみられるのです。
発作時の安全確保
発作を手で押さえるのは "御法度"
患者が激しく痙攣していると発作を手で押さえたくなるかもしれませんが、 それは御法度です。 無理に押さえつけると脱臼などの外傷を負ってしまうかもしれませんし、 医療従事者が怪我を負う可能性だってあり危険です。 また昔は痙攣発作時の舌咬傷を防ぐなどのため 「口にタオルを入れて噛ませる」 などの対応をしていた時代がありますが、 気道閉塞のリスクがあるため推奨されません。 発作を力技で強引に止める必要はないのです。
まず発作が起きている状況の安全を確保
それよりも、 ベッド柵を上げることで患者の転落を防ぐなど、 まずはその発作が起きている状況の安全確保を優先します。 他には、 病室でけいれんした場合であれば枕元などに患者のスマホや眼鏡がおいてある可能性があります。 これらが痙攣で破損する可能性もあるので、 安全な場所に移動させましょう。 そして痙攣している手足がベッド柵で打撲しないようにクッションを挟むなどの対応も大事です。
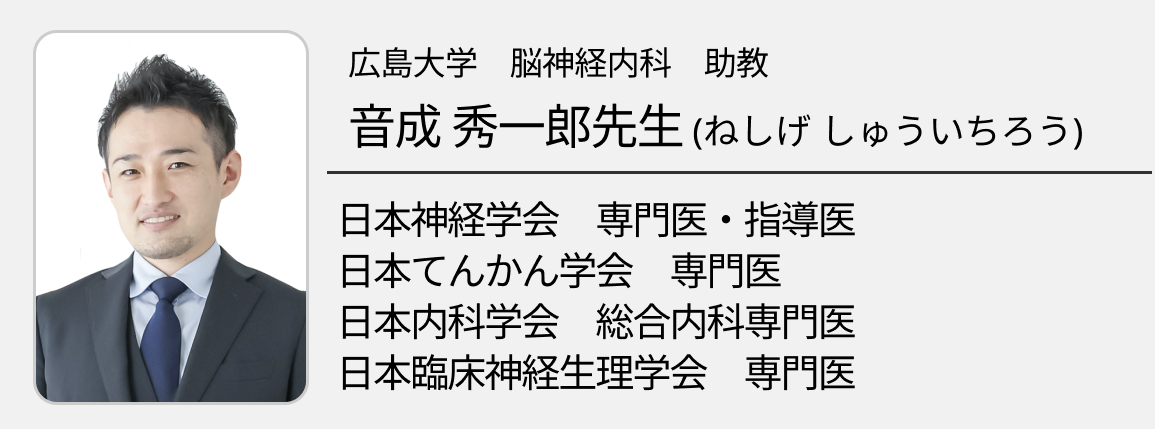
2008年に大分大学医学部を卒業。 広島大学脳神経内科に入局後は救急系の関連病院で研修し2015年に京都大学大学院 (臨床神経学) へ国内留学。 同てんかん ・ 運動異常生理学講座の池田昭夫教授の指導のもと、 てんかんと脳波の臨床研究に従事し、 JES Prize, Excellent Presentation Award, JUHN AND MARY WADA Award, Hans Berger Awardなど日本てんかん学会の受賞歴あり。 福島県立医科大学ふたば総合医療センターでの復興医療支援を経て2019年4月から広島大学脳神経内科助教、 現在に至る。
X (旧Twitter) : https://x.com/neshige_s
noteでの連載 : https://note.com/nec283
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。