寄稿ライター
6ヶ月前
説明義務違反と損害賠償

医療訴訟が珍しくなくなった今、 医師は法律と無関係ではいられない。 連載 「臨床医が知っておくべき法律問題」 12回目のテーマは 「説明義務違反と損害賠償」。
裁判所が 「創造」 した説明義務
医療訴訟では、 「説明義務違反」 がよく問題にされる。 医師が手術などの説明をし、 インフォームドコンセントの書面を交付して患者に署名してもらうことが一般的だが、 具体的な内容が法令で決まっているわけではない。
ただ、 裁判所が医師の説明義務なるものを創造し、 規範としているので、 実質的に法律のような効果を生んでいる。 最高裁判決 (平成13年11月27日) では、 「医師は、 患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、 診療契約に基づき、 特別の事情のない限り、 患者に対し、 当該疾患の診断 (病名と症状)、 実施予定の手術の内容、 手術に付随する危険性、 他に選択可能な治療方法があれば、 その内容と利害得失、 予後などについて説明すべき義務がある」 としている。

これを受け、 医療法第1条の4は 「医師などは、 医療を受ける者に対し、 良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない」 と努力義務として一般的抽象的な説明義務を規定している。
死亡と因果関係がなくても賠償責任を負うのか?
説明義務違反は、 往々にして手術侵襲の結果死亡したようなケースで主張される。 事前に聞いていればこんな危ない手術は受けなかったという主張は訴訟ではよくされるが、 説明義務違反と死亡との間で因果関係が認められないならば、 死亡に起因する全損害を賠償させられることはない。
ただ、 いずれにせよ手術を受けたであろう事案でも、 説明義務違反により患者が被った精神的苦痛に対する慰謝料の賠償が認められる可能性がある。 説明義務は、 手術のように本来医師側が給付すべき診療契約上の義務ではないものの、 付随義務として認められるからである。

写真はイメージです
つまり、 仮に手術を受けざるを得ない状況にあったとしても、 説明義務違反があれば、 医療者側が慰謝料の賠償責任を負うことが裁判例では多かった。
画期的な判決
ところが、 最近私が担当した訴訟事件で、 画期的な判決が出た。 説明の時期が遅い (手術直前) という説明義務違反はあるものの、 結局は手術を受けざるを得ない状況だったため、 賠償金がゼロとなったのだ (大阪高裁令和5年11月17日判決)。
もちろん患者側は、 「説明義務違反はあるのだから、 精神的苦痛に対して慰謝料が認められるべきだ」 と最高裁へ上告受理申立てを行った。 これに対して私は、 最高裁に対して、 10p以上の反論書を提出した (これは控訴審での勝訴側としては、 あまり例のない訴訟行為である)。
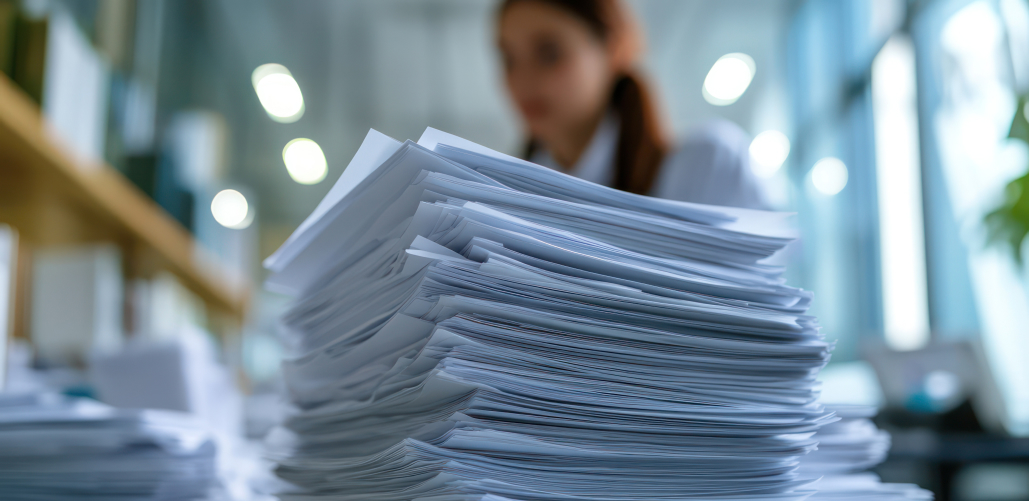
写真はイメージです
詳細は割愛するが、 「主たる義務である診療行為については、 最高裁は悪い結果との因果関係がない場合は、 診療行為がよほどひどい場合以外は賠償を認めない。 一方、 付随義務である説明義務の場合に、 義務違反があれば全部賠償せよというのはおかしいのでは」 という問題提起である。
最高裁がこの見解をそのまま採用したのか不明ではあるが、 最高裁は令和6年5月24日決定によって上告受理申立てを却下し、 医療側の勝訴が確定した。
説明義務違反があっても、 患者の判断結果が変わらない場合には賠償が認められないという貴重な裁判例である。 裁判で説明義務を主張されている医師で、 担当弁護士が困っているようなら、 この記事を紹介していただければよいかもしれない。
プロフィール
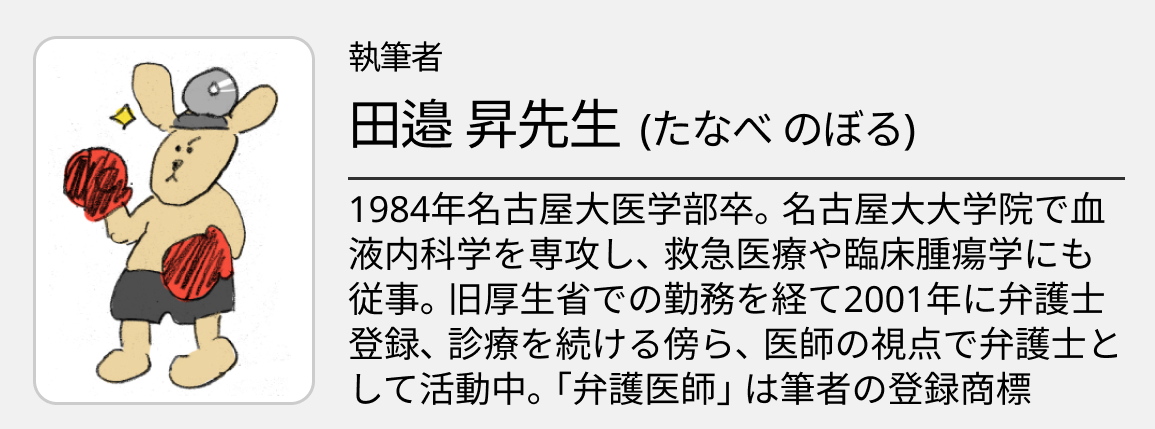
HOKUTO関連コンテンツ
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。