HOKUTO編集部
3ヶ月前
【がんゲノム医療】保険適応外薬をどのように使うか?

がんゲノム医療では、 遺伝子パネル検査で得られた結果に基づく治療選択肢が保険適用外となることも多く、 保険外併用療養費制度は重要な役割を担う。 制度の現状と課題、 今後の見直しについて、 国立がん研究センター中央病院 企画戦略局の鈴木達也氏が発表した。
座長 : 京都大学腫瘍内科 武藤学氏、 東京大学大学院 統合ゲノム学 織田克利氏
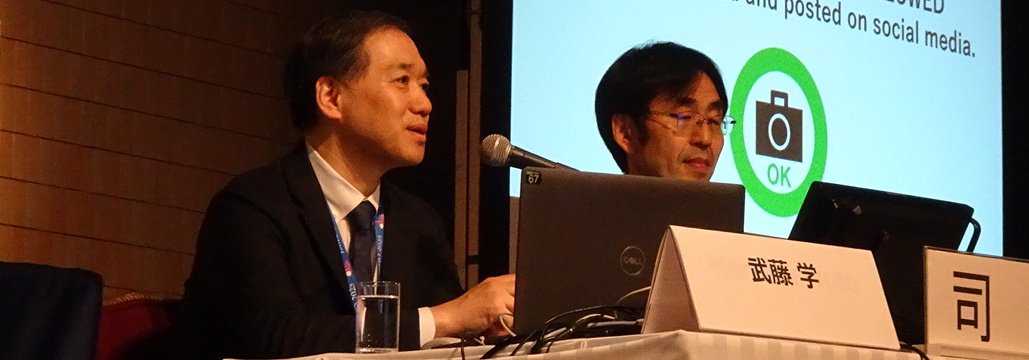
背景と制度の全体像
がん遺伝子パネル検査の普及と現状
がん遺伝子パネル検査の普及に伴い、 遺伝子異常に基づく治療提案が増加している。 がんゲノム情報管理センター (C-CAT) の集計結果によると、 エキスパートパネル (EP) で治療選択肢提示が行われた患者のうち、 実際にEP提示治療を受けた割合は8.2%であった。 治療実施例の71.6%は保険診療であり、 企業治験13.2%、 医師主導治験4.2%、 先進医療0.3%、 患者申出療養は7.5%にとどまっている。 保険診療外治療の利用は限られている現状である。
混合診療禁止と保険外併用療養費制度の位置づけ
混合診療は原則として禁止されており、 違反した場合には保険医療機関の指定取消や保険医登録の抹消に至る可能性がある。 この中で例外的に認められているのが 「保険外併用療養費制度」 であり、 評価療養・患者申出療養・選定療養の3つに分類されている。 制度は、 新たな治療法を保険収載するための評価という側面と、 目の前にいる患者に対して保険外治療を提供する治療アクセス確保の側面から活用されるべきである。
現行制度の仕組みと運用実態
制度の構造
保険外併用療養費は 「基準的部分 (保険適用分) 」 と 「特定部分 (保険適用外で患者から徴収可能な部分) 」 に分かれている。 患者からの相談に対しては、 治験、 先進医療、 患者申出療養、 臨床研究の順に検討し、 治療機会を提供する流れとなっている。
患者申出療養の実績報告
国立がん研究センター中央病院では、 全国のがんゲノム医療中核拠点病院と共同で、 特定臨床研究 「遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく複数の分子標的治療に関する患者申出療養 (NCCH1901) *」 を実施している。 2019年10月~24年11月に753人の患者に対して21種類の治療を提供した。
*日本で薬事承認済み、 あるいは、 評価療養として実施されている遺伝子パネル検査を受け、 actionableな遺伝子異常を有することが判明した患者を対象に、 それぞれの遺伝子異常に対応する適応外薬を患者申出療養制度に基づいて投与し、 治療経過についてのデータを収集することを目的とする。
患者申出療養の課題
同特定臨床研究は、 臨床研究法に基づく規定に加えて、 患者申出療養制度独自の規定が適用されている。 これにより二重規制が発生し、 医療機関や医師の業務負担増につながっている。
例えば、 疾病等報告では、 臨床研究法では当局への急送報告対象ではない、 因果関係のない有害事象 (例 : 試験治療とは無関係の感染症による入院) が、 患者申出療養制度では急送報告対象となっている。 こうした重複規定の解消が必要である。
保険適応外薬に患者がアクセスするには?
薬機法改正の方向性
医薬品の品質・安全性管理の強化や、 供給安定性向上を目的とした薬機法*の改正法案が国会に提出されている。
*医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律
その中で、 活発な創薬活動を促進する環境整備の一環として、 条件付き承認制度の見直しが検討されている。 これにより、 臨床的有用性が合理的に予測可能である場合などに、 迅速な承認が可能となることが期待される。
Single Patient INDの検討
米国で運用されているSingle Patient IND*制度を参考に、 拡大治験の手続き簡素化や、 患者一人を対象とする未承認薬の救済的使用 (コンパッショネートユース**) に相当する制度の導入が検討されている。
*Single Patient IND : 標準治療がない重篤な患者個人に対し、 人道的見地から医師が未承認薬を処方するため、 FDAが個別に許可を与え、 製薬企業が薬剤を提供する治試験の一類型。
**コンパッショネートユース制度 : 標準治療がない生命を脅かす疾患をもつ患者 (個人または患者グループ) に対し、 人道的見地から製薬企業が規制当局の承認を得て未承認薬を提供し、 医師が処方する制度 (米国、 欧州等で導入済み)。
さらに、 制度の円滑な運用には産業界との連携も不可欠である。 実際に国内では、 患者申出療養制度に基づく要望に対して、 製薬企業が無償で試験治療薬を迅速に提供し、 患者への治療機会を拡げるために制度に積極的に協力している事例が報告されている。 こうした企業側の協力体制を含めた枠組み整備が、 今後の制度発展において重要な要素となると考えられる。
まとめ
- 保険外併用療養費制度は、 がんゲノム医療における治療機会提供に不可欠な仕組みである。
- 海外制度を参考に新たな枠組みを導入するとともに、 産業界との連携強化を進めることで、 患者への迅速な治療アクセス確保が期待される。
関連コンテンツ
📖 がん遺伝子パネル検査
神奈川県立がんセンター 廣島幸彦氏
JSMO 2025 オンデマンド配信情報
こちらのご発表はJSMO 2025公式サイトより、 オンデマンド配信でもご覧いただけます。
2025年3月6日 (木) ~4月30日 (水)
※ 「教育講演」 のみ3/6から配信開始
それ以外のセッションは、 3月26日に配信開始
「日本臨床腫瘍学会」 入会について
日本臨床腫瘍学会に入会を希望される方は、下記より入会手順をご確認の上、手続きをお進めください。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。